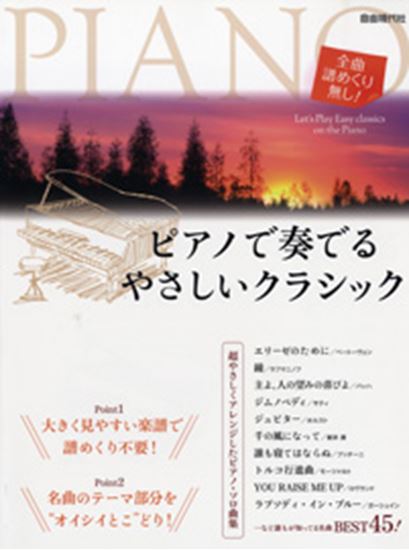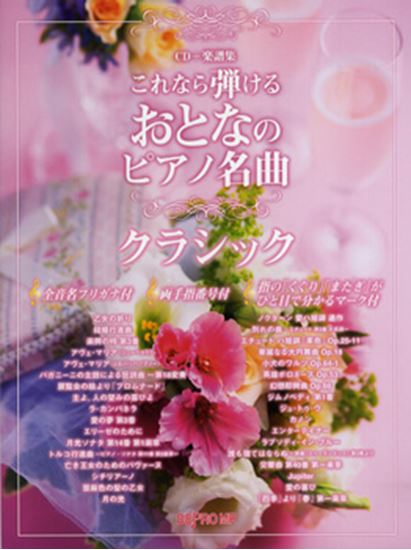作品概要
解説 (2)
総説 : 朝山 奈津子
(2157 文字)
更新日:2008年7月1日
[開く]
総説 : 朝山 奈津子 (2157 文字)
ショパンの2つの《練習曲集》全24曲の起源は、2つある。
ひとつは、バッハ《平均律クラヴィーア曲集》、すなわち24の調によるプレリュードとフーガである。もちろんこうした曲集の編み方自体はバッハの発明ではないが、音楽のあらゆる技法や形式の見本として、学習者のための規範として《平均律》こそが金字塔を打ち立てた。そして、ショパン以前には既に、クレメンティ、カルクブレンナーなど、ショパン以後にはリスト、バルトーク、ラフマニノフ、ピアノ以外にもパガニーニなど、実に多くの作曲家がバッハへのオマージュを込めて《練習曲集》を世に送り出している。18世紀後半の間は、前奏曲と練習曲を一対としたものが、19世紀に入るとこうした組み合わせが時代に合わなくなり、それぞれ別の曲集として作られるようになった。ショパンもまた、《練習曲集》Op. 10, 25のほかに《24の前奏曲集》Op. 28を出版している。
もうひとつの起源とは、もちろん、19世紀前半にさかんに書かれたピアノ教則本としての練習曲集である。これらは、楽曲形式や演奏技法の包括的範例であるとともに、実践的な訓練のためのプログラムだった。ショパンは特に、クレメンティ、モシェレスのものを参考としたが、先達の練習曲集にはない「独自の方法で」みずからの練習曲を書いた。すなわち各曲には、高度な練習曲は高度な音楽であるはずだ、というショパンの信念が反映されている。これが単なる学習課題の範疇を超えてこんにち広く愛されているのは、美しい旋律と和声が織り成す抒情性、まさに高度な音楽であるが故だろう。ただし、これらが実際に彼自身のための練習課題であったことは間違いない。つまり、リストがのちに行なったような、「練習曲」の語をひとつのジャンル名として捉え、当初から演奏会の曲目として、つまり技巧を聴衆に披露する手段としての楽曲をショパンは構想していない。そしてこれが、現代でもピアノ教育の最終段階における課題として学習者に必ず課せられるのは、24曲を通じて、技巧だけでなくショパンの音楽性の真髄をあますことなく学びとれるからである。
《練習曲集》Op.10 は、当代最高のピアニストとして敬意を表し、リストに献呈された(ただしショパンは、作曲家としてはリストをあまり評価せず、後年も友人としては距離を置いた)。この献呈はおそらく、この卓越したヴィルトゥオーゾからの賞賛を狙ったものであり、リストは望みどおり惜しみない賛辞を送った。
12曲の調配列は、次のとおり。
C:-a:-E:-cis:-Ges:-es:-C:-F:-f:-As:-Es:-c:
第1番と第7番にハ長調を置き、前半をシャープ系、後半をフラット系にまとめようした痕跡が窺える(変ト長調は嬰ヘ長調の異名同音調である)。また各曲間には緩やかな調的連関が見られる。すなわち、各関係はつねに一定ではないにせよ、何らかの近親調の範囲にある。なお、《練習曲集》Op.25 第1番は変イ長調(As:)であり、2つの曲集を順番通りに通して演奏する際にも調的な違和感が生じない構成になっている。
第1番
ハ長調であること、同一音型で和声が少しずつ変化することなどから、明らかにバッハ《平均律クラヴィーア曲集》第1巻第1番のプレリュードへのオマージュである。
練習課題は、右手首、右肘の柔軟な使い方と腕の疲労の処理。
第2番
練習課題は右内声の処理。
第3番(「別れの曲」)
練習課題は、両内声の処理、および上声のカンタービレな表現。
第4番
こうした旋律の作り方は、バッハの時代に「紡ぎ出し」と呼ばれたもの。細かな動機が変奏や転回によって徐々に発展してゆく。
練習課題は、正確で粒の揃った右手の発音、各部のコントラスト。
第5番(「黒鍵」)
右手が黒鍵の音のみを使用するため、機能和声の力が殺がれ、一種エキゾティックな響きが生まれる。
練習課題は黒鍵の奏法。
第6番
非対位法的ポリフォニーの例。一貫して3つのパートが維持される。
練習課題は、左内声の処理。
第7番
練習課題は、重音のレガート奏法。
第8番
練習課題は右手のパッセージワーク、特に幅広い音域に渡る分散和音音型。
第9番
練習課題は左手の分散和音音型。
第10番
ショパンの付けたスラーとアクセントによって、両手に異なる拍子が現われている。
練習課題は、両手の対照的アクセント、左手の跳躍を含む分散和音音型。
第11番
練習課題は、両手で幅広い分散和音をつかむこと。
第12番(「革命」)
通称は、リストによる命名。ただし、ショパンがポーランドからパリに向かう途中、1831年にシュトゥットガルトで、前年12月に起こったロシア軍のワルシャワ侵攻を知ったのは事実だが、失望と憤怒のあまり〈革命〉のエチュードを一気に書き上げたというのは俗説である。そもそもこの曲の構想はそれ以前からあったとみられ、前年秋には作曲に着手していた可能性がある。また、確かに即興的なパッセージワークに満ちているが、ショパンの作品が常にそうであるように、即興性はあくまで演出であって、〈革命〉のエチュードもまた細部まで精緻に計算され、よく練られている。
練習課題は、左手の細かな音型の正確な発音、右のオクターヴの奏法、そしておそらくはフォルティシモそのものの演奏。
解説 : 今関 汐里
(5991 文字)
更新日:2019年8月7日
[開く]
解説 : 今関 汐里 (5991 文字)
概説
フランツ・リストに献呈された。
「練習曲」は、その名のとおり、器楽演奏をする際に、必要な技術上の難所を乗り越え、その演奏技術の完成度を高めることを目的としている。もとは、18世紀中ごろ以降、ヴァイオリン教本の中の練習課題を指す語として用いられていたが、19世紀初頭に、ヨハン・バプティスト・クラーマーが《42の訓練課題からなるピアノフォルテのための練習曲》Op. 30、Op. 40(1804、1809)を出版したことをきっかけに、鍵盤楽器の領域においても、新しいジャンルとしても定着していった。その後、ムーツィオ・クレメンティ、フレデリック・カルクブレンナー、カール・チェルニーなどのヴィルトゥオーゾ・ピアニストたちが相次いで練習曲を手掛けている。加えて、ショパンが練習曲集Op.10を手掛ける1830年頃までには、上述の教育的な意図のもとに作曲された練習曲のほかに、ヴィルトゥオーソ演奏家たちによって「演奏会用練習曲」が作曲され、個人的な様式を打そうという試みも新たに興った。例えば、パガニーニのヴァイオリンのための超絶技巧作品からインスピレーションを受けて作曲した、フランツ・リストの練習曲集などが挙げられる。
しかしながら、ショパンの練習曲は、その多くが先人たちの練習曲に比べてカンタービレな性格を備えていながらも、演奏会用に作曲されたのではなく、教育上の意図をもって作曲されたと考えられる。それは、ショパンが弟子たちのレッスンで、自らの練習曲をクラーマーやクレメンティなど先達たちの練習曲の後に弾かせていたという証言からも見て取れる。
各曲の解説
第1番
ハ長調。4分の4拍子、Allegro。
1830年11月作曲。ライプツィヒ、ロンドン、パリで1833年に第2番と共に出版。
ワルシャワのショパン博物館に所蔵されている自筆譜(M/190, M/191)には、第1番と第2番の練習曲にそれぞれ、「練習曲(エグゼルシス)1」、「練習曲(エグゼルシス)2」と記載されており、これらの2作品が一組のものとして意図されたことが判る。
幅広い音域でのアルペッジョの習得を目的としている。アルペッジョを主たる練習課題とした作品は、モシェレスのOp. 70, no. 11やクラーマーのニ短調Op. 30, no. 18などの先人たちの練習曲集にもみられることから、ショパンがこれらの作曲家の練習曲集から影響を受けていたことがわかる。しかしながら、この作品は、より多くをヨハン・ゼバスティアン・バッハに担っている。本作がハ長調で、和声の変化を伴いながらも楽曲を支配する単一の音型は、バッハの《平均律クラヴィーア曲集》第1巻のハ長調の前奏曲からインスピレーションを受けている。
ショパンの弟子のシュトライヒャーによれば、ショパンはこの練習曲について「手も広がり、ヴァイオリンの弓で弾くような和音の効果」を得ることができると語ったという。この言葉が示すように、この作品では、ピアノの4オクターヴを越える音域を端から端へと右手の分散和音が駆け抜けるため、ヴァイオリン奏者が一度のボウイングで、低音から高音までを一気に軽々と演奏するかのような印象を受ける。
演奏の際には、右手の拡張と伸縮が課題となるのと同時に、右手上腕(肘、手首など)の柔軟性が求められる。加えて、低音域から高音域、またその逆へと進行する分散和音を無理なく演奏できるようになるためには、上半身の安定(体幹)を意識することも重要となろう。
第2番
イ短調。4分の4拍子、Allegro。
1830年11月作曲。
ワルシャワのショパン博物館(M/191)とストックホルムの音楽文化財団Stiftelsen Musikkulturens Främjandeに自筆譜が現存する。
第1番の解説にも書いたように、この作品は、第1番と組になって作曲された。
右手の3、4、5の指をくぐらせ、半音階を滑らかに奏し、1、2(時折3)の指で拍頭の内声と弾き分けることが課題となっている。モシェレスのOp. 70, no. 3(ト長調)でも右手の半音階の演奏が課題とされており、こちらでは1、2、3の指が訓練の対象となっている。それに比べ、ショパンの本作品は、より打鍵の力の弱い指の強化を図り、比較的力の加えやすい親指等が16分音符による内声を担うためより一層繊細なコントロールを要求している。左手は、スタッカート付きの八分音符によるバスの単音と三和音からなり、和声的な支えをもたらしている。
A(1~18)-B(19~35)-A(36~49)の三部形式。Bは借用和音の頻出により、一時的に調が不安定となるが、32小節目から低音でイ短調の属音(e)が鳴らされることにより、Aの冒頭の音型と同時に主調イ長調が回帰する。
第3番「別れの曲」4分の2拍子、ホ長調、Lento ma non troppo
1832年8月25日作曲。
資料
スケッチ(ニューヨークのモーガン・ライブラリー所蔵、請求番号Cary 144)
ワルシャワのショパン博物館(M/192)および、ニューヨークのロバ―ト・レーマン・コレクションに自筆譜が所蔵されている。
通称は、1934年に公開されたドイツ製作のショパンの伝記映画『別れの曲』で、本作が主題歌として用いられたことから定着した。
現存する2つの自筆譜の速度記号は異なっており、レーマン・コレクション所蔵の自筆譜には、「Vivace」、ショパン博物館所蔵の自筆譜には「Vivace ma non troppo」と記されている。これらは、出版時にショパンによって「Lento」へと変更されたとみられている。この変更は、ショパンが弟子のグートマンに「私の一生で、これほど美しい歌を作ったことはない」と語っているように、この作品のもつ叙情性をより一層引き立たせるためのものだと考えられる。両手の内声と旋律、バスの弾き分けが重要な課題として打ち出されている。
A(1-21)-B(22-61)-A(62-77)の三部形式。中間部(B)は、Aとは対照的に転調が激しくなるのと同時に次第に荒々しい局面を見せる。鏡に映したように左右で対称的な動きをする6度の重音が8小節にわたって現れ(46-53小節)、その激情は頂点に達し、叙情的なA主題と主調が回帰する。
音楽学者ジム・サムスンによれば、現存する自筆譜には「Presto con fuoco(すぐに続けて)」という指示があるという。このことから、本作品は、熱情的な第4番と対を成す作品と考えられる。
第4番 嬰ハ短調。4分の4拍子、Presto
1832年8月作曲。
第3番が中間部を除き穏やかで美しい旋律に支配されている一方で、第4番は激しく情熱的である。冒頭のアウフタクトは属和音から始まり、1小節目1拍目で主和音に解決してから紡ぎだされている。
正確な打鍵による16分音符のパッセージワークの練習。短い動機が音度や調を変え、転回される、「紡ぎだしFortspinnung」という手法で作曲されている。これは、バッハが活躍したバロックの時代に頻繁に用いられた手法である。例えば、冒頭の1~2小節で登場する右手の16分音符による細かい音型とそれに続く跳躍音型(3小節目)は、5~7小節目で左手によって音度を変えて繰り返される。
第5番「黒鍵」変ト長調、4分の2拍子、Vivace
1830~32年作曲。
ワルシャワのショパン博物館に自筆譜が所蔵されている(請求番号M/193)
黒鍵上での右手の三連符の奏法が課題となっている。ショパン自身は、1839年4月25日にパリに住む作曲家ユリアン・フォンタナに宛てた手紙の中で、クララ・ヴィーク(のちのシューマン夫人)がこの作品を演奏したことに対し「黒鍵のために書かれたことを知らない者にとっては、およそつまらないもの」と不満を漏らしている。ショパンにとって、本作品がこの《練習曲集》の繋がりの中で演奏されることこそ、意味のあることだったのかもしれない。
ショパンは、本作品で、それまで規則的に禁止されていた親指での黒鍵演奏を認め、革新的な運指法を編み出した。白鍵に比べて幅が狭い黒鍵を連続して弾くためには、親指を含む各指をある程度ねかせて演奏する必要があるだろう。
A(1~16)―B(17~49)―A(50~65)の三部にコーダ(66~85)が付く形式。左手の決然と鳴らされる和音の上で、右手が軽やかにパッセージワークを奏でる。
第6番
1830~32年作曲。
ワルシャワのショパン博物館に自筆譜が所蔵されている(請求番号M/194)。
変ホ短調。8分の6拍子、Andante
ポリフォニックな書法の本作品は、3声の弾きわけに加え、豊かな表現能力が求められる。右手の旋律と低音は長い音価で書かれている一方で、16分音符による内声が微妙な和声の変化をもたらす。旋律、バスを長い息のフレーズで維持しながら、細かく揺れ動く内声の和声の変化をいかに表現するかが課題となる。和声の微妙な変化に伴い、ペダルの効果的な踏みかえも重要な鍵となろう。
冒頭主題は8小節からなる。中間部(17小節~)は、著しい転調、音量の増大によって、徐々に感情の高まりを見せる。
第7番
1830~32年作曲。
自筆譜は、ニューヨークのモーガン・ライブラリーに所蔵されている(請求番号MA2473)。
ハ長調、8分の6拍子、Vivace
右手の6度、3度を中心とした重音奏法が課題。しかし、単に重音の課題として弾くだけではなく、その複数の声部を弾きわけることも意図されている。
ハ長調でありながらも、主和音への回帰はほんのわずかに一時的にしか行われず、すぐに新しい動機が紡ぎだされる形で音楽が展開される。33小節、42~43小節では、カデンツが引き延ばされ、主和音への回帰が慎重に行われる。55、56小節目ではへミオラ風のリズムで続く上行音型への緊張感が次第に高められ、最後は華々しく幕を閉じる。
第8番
1830~32年作曲。
ワルシャワのショパン博物館に自筆譜が所蔵されている(請求番号M/195)。
ヘ長調、4分の4拍子、Allegro
右手の16分音符のパッセージの練習。順次進行、跳躍の入り混じるこの音型は、スラーを伴い、下行、上行を頻繁に繰り返す。一方で、左手はバス音と付点リズムを伴い、より躍動的なパートを担当する。
A(1~28)B-(29~59)-A(60~73)-Coda(74~94)の三部形式。中間部(29小節目以降)は一時的に、平行短調であるニ短調で冒頭主題を提示したのち、両手で16分音符のパッセージへと展開していく。コーダでは、まず、右手は16分音符のパッセージを続け、左手は、内声に新しい旋律を伴い、左手と右手の性格は対照的になるが、最終的に両手のユニゾンで煌びやかに終わりを迎える。
第9番
1830~32年作曲。
ワルシャワのショパン博物館に自筆譜が所蔵されている(請求番号M/196)。
ヘ短調、8分の6拍子、Allegro molto agitato
ショパンの練習曲集Op.10の中では、圧倒的に右手の演奏技術を高めるための作品が多い中で、本作品は、左手のための数少ない作品の一つである。左手の16分音符の分散和音による伴奏音型が課題となっている。左手の分散和音は、オクターヴ以上離れた小指の音と親指の音が含まれているため、2、3、4、の指を軸とし、横移動のための手首と肘の柔軟性が求められる。右手の旋律は、1拍目裏拍から、八分休符を挟み途切れ途切れに順次進行し、3小節間続く跳躍進行のぎこちない姿で現れる。
中間部(17小節~)は、借用和音の連続により、調が不安定になり、緊張感と激情が高まっていく。
第10番
1830~32年作曲。
ワルシャワのショパン博物館に自筆譜が所蔵されている(D/21)。
変イ長調、8分の12拍子、Vivace assai
右手の6度の重音、左右で異なるアクセントを適切に演奏するための作品。単音と重音が交互に現れる右手は、単に、重音を正確にとらえるテクニックだけではなく、上声と内声の横の流れを意識することが重要となる。左手の分散和音を正確に、そして冒頭の指示通り「legatissimo」で弾くためには、手首と肘の柔軟性とペダルの微細な操作も必要不可欠である。
煌びやかな主題は、まずレガート、その後13小節目からはスタッカートで提示される。中間部では転調が繰り返されたのち、54小節目から冒頭の主題が回帰し、煌びやかに終止を迎える。
第11番
ストックホルムの音楽文化財団Stiftelsen Musikkulturens Främjandeに自筆譜が所蔵されている。
1830~32年作曲。
変ホ長調、4分の3拍子、Allegretto
両手の分散和音を弾く練習。身体的運動としての側面からみると、両手首、上腕の柔軟性と俊敏性、および、敏速なペダルの踏みかえが課題となろう。
右手の最高音は、旋律としての機能を担っていると同時に、和音の構成音としての役割も果たしている。左手の最低音は、バス音として他の声部を支える役割を果たしているが、バス声部だけに着目すると、右手の旋律の対旋律としても聴かれうる。
高音の煌めくような響きと、和音の揺蕩うようなニュアンスの変化が印象的である。
第12番
ストックホルムの音楽文化財団Stiftelsen Musikkulturens Främjandeに自筆譜が所蔵されている。
1830~32年作曲。
ハ短調、4分の4拍子、Allegro con fuoco
「革命」という、フランツ・リストによる通称で知られる。1830年12月にロシア軍が、ワルシャワに攻め入ったことを知ったショパンが、失意と怒りに突き動かされて、翌年に本作品を作曲したといわれているが、実際には、1831年以前から着手していたとみられている。
右手のオクターヴの旋律、左手の16分音符の細かいパッセージワークが課題となり、左手の指の独立、右手を無理なく広げ、オクターヴを含む和音を無理なく、各音を均等に抑えることが要求される。
ハ短調の属七の和音で緊迫感の中で始まり、その後も10小節目まで主和音が鳴らされることなく進む。右手オクターヴの主題(10小節~)は、左手の低音から高音へと波打つような音型の切迫した雰囲気の中で決然と提示される。転調の激しい中間部の後、5小節目で現れた16分音符での両手のユニゾンが再現され(44小節~)、冒頭主題が回帰する(50小節~)。76小節目からのコーダでは、同主長調であるハ長調が一時的に現れ、一時的な平穏が感じられるが、最後は両手のユニゾンで高音域から低音域に一気に駆け下り、幕を閉じる。
楽章等 (12)
ピティナ&提携チャンネル動画(117件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(53件)
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (166)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)春秋社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)サーベル社

ミュージックランド

カワイ出版

(株)サーベル社

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ミュージックランド

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)リットーミュージック

(株)学研プラス

ミュージックランド

(株)タイムリーミュージック

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
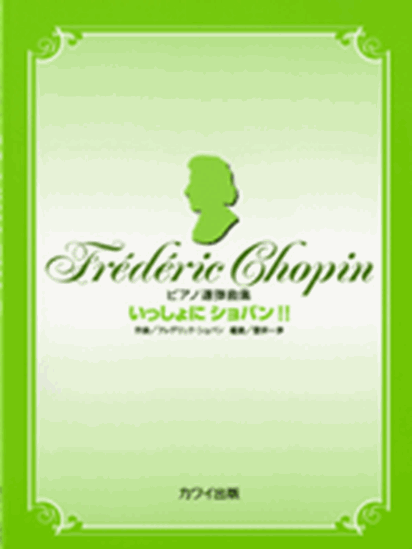
カワイ出版

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ミュージックランド

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ヤマハミュージックメディア

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ハンナ(ショパン)

(株)リットーミュージック

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)共同音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)
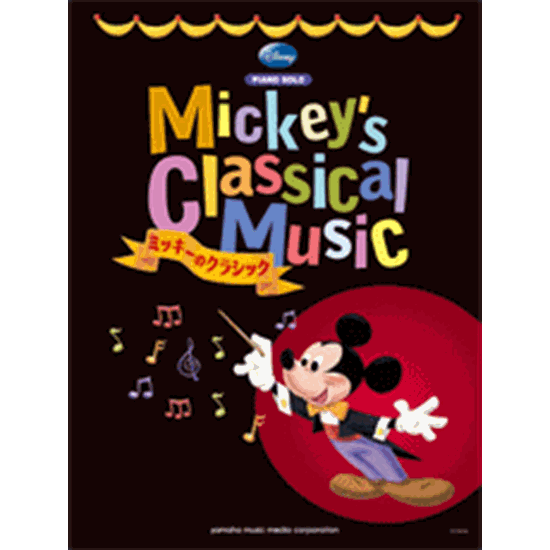
(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

デプロMP

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックメディア

(株)全音楽譜出版社

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)自由現代社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)自由現代社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

ジェスク音楽文化振興会
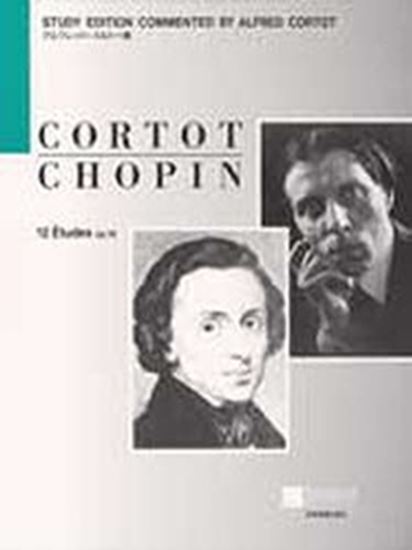
(株)全音楽譜出版社

ヘンレー

ヘンレー

(株)全音楽譜出版社

ヘンレー

ジェスク音楽文化振興会

(株)全音楽譜出版社

ヘンレー

ポーランド音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ロケットミュージック

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)学研プラス

Musikverlag Doblinger

Musikverlag Doblinger

Peters

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

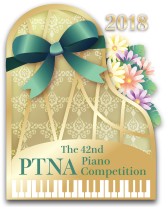 コンペ課題曲:E級
コンペ課題曲:E級  ステップレベル:発展2,発展3,発展4,発展5,展開1,展開2,展開3
ステップレベル:発展2,発展3,発展4,発展5,展開1,展開2,展開3