作品概要
出版年:1827年
初出版社:Haslinger
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:即興曲
総演奏時間:26分00秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (1)
解説 : 髙松 佑介
(5080 文字)
更新日:2019年4月4日
[開く]
解説 : 髙松 佑介 (5080 文字)
総説
シューベルトによる二手のピアノ小品は基本的に、舞曲や変奏曲を除けば、後年に集中して作曲された。4つの即興曲D 899(作品90)も例外ではなく、それゆえにシューベルトの円熟した様式的特色が至る所にあらわれた、彼の代表的なピアノ曲に数えられる。
とはいえ、本曲集の自筆譜に作曲日が記されていないため、詳細な作曲期間は明らかでない。作曲に用いられた五線紙の透かしの調査によれば、自筆譜の作成は1827年夏と推定されており、1827年12月10日に本曲集の出版予告が出たことから、下書きに続いて比較的すぐ細部の彫琢に取りかかったと考えられる。本曲集が成立した1827年後半は、作曲者の夭逝するおよそ1年前である。
「即興曲(Impromptu)」という曲名の名付け親も、明確には分かっていない。なぜなら第1曲の自筆譜には、シューベルトではなく、出版を引き受けたトビアス・ハスリンガーによって曲名が記されているためである。さらに、当時のピアノ曲集には中産階級に親しみやすい題名が与えられたことを踏まえれば、出版社が売れる曲名を提案したという推測が成り立つ。ただし状況証拠からは、シューベルト自身が名付けた可能性も否定できない。というのも、1822年にヤン・ヴァーツラフ・ヴォジーシェクによる《即興曲集》(作品7)がウィーンで出版されており、そのヴォジーシェクにシューベルトがキーゼヴェッター宅の愛好家コンサートで知り会った可能性があるためだ。いずれにしても、続く即興曲4曲D 935の自筆譜には作曲者自ら「即興曲(Impromptu)」と書き入れていることから、シューベルトがこの曲名に満足していたことは間違いない。
だが、これら「即興曲」に対して作曲者が抱いていたものと、受容者および出版社が期待していたものは、どうやら一致しなかったようだ。出版社が当時のピアノ曲集に通例の、小規模で比較的すぐ演奏できるバガテルのような小品集を期待していたのに対し、シューベルトが創作したものは、「ソナタ」に比類しうるような、大規模な作品集だったのである。シューベルトは当初、ハスリンガーから8曲まとめて出版されるという希望を持って、続く4曲に第5番~第8番と通し番号を付けたが、ハスリンガーは1827年12月に冒頭2曲を出版したのち、残る6曲の出版を渋ってしまった。後半の4曲は、それを察した作曲者が別の出版社に売り込んだのに対し、前半の残り2曲は、世に出るまで30年を待たねばならなかった。
即興曲集を初めてソナタに譬えたのは、他ならぬローベルト・シューマンである。シューマンは雑誌『新音楽時報』(1838年)において、作品142の4曲を「ソナタ」として評論を展開した(詳しくは即興曲D 935の解説を参照)。シューベルト作品の良き理解者であったシューマンによる指摘は、出版社が出版に難色を示したことが象徴するように、D 899にも当てはまるようにみえる。しかし厳密に言えば、シューベルトにとって最も重要な構想は、ソナタを念頭に置きつつも、実際にはソナタと差別化を図ることにあったと考えられる。「小品」より「ソナタ」に近いが、ソナタの型にはまることなく自分のスタイルを存分に発揮できる作品――これこそシューベルトが「即興曲」に関して抱いていた考えだろう。シューマンがなぞらえた4楽章制のソナタという枠組みにおいては、ソナタ形式を取る第1楽章が形式的に最も安定していると考えられるため、第1楽章に相当する第1曲を詳細に分析することで、この点について具体的に検討してみよう。
各曲解説
第1曲:アレグロ・モルト・モデラート、ハ短調、4分の4拍子
即興曲集の冒頭に位置する本楽曲は、曲集の4曲を「ソナタ」にたとえるなら、ソナタ形式を取る第1楽章に対応する。したがって本楽曲は、概説で言及したソナタとの関係を考える際の鍵となるため、詳細な形式分析をとおしてシューベルトの作曲上の構想を明らかにしよう。
本楽曲は、オクターヴで幾重にも重なったト音の強打によって幕を開ける。これに続き、単旋律の「問い」と、和声を伴った「答え」が4小節一組で4回演奏される。その際、まるで一つの対象に様々な角度から光を当てるかのように、8小節のフレーズは毎回異なる和声で色付けされている。ハ短調で始まったこのセクションは最終的には変イ長調に終止し、変イ長調で新たなセクションが幕を開ける(第42小節~)。ここで注目すべきは、新たなセクションの主題が、調性と伴奏リズムに関しては冒頭主題と異なるため第2主題として認識されるものの、旋律的には第1主題の冒頭リズムから派生しているという点だろう。つまりこの第2主題は、冒頭主題と親和性を有しているのである。第2主題が第1主題と同様に幾度も反復され、高揚した後、第74小節から新たな主題が8小節間、変イ長調で簡潔に提示される。この主題は、新たな旋律を持つため第3主題と名付けられるが、主題提示の短さと調性に鑑みれば、第2主題の続きとも解釈できる。
この後、第1及び第2主題から派生した5小節の移行部が続いて一段落となるため、ソナタ形式になぞらえれば第87小節までが提示部に相当する。確かに、複数の主題が提示され、ハ短調から変イ長調に転じる点では、ソナタ形式とも解釈されうる(平行調ではないものの、第2主題で長三度下に転調する調関係は、たとえば交響曲第7番《未完成》D 759にも見られる)。だが、第1主題と第2主題が同じ旋律素材を有し、第2主題と第3主題が同じ調性を取るため、「提示部」に置かれた3つの主題はコントラストが弱められ、徐々に移り変わるよう設計されているのである。この点で本楽曲は、主題間でコントラストが生み出される通例のソナタ形式楽章とは一線を画しており、それゆえ相対立する2つの命題の「止揚」というベートーヴェンに刻印された作曲様式とは異なる、シューベルトの特徴が浮き彫りになっている。
第88小節からは、前半部が展開部風にパラフレーズされて再提示される。まず第1主題が主調で回帰する。ここでは第2及び第3主題に由来する三連符の伴奏リズムを伴うのみならず、それがさらにオクターヴの連打となって現れることで切迫の効果が生じている。8小節一組の主題が2回奏されると主題から逸脱し、盛り上がりを見せる。もともと長調だった第2主題はト短調で再現され、十六分音符と後打ちの低声部という新たな伴奏リズムを取り(第125小節)、そして第3主題は、不意打ちの長調転換を通してト長調で回帰する(第152小節)。このように、ここまで全体的に展開部の性格を持っているが、実際に演奏されるものは前半部の再現に他ならない。展開部と再現部を合併するという構造のみならず、再現部の調設計という観点でも、本楽曲はソナタ形式楽章より自由に作られていることが分かる。提示部では可能な限り対立的要素を避け、展開部の性格を再現部に取り込み、自由な調で再現を行う――ソナタ形式がシューベルト特有に解釈されており、本楽曲はソナタの第1楽章に比類されうるにもかかわらず、それとは明確に差別化されている。シューベルトが「ソナタ」と命名しなかった理由は、ここにあると見てよいだろう。
第161小節からは第1主題に基づく結尾部となる。ここでは、長短調のせめぎ合いという、シューベルトが後年に好んで用いた手法が突き詰めて用いられている。この技法は、第3主題がト長調で再現される瞬間(第152小節)に予示されており、結尾部ではさらに鮮烈に用いられる。ハ短調で始まった結尾部は、第167小節において突然、ハ長調に転換する。調転換と急な弱音への転換が相まって、《冬の旅》第1曲のように、曲全体で突出した箇所の一つである。その後はハ長調を基本とするが、第177小節から変ホ音や嬰ヘ音というハ短調の要素が顔を覗かせることにより、長短調の先行きは不透明となる。第192小節で一見ハ長調に落ちついたように見えるが、第194~195小節や第199~200小節でも変ホ音を通してハ短調が垣間見え、ようやく最後の4小節でハ長調が確定する。
楽章全体の調構造は、大枠ではハ短調に始まってハ長調で終わるため、ベートーヴェンによって浸透した「暗黒から光明への道(ペル・アスペラ・アド・アストラ)」の構造と一致しているように見える。だが実際は、幕を閉じる直前まで長調と短調が判然とせず、長調の大団円という一義的な結末とは全く異なるストーリーが描かれている。
ソナタ形式を解釈し直すと同時に、長短調のせめぎ合いによって直線的な楽曲構造を異化する――ベートーヴェン亡き後に独自性を打ち出した、シューベルトの方向性がはっきりと見て取れる。
第2曲:アレグロ、変ホ長調、4分の3拍子
大枠はA―B―A―コーダという三部形式を取る。変ホ長調のA部では、三連音による音階が縦横無尽に駆けめぐる。A部の中もさらに三部形式となっており、中間部(第25~51小節)として同主調である変ホ短調のセクションが挟まれている。冒頭セクションが短縮して再現されると、変ト長調の三和音(第82小節)が異名同音の嬰ヘ長調の三和音として読み替えられ、これを属和音としてB部がロ短調で現れる。異名同音の読み替えを行わずに表記すれば、B部は本来変ハ短調を取るため、A部とB部は三度調の関係にあることが分かる。三度調の進行も、五度圏の深みへと進んでゆく手法も、シューベルトのトレードマークである。
舞踏風のB部は、流れる音階によるA部と性格上のコントラストが付けられているが、伴奏の基本リズムはA部と共通している。B部では、旋律から三連符が取り去られることで、舞踏風の伴奏リズムが前面に押し出される。
A部が回帰したのち、B部が変形されてコーダとして現れる(第251小節~)。コーダはハ短調で始まり、転調を重ねて変ホ短調で閉じるため、曲全体は長調で始まって同主短調へ至るという珍しい調構造を取っている。
第3曲:アンダンテ、変ト長調、2分の4拍子
速度標語にアンダンテをもつ本楽曲は、ソナタにおける緩徐楽章の役割を果たす。ただし、2分の4という拍子も、変ト長調というフラット6つの調性も、当時の「小品」としては異例だったため、初版では弾きやすさを考慮して2分の2拍子のト長調に変更された。ここにも、本曲集がいかに受容されにくかったか、その理由を見て取れるだろう。
三部形式で書かれ、変ト長調を取る主部の旋律は、シューベルトが好んで用いたダクテュロス(長短短)のリズムから紡ぎ出される。中間部では平行調の変ホ短調に転じる。中間部は、調性、強音の出だしや左手の切迫する三連音によって主部と対照的な性格が与えられるが、六連符による中声部の伴奏が貫き通すことで、連続性も確保されている。そして中間部の末尾には、低音の左手によるトリルが置かれる(第53小節)。ピアノ・ソナタ変ロ長調D 960の例で知られる、シューベルトらしい手法だ。
第4曲:アレグレット、変イ短調、4分の3拍子
主部―トリオ部―主部という三部形式を取り、各部とも和音を様々に用いて構築されている。
主部は変イ短調で始まり、右手の分散和音と第2拍を強調した左手のリズムで構成される。これら動きのある4小節と、動きに歯止めをかける四分音符の2小節が交互に繰り返された後、四分音符による和音の連続が8小節続くと、不意に変イ長調へと転じる。長短調の突然の転換は、シューベルトの好んだ手法だ。変イ長調になると、四分音符のフレーズが現れなくなり、さらに冒頭では2小節単位だった分散和音が1小節単位に縮まることで、切迫の効果が生まれる。これを土台として、低声部に初めて旋律的な主題が現れ(第47小節)、不協和音(第68小節)へと徐々に高揚する。それが静まると、例の主題が三連音の分散和音を伴って高声部に奏でられ(第72小節)、十六分音符の分散和音が回帰して主部を閉じる。
トリオ部は、変イ音を嬰ト音として読み替え、嬰ハ短調となる。ここで旋律を支えるのは、分散和音ではなく、和音の連打である。トリオ部も三部形式を取るが、主部が同主長調で回帰し(第139小節)、長短調の転換が行われる。
主部が回帰すると、コーダはなく、変イ長調のまま2つの和音によるカデンツで堂々と締めくくられる。第1曲とは異なり、一義的な長調での終止となっている。
楽章等 (4)
ピティナ&提携チャンネル動画(33件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (29)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社
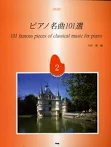
KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)全音楽譜出版社

(株)学研プラス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)学研プラス

Musikverlag Doblinger

 ステップレベル:発展1,発展2,発展3,発展4,発展5,展開1
ステップレベル:発展1,発展2,発展3,発展4,発展5,展開1

























