作品概要
解説 (2)
執筆者 : 朝山 奈津子
(2083 文字)
更新日:2008年7月1日
[開く]
執筆者 : 朝山 奈津子 (2083 文字)
ショパンの2つの《練習曲集》全24曲の起源は、2つある。
ひとつは、バッハ《平均律クラヴィーア曲集》、すなわち24の調によるプレリュードとフーガである。もちろんこうした曲集の編み方自体はバッハの発明ではないが、音楽のあらゆる技法や形式の見本として、学習者のための規範として《平均律》こそが金字塔を打ち立てた。そして、ショパン以前には既に、クレメンティ、カルクブレンナーなど、ショパン以後にはリスト、バルトーク、ラフマニノフ、ピアノ以外にもパガニーニなど、実に多くの作曲家がバッハへのオマージュを込めて《練習曲集》を世に送り出している。18世紀後半の間は、前奏曲と練習曲を1対としたものが、19世紀に入るとこうした組み合わせが時代に合わなくなり、それぞれ別の曲集として作られるようになった。ショパンもまた、《練習曲集》Op. 10, 24のほかに《24の前奏曲集》Op. 28を出版している。
もうひとつの起源とは、もちろん、19世紀前半にさかんに書かれたピアノ教則本としての練習曲集である。これらは、楽曲形式や演奏技法の包括的範例であるとともに、実践的な訓練のためのプログラムだった。ショパンは特に、クレメンティ、モシェレスのものを参考としたが、先達の練習曲集にはない「独自の方法で」みずからの練習曲を書いた。すなわち各曲には、高度な練習曲は高度な音楽であるはずだ、というショパンの信念が反映されている。これが単なる学習課題の範疇を超えてこんにち広く愛されているのは、美しい旋律と和声が織り成す抒情性、まさに高度な音楽であるが故だろう。ただし、これらが少なくとも当初は、実際に彼自身のための練習課題であったことは間違いない。つまり、リストがのちに行なったような、「練習曲」の語をひとつのジャンル名として捉え、演奏会の曲目として、技巧を聴衆に披露する手段として作曲されたものではなかった。そしてこれが、現代でもピアノ教育の最終段階における課題として学習者に必ず課せられるのは、24曲を通じて、技巧だけでなくショパンの音楽性の真髄をあますことなく学びとれるからである。
《練習曲集》Op.25 もまたピアニストとしてのリストに敬意を表し、そのパートナーであったダグー伯爵夫人に献呈された。
調的連関はop.10に比べるといっそう緩やかである。
As:-f:-F:-a:-e:-gis:-cis:-Des:-Ges:-h:-a:-c:
強いていうならば、同じ調が2回登場することがないよう意識されているが、調ツィクルスとしての構想はあまり明確でない。
作曲年代は Op.10 にほぼ続いているが、大半がパリで書かれた。パリで最初の2年間はショパンにとって不遇の期間であったが、やがてサロン・ピアニストとして、またサロンを飾る女性達のためのピアノ教師として注目されるようになる。そこで《練習曲》はきわめてに有効な商品となった。演奏技法を習得できるばかりでなく、練習成果がそのまま、サロン・コンサートでのちょっとした演目として通用するからである。ショパンは《練習課題 Exercices》と呼んでいたものを《練習曲集 Etudes》に改名してまず Op.10 を出版した。さらに12の練習曲を作り、これが Op.25 となった。後者が前者に比して抒情性豊かで個性的だと感じられるなら、それは、ショパン自身の音楽的発展とともに、パリにおけるレッスン課題ないしサロンでの演目としての機能を意識したからと考えられる。
Op.25はまた、ショパン自身が自らの演奏会で好んで取り上げた。
第1番(「エオリアン・ハープ」)
通称はシューマンの批評による。
練習課題は、五指の独立。
第2番
練習課題は、両手で異なる拍子の演奏、および一貫したピアノの音量コントロール。
第3番
右手のいわゆる逆付点リズムは「ロンバルディア・リズム」とも呼ばれる。
練習課題は、食い違うリズムの正確な演奏と、両手のポジション移動。
第4番
練習課題は正確な跳躍。
第5番
優美な中間部には、きわめてショパンらしい旋律を持つ。
練習課題は、右手の拡張と左手の幅広い分散和音。
第6番
ショパンには珍しく、トリルによる曲。
練習課題は、右手の3度重音奏法。
第7番
練習課題は、右の外声と内声の処理、左手によるカンタービレ。
第8番
練習課題は、両手の6度重音奏法。
第9番(「蝶々」)
練習課題は、右手のレガートとスタッカートの交代。
第10番
練習課題は、オクターヴの奏法、および腕の重みの効果的な使い方。
第11番(「木枯らし」)
問いかけるような前奏の4小節は、のちに友人の提案によって付加された。これによって、超絶的な技巧を伴うとはいえ同じ旋律の単調な反復に陥るところだったこの曲が、にわかに抒情性を増した。
練習課題は、右手のパッセージワークと披露の処理。
第12番(「大洋」)
実際に書かれた譜面はもっぱら16分音符の無窮動であるにも関わらず、そのアクセントの効果によってみごとに旋律が浮かび上がる奇跡的手法には、驚嘆を禁じ得ない。
練習課題は、俊敏な両手のポジション移動。
解説 : 今関 汐里
(4949 文字)
更新日:2019年8月7日
[開く]
解説 : 今関 汐里 (4949 文字)
ショパン 練習曲Op. 25
1835~37年作曲。
1837年にライプツィヒ、パリ、ロンドンにて出版。
マリー・ダグー伯爵夫人に献呈。
自筆譜は、国際音楽資料目録(RISM online)によれば、ポーランド国立図書館に所蔵されている(請求番号Mus.217 Cim)。
「練習曲」は、その名のとおり、器楽演奏をする際に、必要な技術上の難所を乗り越え、その演奏技術の完成度を高めることを目的としている。もとは、18世紀中ごろ以降、ヴァイオリン教本の中の練習課題を指す語として用いられていたが、19世紀初頭に、ヨハン・バプティスト・クラーマーが《42の訓練課題からなるピアノフォルテのための練習曲》Op. 30、Op. 40(1804、1809)を出版したことをきっかけに、鍵盤楽器の領域においても、新しいジャンルとしても定着していった。その後、ムーツィオ・クレメンティ、フレデリック・カルクブレンナー、カール・チェルニーなどのヴィルトゥオーゾ・ピアニストたちが相次いで練習曲を手掛けている。加えて、ショパンが練習曲集Op. 10を手掛ける1830年頃までには、上述の教育的な意図のもとに作曲された練習曲のほかに、ヴィルトゥオーソ演奏家たちによって「演奏会用練習曲」が作曲され、個人的な様式を打そうという試みも新たに興った。例えば、パガニーニのヴァイオリンのための超絶技巧作品からインスピレーションを受けて作曲した、フランツ・リストの練習曲集などが挙げられる。
しかしながら、ショパンの練習曲は、その多くが先人たちの練習曲に比べてカンタービレな性格を備えていながらも、演奏会用に作曲されたのではなく、教育上の意図をもって作曲されたと考えられる。それは、ショパンが弟子たちのレッスンで、自らの練習曲をクラーマーやクレメンティなど先達たちの練習曲の後に弾かせていたという証言からも見て取れる。
第1番 「エオリアン・ハープ」
変イ長調、4分の4拍子、Allegro sostenuto
1835年、ショパンが、ドレスデンからパリへと向かう途中で、ライプツィヒのシューマン宅を訪ねた時に、彼の友の前で、当時未完成だったバラード第2番の冒頭と、Op. 25の練習曲の最初の2曲を弾いたとされる。シューマンは、この時ショパンが作品を弾いた様子について鮮明に描写しており、この練習曲第1番について「エオリアン・ハープを思い浮かべられたい」と言及した。以来、本作には「エオリアン・ハープ」という通称が定着した。
エオリアン・ハープAeolian Harpとは、自然の風で音が奏でられる弦楽器のことで、箱状の木に複数の弦が張られている。風の強さや方向、勢いによって、振動する弦が異なり、様々な音色が奏でられる。当時のヨーロッパ(主にイングランドやドイツ)では、家、洞窟、庭園そして避暑のための別荘等に置かれていたため、人々がその音色を耳にする機会は多かったと考えられる。両手が奏でる分散和音のニュアンスが微妙な変化がシューマンにその楽器を連想させたことは明白である。
一方、作曲者であるショパンは、一人の弟子に対して「羊飼いの少年が、近づく嵐を避けて、安全な洞窟に逃げたところを想像してごらんなさい。遠くの方では雨や風が荒れ狂っても、羊飼いは心静かに草笛を吹き、思いつくままにメロディーを奏でているのです」と語ったという。
各指の独立と細かい分散和音をレガートに弾くための手首と肘の柔軟性が課題となる。
第2番
ヘ短調、2分の2拍子、Presto
1835年、ショパンがライプツィヒのシューマン宅を訪れたときに、バラード第2番、Op. 25の第1番と共に演奏したとされる作品。シューマンは、この作品について「独創的で、一度聴いたら忘れられない」とし「眠っている子供の歌のように、人を恍惚とさせ、夢みさせるような優しさがある」と述べ評価している。
両手で異なる拍子を演奏するための練習曲。右手の旋律音型は各音を明確に発音することが求められつつも、刺繍音を多く含みながら展開されていくため、核となる音と刺繍音とをしっかりと区別する必要がある。右手が紡ぎ出しによって展開されていく一方で、左手は、三連符で小さな円を描くような音型を奏でる。
第3番
ヘ長調、3分の4拍子、Allegro
右手と左手で異なるリズム音型を明白に発音して演奏することが求められる。
シューマンは、1854年に出版した『音楽と音楽家』でこの作品を特徴づける華麗な技巧が愛らしい様を語り、ショパンに賛辞を送っている。シューマンの言う愛らしさは、ロンバルディア・リズムやスコッチ・スナップと呼ばれる逆付点リズム等に由来するのだろう。
快活な逆付点のリズムに加えて、右手の16分音符の倚音や、左手に6度音程が多用されているために、どこか異国情緒が感じられる。
第4番
イ短調、2分の2拍子、Agitato
跳躍の練習のための作品。右手は裏拍でオクターヴを含む三和音、左手は拍頭の低音と裏拍の重音(あるいは三和音)の跳躍を正確に打鍵することが求められる。
アルフレッド・コルトーは、この練習曲集の改訂版でこの作品のテクニックについて「一見同じような形であるにも拘わらず、リズムと表情は細かい点に於いて多様」であるとし、この作品から奏者が、そしてスタッカートやポルタメント、レガートなどの様々な奏法を習得できると説明している。
コルトーの言うように、9小節目以降は、左手、右手の内声をそれまで通りにスタッカートで弾きながら、右手最上声部の旋律をいかにレガートで演奏するかが鍵となる。
第5番
ホ短調、4分の3拍子、Vivace、三部形式
A部分では、非和声音を含む右手の旋律と、左手の音域の広い分散和音が練習課題となる。右手の逆付点のリズム、内声の非和声音と、左手の分散和音が滑稽scherzandoな雰囲気を醸し出す。
中間部のB(45小節~)は一変して、重音を含む右手の分散和音が課題となる。低音域と高音域を行き来する分散和音の演奏には、上半身の体重移動と、右手のポジション移動を効果的に行う必要がある。左手には、甘美で息の長い旋律が現れる。徐々に緊迫し激情的になるが(73小節~)、再び平穏を取り戻し(80小節~)、Aへと回帰する。
第6番
嬰ト短調、2分の2拍子、Allegro
右手の三度の重音によるトリルおよび半音階が課題。ショパンは、自らのピアノ作品で、革新的な運指法を生み出しており、この作品にも、以下のようなそれらの特色が見られる。
1.三度の重音による半音階で、同じ指を滑らせて演奏する奏法
2.指の飛び越しや交叉
これらの奏法を取り入れていることにより、ショパンはこの作品でレガートを美しく演奏する可能性を広げていると考えられる。2の指の飛び越しや交叉といった技術には、手首の高さの微妙な調整や、手首や肘の柔軟性が求められるだろう。
右手が華麗な装飾的音型を奏でる一方で、左手が、円を描くような伴奏音型に続いて、下行する三和音でため息の音型を奏でることにより、不安感が高められる。
第7番
嬰ハ短調、4分の3拍子、Lento
緩徐楽章的な性格の作品。左手の旋律のカンタービレな奏法と、右手の内・外声の弾き分けが課題となる。
ショパンは、先立つ《練習曲》Op. 10の第5番〈黒鍵〉でも行ったように、この作品でも黒鍵上での親指の使用を認めている。この作品でいえば、特に12小節目の右手の内声dなどにみられるように、内声をよりレガートに演奏するための工夫であると考えられる。
左手の旋律は、チェロのような温かみのある音色で、情緒的に歌われる。右手の旋律は、基本的にこの左手の主旋律に応える形で、左手の模倣を奏でる一方で、時折左手が装飾音を奏でる際には主導的立場をとる。右手内声は、八分音符による重音を奏で、緩やかなニュアンスの移ろいを表現している。
第8番
変ニ長調、2分の2拍子、Vivace
前の憂鬱な性格の第7番とは対照的で煌びやかな性格をもつ。
両手での6度の重音が課題となる。6度の重音は基本的に、右手でいえば、1、2の指が内声を、3、4、5の指が外声を、左手では、3、4、5の指が外征を、1、2の指が演奏することになるため、隣接する指の切り替えと、両声部を同時に打鍵する能力が求められる。左手は拍頭のバス音と次に続く6度の重音までが跳躍音程であるため、素早いポジションの移動と正確な打鍵が必要である。一方で、右手は最上声部の主旋律がレガートに聞こえるよう、そして内声とのバランスに注意を払うことも不可欠である。
A-B-Aの三部形式。28小節目からコーダとなり、33小節目から6度の重音の半音階で一気に最高音まで駆けあがる。
第9番「蝶々」
変ト長調、4分の2拍子、Assai allegro
右手のオクターヴを含む音型を軽やかに演奏する練習。レガートとスタッカートが交互に登場することから、これらのアーティキュレーションの弾き分けも重要となる。八分音符の伴奏音型を担当する左手は、特に後半に幅広い跳躍を含んでいるため、素早くポジションを移動する必要がある。
ショパンの練習曲の多くと同じように、A-BーAの三部形式である。25小節目で冒頭主題が回帰した後、38小節目からコーダに入る。
第10番
ロ短調、2分の2拍子、Allegro con fuoco、三部形式
A部分(1~29小節)は、両手のオクターヴのユニゾンの練習となっている。重くのしかかってくるような順次進行が特徴的となっており、その音響効果を出すためのペダルの効果的な踏み方や、腕の重みの掛け方の追究が要となる。
3拍子になり、ロ長調へと転調するB部分(30小節~)の右手は、Aと同じオクターヴで旋律を奏でるが、その性格は一変し、穏やかで優美になる。左手は内声と外声に分かれ、時折内声が右手旋律をユニゾンでなぞる。同じ下行音型が14小節繰り返される移行部を経て、Aに回帰する。
第11番 「木枯らし」
イ短調、2分の2拍子、Lento/ Allegro con brio
冒頭の4小節は作曲当初には存在しなかったが、後に友人の提案によって追加された。右手の細かいパッセージワークの演奏が課題となる。主部では、右手は一部を除いてひたすらパッセージワークを奏で、左手が序奏の旋律を担当する。右手のパッセージワークは幅広い音域を行ったり来たりするため、腕だけでなく、上半身全体のスムーズな体重移動が要求される。
この作品は、ショパンがパッセージワークを効果的に演奏するために、小指による親指の飛び越えを認めたことでも良く知られている。
冒頭で懐古的に主題が提示されたのち、一変して主部では、パッセージワークを伴って主題が激しく提示される。中間部で一時的に長調へと転じるが、この激情性は楽曲全体を貫ぬく性格である。
また、1935年に公開されたショパンの伝記映画『別れの曲』では、ショパンが、ロシアのワルシャワ侵攻の知らせを受けた直後、演奏会で衝動的に本作を披露するシーンが描かれているが、これはフィクションである。ショパンはワルシャワ侵攻を知り動揺したことは事実であるが、この出来事と本作に直接的な関連はない。
第12番 「大洋」
ハ短調、2分の2拍子、Molto allegro con fuoco
両手の分散和音の練習。低音から高音へと駆け上がり、高音から低音へと一気に駆け下りてくる。そのため、上半身の効果的な体重移動と、両手の素早いポジション移動が要求される。アクセントや4分音符で示されている旋律音により、分散和音から力強い旋律線が浮かび上がってくる。
コルトーは、自身が校訂した楽譜で、指だけでアクセントやレガートが弾き分けるようにし、ペダルは、主題を形作る音を延ばすために用いるように心がけることが必要であると指摘している。これは、ペダルに依存しすぎて演奏してしまうと、かえって音が濁ってしまい、効果が得られないことを示唆していよう。
急速に上行下行を繰り返す分散和音は、楽曲を通して、フォルテやフォルティシモなど力強く演奏され、最も強いフォルティッシッシモで決然と終わりを迎える。
楽章等 (12)
ピティナ&提携チャンネル動画(94件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(41件)
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (59)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)春秋社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
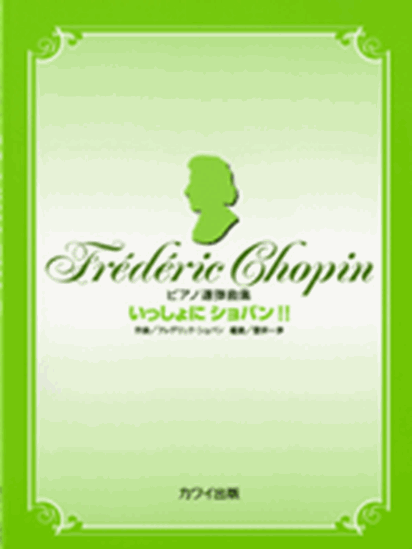
カワイ出版

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ハンナ(ショパン)

(株)リットーミュージック

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ジェスク音楽文化振興会

ヘンレー

ヘンレー

ヘンレー

(株)全音楽譜出版社

ジェスク音楽文化振興会

(株)全音楽譜出版社

ヘンレー

ポーランド音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ロケットミュージック

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Peters

Peters

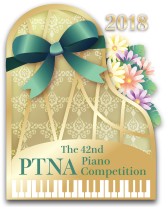 コンペ課題曲:D級
コンペ課題曲:D級  ステップレベル:発展2,発展3,発展4,発展5,展開1,展開2,展開3
ステップレベル:発展2,発展3,発展4,発展5,展開1,展開2,展開3



















































