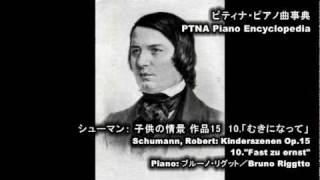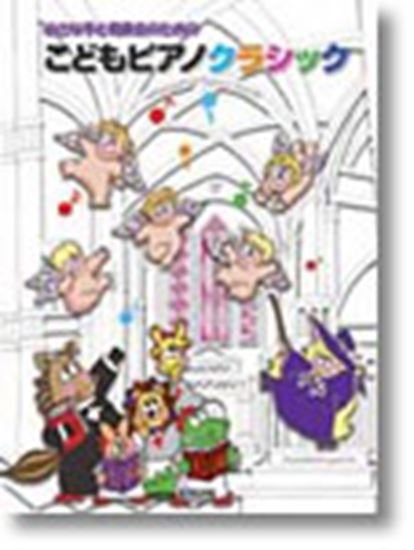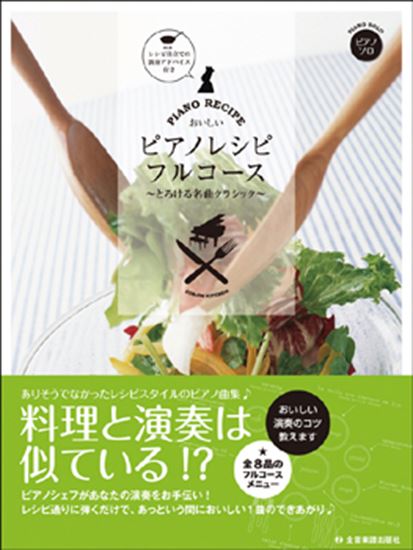作品概要
解説 (2)
執筆者 : ピティナ・ピアノ曲事典編集部
(735 文字)
更新日:2010年1月1日
[開く]
執筆者 : ピティナ・ピアノ曲事典編集部 (735 文字)
(全13曲)
この曲集は‘子供の’というタイトルがついているが、必ずしも子供が簡単に演奏できるといった曲ではなく、大人が見た子供の日常の様子を精密に綴ったもので、シューマンの描写力と表現力の並々ならぬ才能が発揮された傑作の筆頭である。どの曲も複雑な音型はないため子供が演奏することもあるが、各曲の要求する内容を表現するには、極めて高度な表現力が要求される。
1.「見知らぬ国」 / "Von fremden Ländern und Menschen"
行ったことのない国のお話しに耳を傾ける子供。異国への憧れが幻想的に描かれている。
2. 「不思議なお話」 / "Curiose Geschichte"
これは、リズミカルで元気のよいお話。子供の興味をかきたてている様子が窺える。
3.「鬼ごっこ」 / "Hasche-Mann"
鬼ごっこをして走り回る、活発な子供たち。
4.「ねだる子供」 / "Bittendes Kind"
5.「満足」 / "Gluckes genug"
6.「重大な出来事」 / "Wichtige Begebeheit"
7.「トロイメライ」 / "Träumerai"
8.「炉端で」 / "Am Camin"
9.「木馬の騎士」 / "Ritter vom Steckenpferd"
10.「むきになって」 / "Fast zu ernst"
11.「こわがらせ」 / "Fürchtenmachen"
12.「眠っている子供」 / "Kind im Einschlummern"
13.「詩人のお話」 / "Der Dichter spricht"
子供の夢の世界が、ゆっくりと広がってゆく。途中、詩人がレチタティーボで登場し、「見知らぬ国」のお話をそっとしてくれる。
解説 : 鄭 理耀
(3338 文字)
更新日:2019年4月27日
[開く]
解説 : 鄭 理耀 (3338 文字)
総説
シューマンのピアノ独奏曲の中で最もポピュラーなこの作品は、それぞれ標題のついた13の小品からなる。作曲されたのは、おおよそ1838年2月12日から3月17日の約1ヶ月の間である(第6曲と第9曲は1837年秋には成立していた可能性あり)。シューマンの日記から、いくつかのさらに具体的な作曲の日付をたどることができる。2月17日「夜に2、3の小さくて可愛らしい《子供の情景》(を作曲)」、2月24日「小品〈トロイメライ〉を作曲」、2月25日「夜に再び《子供の情景》よりヘ長調(を作曲)、とても美しい」、3月11日「〈満ちたりた幸福〉と《ノヴェレッテン》のポロネーズ(を作曲)」。
作品を書き上げたシューマンは3月17日、婚約中のクララ・ヴィーク(1819-96)に宛てた手紙の中で、次のように述べている。「あなたは以前、〈あなたの目に私は時々子供のように映るでしょう〉と書いていましたが、その言葉が余韻のように残っています。… そこで私は30ほどの小さな曲を書きました。そこから12曲を選んで《子供の情景》と名付けました。あなたはこれを喜んでくれるでしょう。ただし、自分がヴィルトゥオーソであることを忘れてくださいね」。ここには、まず約30曲の小品が作られたこと、そしてその中から12曲を《子供の情景》として選曲したことが説明されている。つまり、この時点で作品は12曲構成として考えられていたのである。最終的に《子供の情景》は13曲構成となり、追加されたのは終曲〈詩人は語る〉であることが知られているが、これがいつ、どのような経緯で曲集に加わったのかについては、わかっていない。なお、最初の30曲のうち《子供の情景》に採用されなかった曲は、数曲が《色とりどりの小品》op. 99(1851年出版)と《アルバムの綴り》op. 124(1853年出版)に入っていることが推測される。
成立過程において、重要な点がもう一つある。それは、この作品が《ノヴェレッテン》op. 21の付録として構想されていた時期があるということである。《ノヴェレッテン》は1839年に全曲出版された全8曲からなる曲集で、おおよその作曲時期は1838年1月から4月、《子供の情景》と同時期である。前述の3月11日の日記は、まさに両作品が同時に書き進められていることが示されている。《ノヴェレッテン》の印刷底本には、タイトルに「ピアノのためのノヴェレッテン、ローベルト・シューマンより友情を込めてフリードリヒ・ショパンに捧げる、2集、子供の物語の付録付き、Op. 16」と記されており、線で消された部分にある「子供の物語」とは、まさに《子供の情景》のことである。ここから、一度はこの作品を《ノヴェレッテン》の付録として計画したが、やはり個別に出版しようと考えを改めたため、線で削除したことが読み取れる。全くの別物である両作品が、実は関連性を持っていたという事実は、作品を理解する上で注目に値する。
この作品は、そのタイトルと曲想から、しばしば「子供のための作品」と誤解されがちであるが、シューマンによると「年長者の回想であり年長者のためのもの」である。フランツ・リスト(1811-86)も「子供が弾くにはおそらく難しすぎるので、子供に読み聞かせる物語のような作品」と解釈していた。シューマンの抱く子供の世界への憧れを具現化したこの作品は、幼いころを思い返す大人のための作品なのである。そして、シューマンが思い描くクララとの幸せな家族像も、ここに投影されていると考えられるのではないだろうか。最後に、13曲それぞれに与えられた標題について、シューマンは「各曲が出来上がったあとに付けたもので、演奏や解釈のためのヒントとして与えただけである」と述べている。
各曲解説
第1曲〈見知らぬ国々と人々〉
ト長調、4分の2拍子。ABAの3部形式。終始、3声部で進行する。右手の上声部に繰り返し現われる主題は、中間部において左手の下声部で展開される。子供がまだ見ぬ異国の地へ、思いを馳せている様子が浮かんでくる。
第2曲〈珍しいお話〉
ニ長調、4分の3拍子。装飾音、休符、付点によるリズミカルで活発な曲調かと思いきや、長いフレーズをもつレガートの柔和な旋律が突然現われる。交互に出てくる2つの部分の対比を楽しんでほしい。
第3曲〈鬼ごっこ〉
ロ短調、4分の2拍子。ABAの3部形式。スフォルツァンド・ピアノとアクセントの付いた右手のスタカートの旋律が印象的で、まさに子供が鬼から必死で逃げ回っているようだ。中間部の最後では、左手に初めてスフォルツァンドが付けられ半音階で駆け上がっていく音型があるが、危うく鬼に捕まりそうになっている光景が浮かんでくる。
第4曲〈おねだり〉
ニ長調、4分の2拍子。第1曲の主題との関連性がはっきりと見られる。子供が甘えて何度もおねだりする様子が窺える。まだ満ち足りていない気持ちを表すかのように、最後はニ長調の属七の和音で曲を終える。
第5曲〈みちたりた幸福〉
イ長調、4分の3拍子。第4曲でドミナントのまま終わった満たされない気持ちは、この曲の冒頭で属調のトニックに解決することにより、標題通りようやく満たされる。右手の主題は左手で模倣されながら、対位法的に進んでいく。
第6曲〈重大な出来事〉
イ長調、4分の3拍子。ABAの3部形式。全体的に和音で進行していく。豊かな音量が響く力強い作品である。中間部では、左手がオクターヴ進行で活躍する。
第7曲〈トロイメライ〉
ヘ長調、4分の4拍子。「トロイメライ」とは、「夢想」や「夢想にふけること」を指す。前曲から雰囲気が一変して、標題通り穏やかで夢見心地な空気が漂う。シューマンはここで1拍目に強拍がくるのを避け、4分の4拍子という拍節を曖昧にすることで、この曲の夢想的な性格を作り上げている。この曲は、4声の4小節からなる旋律が、和声を変えながら8回繰り返されて曲を閉じる。この8回をいかに聴かせるかが、演奏者の腕の見せどころであろう。
第8曲〈炉端で〉
ヘ長調、4分の2拍子。第7曲と同じヘ長調で、同じようにハ音からヘ音への四度上行で曲が始まる。前曲との関連が明らかである。
第9曲〈木馬の騎士〉
ハ長調、4分の3拍子。右手が終始同じ音型で統一されている。一拍目に休符、続いてシンコペーション、三拍目にアクセントが付けられており、シューマンによるリズムの工夫が見られる。
第10曲〈むきになって〉
嬰ト短調、8分の2拍子。第9曲に続いて、シンコペーションで静かに曲が展開していく。原題「Fast zu ernst」の「ernst」とは、「まじめな」や「真剣な」を意味する。子供がひたむきに何かに取り組んでいるのだろうか。
第11曲〈こわがらせ〉
ト長調、4分の2拍子。ゆるやかで和やかな主題部分と、急速でおどけたような挿入部分が交互に現われる、メリハリのある作品。4度出てくる主題部分では、右手の旋律が左手で模倣される。
第12曲〈子供は眠る〉
ホ短調、4分の2拍子。ABAの3部形式。Aの部分ではロ音を中心に、同じリズムが右手と左手で交互に繰り返され、このゆりかごのような動きが聴く者を夢うつつの状態へ導く。Bの部分では同主調のホ長調に転調する。終始静かなまま、主和音に解決されずに曲が終わる。眠りの世界が限りなく広がっていくようである。
第13曲〈詩人は語る〉
ト長調、4分の4拍子。ABAの3部形式。Bの部分にはレチタティーヴォが置かれているが、この旋律は《幻想小曲集》op. 12より第2曲〈飛翔〉の内声部から引用されていることが指摘されている。シューマンは、一度用いた素材や旋律を、他の作品でも再び用いることが多々あり、これもその一例であると考えられる。クララはこの作品について、「この曲のなかで語る詩人はわたしのいとおしい方ではないでしょうか」と述べており、標題の「詩人」をシューマンと解釈していたようである。
楽章等 (13)
ピティナ&提携チャンネル動画(124件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (200)
![やさしいピアノ名曲集2[発表会用/CD付] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/46.jpg)
(株)エー・ティ・エヌ

(株)エー・ティ・エヌ
![子どものピアノ小曲集3[発表会用]/CD付 - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/55.jpg)
(株)エー・ティ・エヌ

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)オンキョウパブリッシュ〇

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)音楽之友社

(株)リットーミュージック

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー
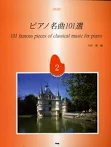
KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド

(株)全音楽譜出版社

(株)サーベル社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ミュージックランド

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)共同音楽出版社

ミュージックランド

(株)オンキョウパブリッシュ〇

(株)リットーミュージック

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)自由現代社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)学研プラス

(株)オンキョウパブリッシュ〇

ミュージックランド

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)リットーミュージック

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

カワイ出版

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社
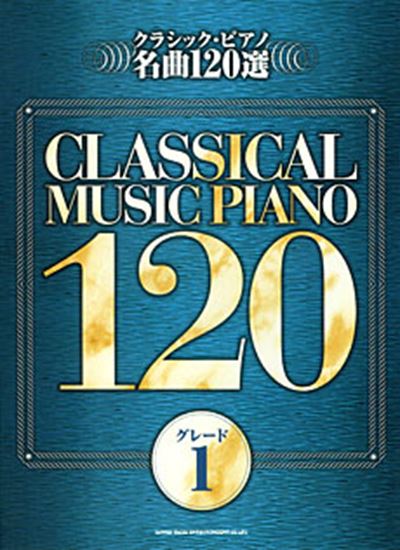
(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックメディア

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)
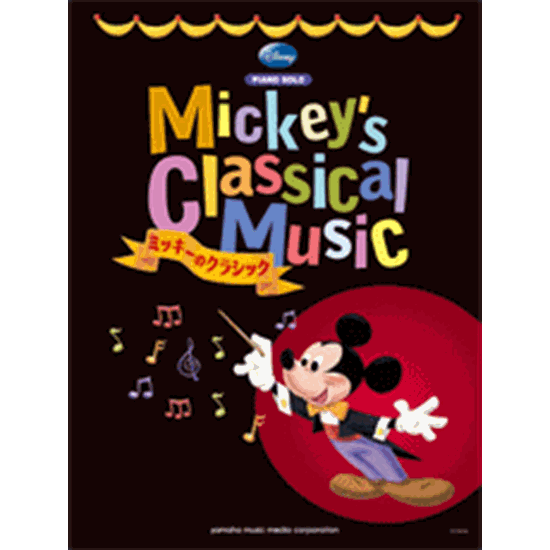
(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

(株)オンキョウパブリッシュ〇

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

デプロMP

成美堂出版(株)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)共同音楽出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

デプロMP

(株)サーベル社

ミュージックランド

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

(株)全音楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド
![小学生のための ピアノ名曲集B [バイエル終了程度] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/1764.jpg)
(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

(有)中央アート出版社

(株)オンキョウパブリッシュ〇

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント
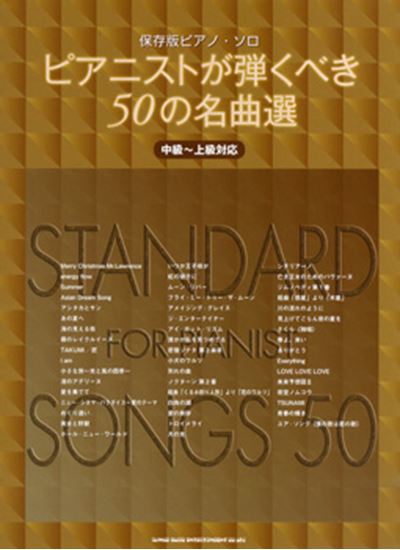
(株)シンコーミュージックエンタテイメント

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社
![ビギナーのためのピアノ/名曲シリーズ1 [ピアノソロ] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/1852.jpg)
ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)東音企画(バスティン)

プリズム((株)あいおんプリズム事業部)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(有)中央アート出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)学研プラス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Musikverlag Doblinger

Musikverlag Doblinger

Musikverlag Doblinger

Musikverlag Doblinger

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

Breitkopf & Hartel

ミュッセ

 ステップレベル:応用7,発展1
ステップレベル:応用7,発展1