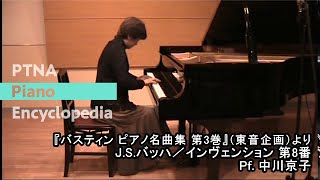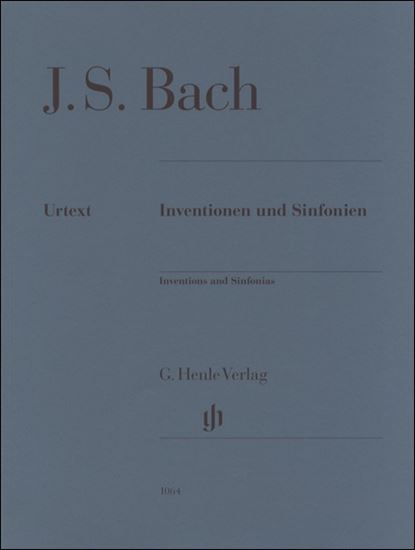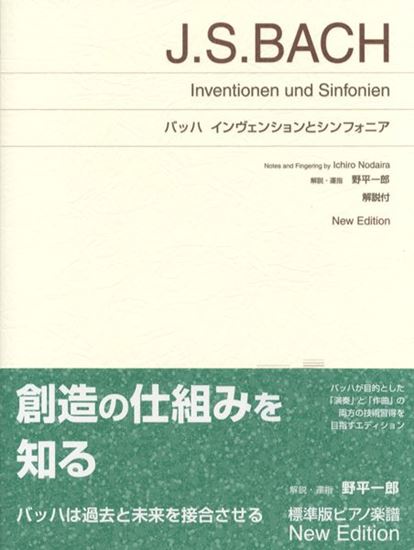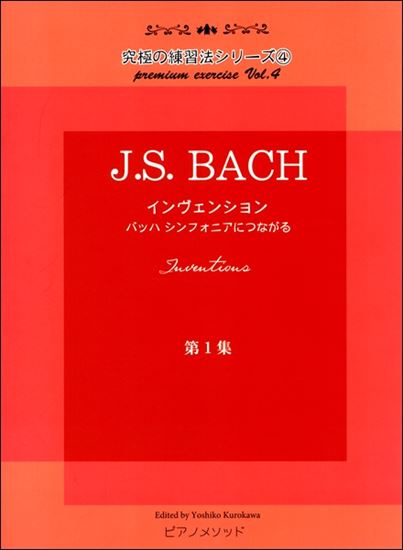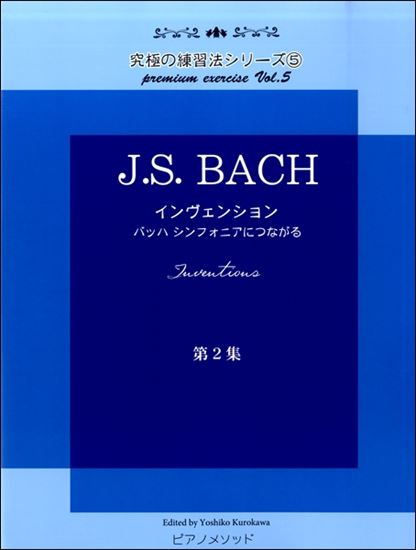作品概要
解説 (2)
総説 : 朝山 奈津子
(2103 文字)
更新日:2010年1月1日
[開く]
総説 : 朝山 奈津子 (2103 文字)
「クラヴィーアの愛好者、とくにその学習希望者に、(1)二つの声部をきれいに弾きこなすだけでなく、更に上達したならば、(2)三つのオブリガート声部をも正しく、かつ、手際よく処理し、あわせて同時にインヴェンツィオをたんに得るだけでなく、それをたくみに展開し、そしてとりわけカンタービレの奏法をしっかりと身につけ、しかもそのかたわら作曲への強い関心をも養うための明確な方法を教示するところの、正しい手引き。アンハルト=ケーテン侯宮廷楽長ヨハン・ゼバスティアン・バッハ これを完成す。1723年。」
バッハは完成した曲集の扉に自らこのようにしたためた。《インヴェンション》と《シンフォニア》は、長男フリーデマンのレッスン用の小品を集めて改訂したものであり、その成り立ちから既に教程としての性質を持っている。しかし、ここに書かれていることの真意はいったいなんだろうか?
バッハは音楽家を育てるのに、両手を使った鍵盤音楽の演奏技術を身に付けさせることから始めた。手の運動と結びつけることで、より自然な音楽性を習得するためである。ここで用いられるのはしかし、バロック時代特有の通奏低音、すなわち低音に対して適切な和音を右手で補充するという書法ではない。すべての声部が掛け替えのない「オブリガート」パートであり、それぞれを「カンタービレ」に演奏すべく書かれている。そして独立した各声部は、和声の中でひとつに溶け合う。厳格対位法とカンタービレ、旋律と和声。一見すると簡明な2声および3声の作品群は、実は「多様なものの統一」という16-17世紀の大きな美学的命題を負っているのだ。
バッハのメッセージの中の「インヴェンツィオ」という言葉もまた、古い音楽の美学と作曲法に関わりがある。この語は修辞学に由来し、「着想」と訳されることが多いが、本来(「発明」ではなく)「発見」を意味する。つまり、自分が伝えたい内容にふさわしい表現を見つけだすことである。そのためには、できるだけ多くの修辞表現(フィグーラ)を学び、その配列の方法を知らなくてはならない。《インヴェンション》と《シンフォニア》はその範例として書かれており、バッハの持てる鍵盤音楽のきわめて多様な様式を見ることができる。いってみればバッハの音楽世界の縮図である。
したがって、「インヴェンション」とは決してなんらかのジャンルや楽式を表す言葉ではない。バッハ以前のドイツの作曲家にはこれをタイトルとした曲集がいくつか見られるが、形式の上で統一や共通点はない。バッハ以降、もしも楽曲分析などで一般的な意味での「インヴェンション」という表現が用いられるとすれば、それは簡明でありながらよく整った、様式や技法の上で模範的な対位法作品、というポジティヴな文脈において、あるいはバッハの珠玉の作品へのオマージュとしてであろう。
作曲年代は1720-23年、バッハがケーテンの宮廷に勤め、数多くの器楽曲を生み出した時代にあたる。1720年にバッハは、10歳になった長男フリーデマンのために音楽帖を作り始めた。この中に2声の《プレアンブルム》と3声の《ファンタジア》がハ長調、ニ短調、ホ短調、ヘ長調、ト長調、イ短調、ロ短調、変ロ長調、イ長調、ト短調、ヘ短調、ホ長調、変ホ長調、ニ長調、ハ短調の順で書き込まれている(ただし、3声のハ短調は欠落)。配列は調号の数に関係する。これを1723年に清書した際には、楽曲そのものを改訂したほか、配列も全音階順に改め、2声を《インヴェンション》、3声を《シンフォニア》と名づけた。
※「シンフォニア」の項もご覧下さい。
第5番 変ロ長調 BWV 776
主題と対主題が冒頭から同時に提示されるため、二重フーガの様相を呈す。2つの主題には、上行と下行、装飾音付きのゆったりとしたリズムと16分音符による無窮動、分散和音と順次進行といった、あらゆる対比が含まれている。そのため、あまり複雑な対位法的処理をせずとも、各動機の声部を入れ替えるだけで多彩なヴァリエーションが生まれる。奏者は更に、装飾音を自由に施して、曲の経過に独自の色づけをすることができるだろう。
この曲がごく少ない動機のみでも単調にならない理由は、もうひとつ、模続進行を巧みに用いて形成される調推移にある。主題そのものが属音上に終止するため、Es-Durで開始したのちすぐに属調(B-Dur)へ移る。その後、冒頭の音型を通常2回のところ、左手も含めて5回繰り返すことで、c-Moll への道を開く。が、第15小節で本来オクターヴの分散和音上行を短7度にすることで、f-Moll を確保する。この手法が次の4小節でも繰り返され、一旦 b-Moll へゆく。しかしそれも、第20小節から上行へ模続するはずの冒頭動機が下行し、再び f-Moll へと押し戻されてしまう。このように中間では、安定しない短調の領域が続いたが、第24小節の跳躍を両手とも2度で多く飛ぶことで、遂にAs-Durへと抜け出し、次の提示でEs-Dur への回帰を果たす。このように、曲全体が主調を巡るドラマを織り成している。
解説 : 髙松 佑介
(5506 文字)
更新日:2020年9月18日
[開く]
解説 : 髙松 佑介 (5506 文字)
総説
《インヴェンション》と《シンフォニア》という2つの曲集は――バッハが序文に明記しているように――「正しい手引き」という教育的目的で成立した。
現在知られている《インヴェンション》や《シンフォニア》の各曲は、これらの曲集にまとめられる前、バッハが長男のための教材として1720年から数年かけて編纂した『ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集』という音楽帖に収められていた。この音楽帖を見ると、記譜法や装飾音の説明、指使いの練習に続けて、自作・他作を含む小品集が並んでいる。これら小品集として、メヌエットやプレアンブルム(《平均律クラヴィーア曲集第1巻》に含まれることになる楽曲もある)のあと、《インヴェンション》と《シンフォニア》に収められる作品群が「プレアンブルム」と「ファンタジア」というタイトルで書かれている。
このように、この音楽帖には様々な曲が収められていたが、のちに《平均律第1巻》と《インヴェンション》および《シンフォニア》は、それぞれ別の表紙を伴った独立した曲集としてまとめられることとなった。つまり、「インヴェンションとシンフォニア」と「平均律」は、同じ目的をもって同時期に生まれたものの、異なる力点を置いて再編されたのである。
本曲集では、タイトルが音楽帖の「プレアンブルム(前奏曲)」から「インヴェンツィオ」へと変更された。バロック時代には、古代ギリシア・ローマの弁論術を元にして音楽理論の構築が進められ、作曲の手順に関しても修辞学に倣って「インヴェンツィオ(着想)」―「ディスポジツィオ(構成)」―「エラボラツィオ(彫琢)」という三段階で理論化された。つまり「インヴェンション」とは、曲の核となる楽想を「着想」することを指している。ただしこれは単に旋律をひらめくだけではなく、楽曲全体を構築できるような創意に富んだ主題を案出し、更なる作曲プロセスや即興的な発展へと結びつけていくことをも含意している。当時、作曲と演奏は分かちがたく結びついていたため、作曲と演奏の両方の技術を正しく習得できるようにまとめたのが《インヴェンション》と《シンフォニア》という2つの曲集なのである。
《インヴェンション》は2声で書かれ、クラヴィコードを想定して作曲されたと考えられる。曲集全体は、第1曲のハ長調から第15曲のロ短調まで、音階を上るように配列されている。
文献紹介
市田儀一郎,1971,『バッハ インヴェンションとシンフォニア』,東京:音楽之友社.
樋口隆一他,1996,『バッハ全集 第11巻 チェンバロ曲[1]』,東京:小学館.
磯山雅,小林義武,鳴海史生編著,1996,『バッハ事典』(全作品解説事典),東京:東京書籍.
ゲック,マルティン,1998,『大作曲家 バッハ』,大角欣矢訳,東京:音楽之友社.
小鍛冶邦隆,中井正子,2005,『バッハ インベンション――分析と演奏の手引き』,東京:ショパン.
丸山桂介,2020,『バッハ インヴェンチオのコスモロジー』,東京:春秋社.
Küster, Konrad (ed.), 1999, Bach-Handbuch, Bärenreiter & J. B. Metzler.
第1番 ハ長調、4/4拍子
この曲の「インヴェンツィオ(着想)」は、両声部の模倣によって提示される主題に認められる。この簡潔な主題は、第2小節で5度高く反復されたり、第3小節から冒頭部分が摸続進行に使われたりと、曲全体を通して対位法的に展開できるよう工夫されている。
曲は、3つの主題提示部から構成される。冒頭6小節の第1提示部のあと、ト長調~ニ短調~イ短調の第2提示部(第7~15小節)、イ短調から主調のハ長調へと至る第3提示部(第15~22小節)が続く。
「エラボラツィオ(彫琢)」として、簡潔な動機を発展的に用いる技法が挙げられる。例えば、第3小節からの摸続進行では冒頭動機の反行形が用いられ、さらにこの摸続進行の反行形が第19小節から現れる点、第15小節から両声部が冒頭動機とその反行形を交互に模倣する点などに見られるだろう。
第2番 ハ短調、4/4拍子
この曲の「インヴェンツィオ(着想)」として、カノンの技法を念頭に置いた主題が案出されている。《ゴルトベルク変奏曲》(BWV 988)以前に作曲された唯一のカノン風の鍵盤曲という点で、注目すべきだろう。
曲全体は3部分に区切られる。まず第1の主題提示部では、上声部を下声部が2小節遅れで追う(第1~10小節)。続く10小節間では、下声部が属調のト短調で第1展開部の上声部を反復し、これを上声部が追いかけるよう設計されている。つまり第2提示部では、第1提示部と同じ構造を取りつつ、声部の転回が行われている(第11~20小節)。最後の7小節はカノンになっておらず、2小節の導入ののち主題の模倣によってコーダを形成する。
第3番 ニ長調、3/8拍子
冒頭12小節で主題が提示され、その最後のカデンツ(第11~12小節)が曲全体の構造を決定する。中間部は2部分から成り、それぞれロ短調のカデンツ(第23~24小節)とイ長調のカデンツ(第37~38小節)で区切られる。第43小節から冒頭主題が回帰して最後の主題提示部を構成するが、曲の末尾には偽終止(第53~54小節)と完全終止(第58~59小節)と2回カデンツが置かれており、コーダが繰り返されるのは《インヴェンション》において珍しい。このように、カデンツで曲想が変わる構造は、バロック時代のコンツェルトの原理であるリトルネッロ形式を思わせる。
第4番 ニ短調、3/8拍子
上声部が提示する冒頭2小節の主題を、曲全体を通して絶えず反復することによって1曲が構成されている。この16分音符による主題では、2小節目に置かれた減7度の跳躍が厳しい曲調を作り出している。
16分音符による主題は連綿とつながってゆくが、それが途切れる箇所はカデンツを形成し、楽曲構造の区切れに対応している(第17、37、48、51小節)。この主題は、摸続進行として反復されたり(第5小節から上声部、第11小節から下声部)、反行形として用いられたり(第22~25小節)と、様々に形を変えて現れる。
第5番 変ホ長調、4/4拍子
フーガ的な書法で書かれた曲で、3つの主題提示部から成る。
まず冒頭で上声部が4小節の主題を提示すると、続く4小節で下声部が属調で応答する(第1提示部)。冒頭動機の摸続進行から成る3小節の間奏を挟んだのち、第12小節からハ短調とヘ短調で主題が提示される(第2提示部)。再び3小節の間奏と、そして主題の冒頭動機のみの提示(下属調)・応答(主調)を経過して、第27小節から主調で主題を回帰し(第3提示部)、曲を締めくくる。
第6番 ホ長調、3/8拍子
この曲に特徴的な「インヴェンツィオ(着想)」は、両声部のシンコペーションだろう。冒頭では、下声部が全音階を上行するのに対し、上声部は半拍ずれて半音階を下行する。さらに、この4小節の主題は両声部を交換して反復される(このように複数の声部を交換する対位法の手法を転回対位法という)。
また、《インヴェンション》のうちで唯一、曲中の反復記号を伴う点も注目すべきである。この反復記号で区切られた前半部(A)ではホ長調から属調のロ長調へと進行し、後半部は展開的な中間部(B)と主調のまま曲を閉じるAから成っている(||:A:||:BA:||)。この図式(Aの回帰を伴う2部分形式)は、19世紀前半に「ソナタ形式」として理論化されることとなる器楽形式への接近を示している。
第7番 ホ短調、4/4拍子
この曲は、第1番と同様に、簡潔な動機の操作によって構成されている。冒頭で提示される動機は、音の高さを変えて反復されたり(摸続進行)、反行形として用いられたりと様々な形で繰り返される。
曲全体は3つの主題提示部から成る。第1提示部は第1小節から、主題の模倣や摸続進行によって展開し、第7小節で半終止する。第2提示部(第7~15小節)では、ト長調の属音を保続音として、低声部が冒頭動機を加工して展開する。保続音のあとも展開が続くが、主題の1小節目を16分音符の前半部と付点リズムを含む後半部に分け、それぞれを別々に加工している。第15小節から(第3提示部)は、低声部を保続音として上声部が自由な発展を行い、それを低声部が引き継ぐことで、第20小節からの終結部を準備する。
第8番 ヘ長調、3/4拍子
ファンファーレのような上行形の分散和音で幕を開ける、躍動的な曲。3つの主題提示部から成り、第1提示部と第3提示部は下声部が1小節遅れで上声部を追うカノンとなっている。
第2提示部(第12小節~)は、下声部が提示するハ長調の主題を上声部が模倣することで幕を開けるがカノンが続くのではなく、ト短調を皮切りに、既出の動機を用いて転調を重ねる。
第3提示部(第26小節~)からは再びカノンとなるが、主題冒頭の再現は省略され、第4~12小節に対応している。
第9番 ヘ短調、3/4拍子
《インヴェンション》各曲の主題が基本的に簡潔であるのに対し、この曲の主題は4小節と比較的長く作られている。情感豊かなヘ短調の旋律は、とりわけバッハが序文に記した「カンタービレの方法」を学ぶのに適している。
楽曲はちょうど2部分に分けることができる。前半部では、まず上声部が主題を提示し、これに寄り添うかのように下声部が対位主題を奏でる。そして第5小節から両声部が転回し、第9小節から主題と対位主題を用いつつ転調してゆく。後半部(第17小節~)では、冒頭とは逆に、下声部が属調で主題を提示する。
第10番 ト長調、9/8拍子
分散和音音形による快活な曲。即興的な技法との関連が指摘されており、まさに分散和音で構成された主題は、和声進行を考えながら即興演奏を行うのにふさわしい。それが証拠に、和声は基本的に1小節ごとに変化し、同じ音形を高さを変えて繰り返す手法(摸続進行)による転調も多用されている。バッハの時代には演奏と作曲が分かちがたく結びついていたため、いかに即興技術によって演奏と作曲を行うかを示す教育的な意図も含まれているだろう。
全体は2部分で構成される。後半部(第14小節~)では下声部が属調で主題を提示し、上声部が5度上で応答する。
第11番 ト短調、4/4拍子
悲哀に包まれた曲調をもっており、これは4度の半音下行によって裏打ちされている。
バロック時代において、音楽の本質および目的は「情念 Affekt」の表現や喚起にあると捉えられていた。これは、現在想定されるような人それぞれ異なる「感情」ではなく、「喜び」「悲しみ」「苦しみ」など類型化され客観化されたものを指している。冒頭で下声部が奏する対位主題は、「ト―嬰ヘ―ヘ―ホ―変ホ―ニ」と4度の音域を下行する半音階を核としており、これは「悲しみ」の情念を表現するための常套手段である(「パッスス・ドゥリウスクルス」と呼ばれる)。この半音階を基礎とする対位旋律は、常に主題と組み合わせて現れる。
曲は2部分で構成され、第11小節から後半部となる。前後半とも、16分音符がいずれかの声部で鳴り響き、曲全体を貫いて流れるよう設計されている。
第12番 イ長調、12/8拍子
3回の主題提示部と2回の間奏から構成される。冒頭2小節では上声部が主題、下声部が対位主題を提示し、両声部を交換して5度上で反復される。この主題は、第2提示部において嬰ヘ短調(第9小節~)と嬰ハ短調(第11小節~)で現れた後、第3提示部において下声部が主調で奏する(第18小節~)。
前曲と同様に、16分音符が――曲尾のカデンツを除いて――曲全体を通して絶え間なく鳴り響くよう構築されている。
第13番 イ短調、4/4拍子
この曲も、第11・12番と同様に、16分音符が常に鳴り響くことにより一種の無窮動の性格をもっている。主題は分散和音によって構成されており、同じ音形を高さを変えて繰り返す手法(摸続進行)の多用も相まって、和声変化によって曲想が目まぐるしく変わる点も特徴的である。
この曲は前後半に分けられ、前半部もまた2つの主題提示部から成る。第2提示部(第6~13小節)は、第1提示部(第1~6小節)より展開的で少し長いものの、基本的には第1提示部から両声部を交換し、平行調に置いたものとなっている。
第14番 変ロ長調、4/4拍子
祝祭的な曲調をもつ。主題は分散和音を基本として、32分音符の経過音を伴う走句が華を添える。
曲は4つの部分から成る。第1部(第1~5小節)で主題が提示されたあと、第2部(第6~11小節)で声部交換によって属調で主題が提示されつつ、転調する。第3部(第12~16小節)では下声部を上声部が追うカノンが展開され、第4部(第16~20小節)では主題がカノン風に再現する構成となっている。
第15番 ロ短調、4/4拍子
対位法的な書法を用いながらも比較的自由な形式で書かれる「カプリッチョ」の性格をもつ。大まかには、3つの主題提示部(第1~7小節、第12~15小節、第18~22小節)と間奏(第7~12小節、第16~19小節)に分けられ、主題提示部では主題が様々な調で提示され、間奏の部分では一定の音形を高さを変えて繰り返す摸続進行によって転調が行われる。
曲の末尾には「このあとに15曲の3声のシンフォニアが続く」と明記され、学習者は次のステップへと進むよう意図されている。
楽章等 (15)
編曲・関連曲(1) <表示する>
トンプソン: バッハの5つの二声インヴェンションへの第2ピアノ
総演奏時間:7分00秒
ピティナ&提携チャンネル動画(120件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(11件)
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (104)
![やさしいピアノ名曲集3[発表会用/CD付]時代別編纂 - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/45.jpg)
(株)エー・ティ・エヌ
![やさしいピアノ名曲集2[発表会用/CD付] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/46.jpg)
(株)エー・ティ・エヌ

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

カワイ出版

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社
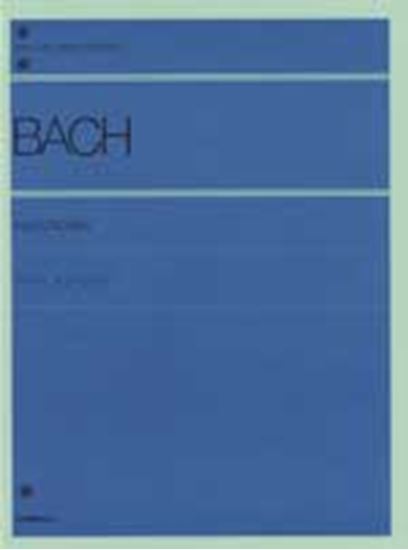
(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)リブロポート

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

カワイ出版

(株)渓水社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)エー・ティ・エヌ

(株)全音楽譜出版社

カワイ出版

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

(株)東音企画(バスティン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)東音企画(バスティン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)学研プラス

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Neil A. Kjos Music Company

Musikverlag Doblinger

Musikverlag Doblinger

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

Peters

ミュッセ

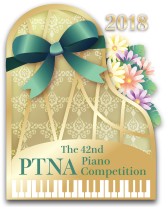 コンペ課題曲:C級
コンペ課題曲:C級  ステップレベル:応用3,応用4,応用5,応用6,応用7,発展1
ステップレベル:応用3,応用4,応用5,応用6,応用7,発展1