作品概要
解説 (1)
執筆者 : 朝山 奈津子
(1494 文字)
更新日:2007年6月1日
[開く]
執筆者 : 朝山 奈津子 (1494 文字)
「クラヴィーア練習曲集。プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグ、メヌエットおよびその他の当世風舞曲よりなる。愛好家の心を楽しませるために、ザクセン公およびヴァイセンフェルス公の楽長にしてライプツィヒの音楽監督、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが作曲。作品1。作曲者により刊行。1731年。」
1726年、バッハは自作品の出版を開始した。ライプツィヒに赴任して3年半を経た頃のことである。出版に際してバッハの計画は慎重と周到をきわめた。曲種としては、当時の最新流行であるギャラントな組曲を選んだ。規模は《イギリス組曲》のように長大でなく、《フランス組曲》のように華奢でなく、内容は平易で、しかし鍵盤楽器のヴィルトゥオーゾと呼ばれたバッハの名声をより高めるような、何より自身が納得できる、充実したものでなければならない。購買層としては、公開演奏のレパートリーよりも、家庭やサロンなど私的な場で演奏しようという一般の人々を想定した。そして、ほぼ毎年1曲を順次刊行して売れ行きを確かめ、1731年にいよいよ6曲をまとめて再版した。タイトルに関しては奇をてらわず、ライプツィヒ・トマス教会の前任者クーナウにならって組曲をイタリア語風に《パルティータ》とした。また、好評を博し当時ひろく知られていたクーナウの作品集から『クラヴィーア練習曲集』の表題を拝借した。この「練習曲」というタイトルは、決して19世紀的なエチュードと同義ではない。音楽から慰めを得たいと望む人々のための親密な作品として、そしてもちろん、完成された音楽的規範としての意図がここには込められている。
この曲集は、出版されたにも拘らず、改訂に関して複雑な問題を残している。バッハは自作、とりわけ鍵盤作品に改良の手を加え続けたが、その筆は出版作品に対しても鈍ることはなかった。分冊で先行して出された稿と、1731年の集成本の稿はすでに異なっている。また、バッハが手元に置いた1731年版には更なる修正が施された。このほかにも改良のための書き込みを含む印刷譜が4部つたえられており、そのうち1冊はバッハ自身のものである可能性が高い。新バッハ全集(V/1)はこれらの修正内容をすべて吟味した上で刊行されたが、現在なお議論の余地がある。
全6曲には、それぞれ異なった冒頭楽章が与えられた。組曲の構成は《フランス組曲》以上にさまざまで、挿入舞曲の曲種や配列においては慣習を逸脱するものがある。楽章構成や音楽語法が多様をきわめる一方、曲の冒頭の関連付けや終止音型の統一、対位法的展開や綿密な動機労作によって、楽曲の統一感はいっそう高まる。「多様と統一」というバッハの美学の極致を、ここに見ることができよう。
なお、この曲集が「ドイツ組曲」と呼ばれたことがあるが、バッハに由来する名称ではないし、様式の上からもこれは適切でない。《フランス組曲》や《イギリス組曲》がそれぞれフランス的、イギリス的な典型とは言えないように、《パルティータ》にもまた、ドイツ的な典型を見出すことができないからである。
※組曲の定型に関しては《フランス組曲》の項をご覧ください。
1. 変ロ長調(7楽章): プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエットI、メヌエットII、ジーグ/ BWV825 / 1726
1726年秋にかつての主人ケーテン侯レオポルトの嫡子誕生を祝い、自作の頌歌を添えて贈った作品。クーラントはイタリア・タイプ。ジーグは通例の対位法的な展開ではなく、分散和音を華やかに用いるスティル・ブリゼ(フランス語で「分散様式」)の手法による。
楽章等 (6)
ピティナ&提携チャンネル動画(25件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (15)

(株)エー・ティ・エヌ

(株)全音楽譜出版社

(株)自由現代社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレー

(株)音楽之友社

ヘンレー

ヘンレー

ヘンレ社(ヤマハ)

ヘンレ社(ヤマハ)

ヘンレー

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

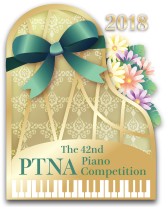 コンペ課題曲:F級
コンペ課題曲:F級  ステップレベル:発展5,展開1,展開2
ステップレベル:発展5,展開1,展開2





















