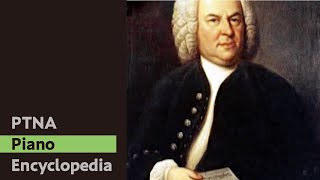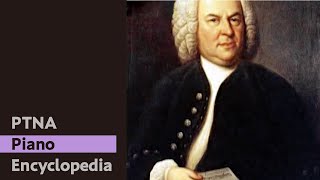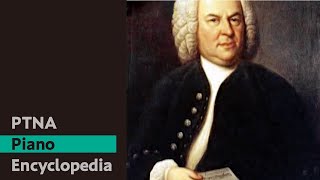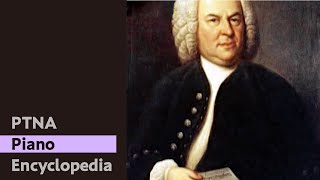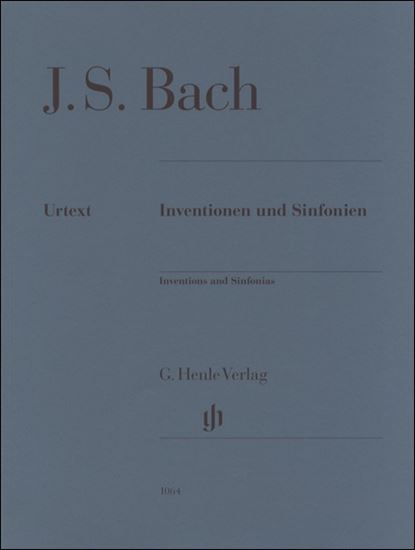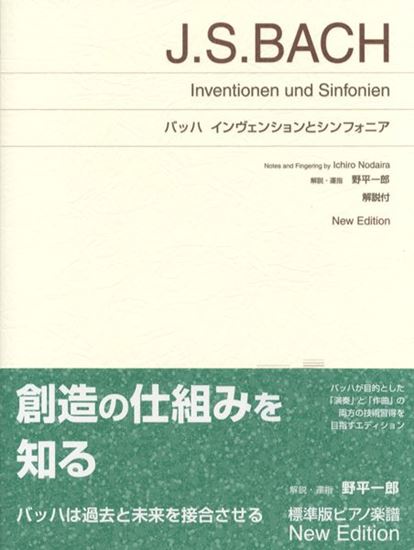作品概要
出版年:1801年
初出版社:Hoffmeister & Kühnel
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:曲集・小品集
総演奏時間:20分50秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (2)
総説 : 朝山 奈津子
(510 文字)
更新日:2007年5月1日
[開く]
総説 : 朝山 奈津子 (510 文字)
バッハは30の作品をまとめたのち、15曲の3声のセットに対して《シンフォニア》の名を与えた。これは当時すでに確立されていた、オペラの序曲に由来するジャンルとは直接の関係はない。むしろ、「とけ合って響く」というこの語のもともとの意味がこめられている。
《シンフォニア》はほとんどがフーガ書法で書かれているが、フーガに独特の累加的な始まり方をするものがまったくない。(《インヴェンション》では第1,2,3,4,8,10番が一声部で開始する。)これは、学習用の小品という意図に見合った短い主題を、やはり短い1曲の中でできるだけ多様に展開するため、また響きが硬くなるのを避けるためと考えられる。しかし部分的には三重対位法をも用い、主題の反行や転回によって多様な組み合わせが現れる。
バッハはこれらが演奏中に譜面をめくる必要のない見開きの2ページに収まるよう配慮した。15曲の調は2声インヴェンションと同じ配列で、ハ長調、ハ短調、ニ長調、ニ短調、変ホ長調、ホ長調、ホ短調、ヘ長調、ヘ短調、ト長調、ト短調、イ長調、イ短調、変ロ長調、ロ短調であり、おそらく実践で用いられる頻度に鑑みて選ばれている。
※「インヴェンション」の項もご覧下さい。
解説 : 髙松 佑介
(5766 文字)
更新日:2020年9月18日
[開く]
解説 : 髙松 佑介 (5766 文字)
総説
《3声のシンフォニア》は、《2声のインヴェンション》と同様に、バッハが長男のための教材として作曲した小品をまとめ直したものである(「インヴェンション」の項を参照)。バッハが1720年から編纂した『ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハのためのクラヴィーア小曲集』という音楽帖には、《平均律第1巻》や《インヴェンション》になる作品も含まれていた。現在「シンフォニア」として知られている曲は、元々この音楽帖において、創造的・即興的な曲を意味する「ファンタジア」と名付けられており、数年後に《インヴェンション》とともに独立した曲集としてまとめる際に改名された。なお「シンフォニア」という語は、複数声部による合奏を意味している。つまりこの新たなタイトルからは、3つの声部が協和して響き合うよう作曲・演奏する方法を習得するための曲集、というバッハの意図が読み取れるだろう。
もちろん《シンフォニア》においても、作曲と演奏の両方の技術を正しく習得するという目的は《インヴェンション》と共通しており、15曲の構成は、ハ長調から音階を上がるという《インヴェンション》と同じ調性配列を取っている(曲順は元々の『クラヴィーア小曲集』から変更されている)。ただし《シンフォニア》は、《インヴェンション》と比較して、対位法を用いたフーガ風の楽曲の数が圧倒的に多くなっており、より高度な作曲・演奏技術が求められている。
文献紹介
市田儀一郎,1971,『バッハ インヴェンションとシンフォニア』,東京:音楽之友社.
樋口隆一他,1996,『バッハ全集 第11巻 チェンバロ曲[1]』,東京:小学館.
磯山雅,小林義武,鳴海史生編著,1996,『バッハ事典』(全作品解説事典),東京:東京書籍.
ゲック,マルティン,1998,『大作曲家 バッハ』,大角欣矢訳,東京:音楽之友社.
小鍛冶邦隆,中井正子,2005,『バッハ シンフォニア――分析と演奏の手引き』,東京:ショパン.
Küster, Konrad (ed.), 1999, Bach-Handbuch, Bärenreiter & J. B. Metzler.
第1番 ハ長調、4/4拍子
この曲は基本的に、流れるような16分音符の順次進行によって構成されており、バッハが序文で記した「カンタービレの奏法」の習得に適している。この音階による主題は、様々な調や形(反行形)で現れ、組み合わされ、うねりを作る。これによって明確な段落形成が避けられており、「展開と構成が入り組んだ古風な書法」と指摘されている。
全体の構成を表すとすれば、4つの主題提示部として、第1提示部(第1小節~)と第2提示部(第8小節~)の前半部と、第3提示部(第12小節~)と第4提示部(第16小節~)の後半部に区切ることができる。
第2番 ハ短調、12/8拍子
主題は、分散和音(第1小節)と減7度跳躍を含む順次進行(第2小節)という2小節から成る。曲全体は明確な2部分で構成され、前半部では上声部と中声部がハ短調で(第1小節~)、下声部と上声部がト短調で(第9小節~)主題を提示する。
ト短調のまま始まる後半部(第19~32小節)では、主題が完全な形で一度も現れない点が特徴的である。主題の1小節目に相当する分散和音の部分のみが主として用いられ、この分散和音の動機と、第8小節などに見られた16分音符の経過的な動機が組み合わされ、摸続進行として転調を重ねる。
第3番 ニ長調、4/4拍子
舞曲風の明るい曲調をもつが、2つの対位主題をもつ高度なフーガとして、第1提示部(第1小節~)――間奏1(第8小節~)――第2提示部(第10小節~)――間奏2(第12小節~)――間奏3(第14小節~)――第3提示部(第19小節~)という構成を取る。
第1提示部では、上声部から下声部へと主題の入りが移り、主題に対して2つの対位主題が組み合わされる。第3提示部では、冒頭とは反対に下声部から上声部へと主題の入りが移り、第1提示部とは異なる組み合わせで主題に対して2つの対位主題が配置される。
第1小節 | 第3小節 | 第5小節 | 第19小節 | 第21小節 | 第23小節 |
主題 | 対位主題1 | 対位主題2 | 対位主題1 | 対位主題2 | 主題 |
主題 | 対位主題1 | 対位主題2 | 主題 | 対位主題1 | |
ゲネラルバス | 対位主題2 | 主題 | 主題 | 対位主題1 | 対位主題2 |
第2提示部は短いものの、上声部が平行調であるロ短調で主題を提示し、中声部が対位主題2、低声部が対位主題1を奏する。これは、冒頭であるがために第1提示部で欠けていた組み合わせのパターンを示している。
第4番 ニ短調、4/4拍子
フーガとして書かれており、主題の「インヴェンツィオ(着想)」の特徴としてタイによる掛留音が挙げられる。掛留音は、主題として用いられる以外にも、動機的に摸続進行として使用され、曲全体を支配している。
冒頭において上声部がニ短調で主題を提示すると、第2小節から中声部が属調で応答する。これは、上声部の主題が終わらないうちに畳み込む「ストレッタ」という技法である。後半部の第13小節以降では、上声部・中声部・下声部と全ての声部がストレッタで主題を提示してゆく。
第12~13小節の中声部、第22~23小節の上声部において組み合わされるのは、半音下行の動機である。これは「パッスス・ドゥリウスクルス」と呼ばれる、悲しみを表現する際に頻繁に用いられた音形であり、独特の曲調を与える。
第5番 変ホ長調、3/4拍子
低声部は一定の音形を繰り返す固執低音(バッソ・オスティナート)となっており、2つの主要声部(オブリガート)と通奏低音から成るトリオ・ソナタを想起させる。2つの主要声部は、一見すると一定の和声の支えに乗って自由に奏でているようだが、中声部は上声部の模倣となっており、対位法を駆使して書かれていることが分かる。
楽曲全体は、第17小節から後半部が始まるという、均整の取れた2部分で構成されている。
第6番 ホ長調、9/8拍子
順次進行による「カンタービレ」の主題をもつ。曲の前半部(第1~18小節)は2つの主題提示部で構成され、その第2提示部(第11小節~)では主題の3拍目を元に、和声的・舞踏的な新たな主題が案出される。
流れるような8分音符のリズムは、いずれかの声部において曲全体を通して鳴り響くが、この「補填リズム」の途切れる箇所が曲尾に2回現れる。まず、第34小節において――不協和音のような効果とともに――フェルマータによって流れがせき止められ、コーダの入りが区切られる。そして、第38小節の即興的・装飾的な16分音符によって減速の効果を生じさせたのち、曲を閉じる。
第7番 ホ短調、3/4拍子
レチタティーヴォ(語り)とアリア(歌唱)の中間的な性格の「アリオーソ」のような曲調をもつ。対位法的書法で書かれているものの、比較的自由な構成を取っている点で、「シンフォニア」の元の名称であった「ファンタジア」の性格が見て取れるだろう。
4つの主題提示部から成る。冒頭の第1提示部のあと、第2提示部(第14小節~)では第1提示部と逆の順番(中声部→上声部)で主題が入り、新たな対旋律が組み合わされる。第3提示部(第25小節~)冒頭では、ニ長調という調性と下声部の休止が、曲の後半部の開始を告げる。主題が切れ目なく提示されたあと、第37小節において主調で主題が回帰する(第4提示部)。ここでは、3つの声部すべてが重なって主題提示を行うかのような印象を与え、終結部を強調している。
第8番 ヘ長調、4/4拍子
《シンフォニア》15曲の中央に位置する第8番は、前後の曲と対照的な性格をもっている。生き生きとした曲調とは裏腹に、厳格な対位法で構築されているのが特徴的である。4つの主題提示部と3つの間奏から成る。
冒頭で提示される1小節の簡潔な主題は、中声部―上声部―下声部の順で提示され、主題の冒頭動機を用いた第1間奏(第4~5小節)を挟んで、例外的に属調で再度提示される(第5~7小節)。第7小節後半では、中声部が休止することで、新たな第2提示部の開始を告げる。ここでは、まず上声部と下声部がストレッタを形成しつつ摸続進行で転調し(第7小節~)、休止していた中声部がト短調で加わりつつ展開する(第11小節~)。比較的短い第2間奏(第15~17小節)、第3提示部(第17~19小節)、第3間奏(第19~20小節)に続いて、第21小節で下声部と上声部において主調で主題が回帰し、曲を締めくくる。
第9番 ヘ短調、4/4拍子
第3番と同様に、主題が2つの対位主題と組み合わされる三重対位法によって構成される。冒頭で中声部によって提示される主題は、休符と2度下行がため息のような性格を表現しているのみならず、低声部に置かれる対位主題1は、苦悩や悲しみの表現に使われた「パッスス・ドゥリウスクルス」(4度音程の半音階下行)を基礎としている。さらに主題は、最も不協和である三全音の跳躍(第2小節冒頭)を含んでおり、哀歌的な曲調を強調する。
冒頭2小節では上声部が休止し、2声となっているが、第3小節からの主題提示では、上声部が主題、中声部が対位主題1を受け持ち、低声部が新たな対位主題2を導入する。曲全体を通して主題は10回提示されるが、冒頭を除く9回は常に2つの対位主題が組み合わされている。曲はおよそシンメトリックに構成され、主題の4~5回目・7~8回目は長調で現れる。
第10番 ト長調、3/4拍子
明朗なト長調の楽曲。第1番のように、16分音符の音階で主題が構成されている。主題は第1~2小節で上声部が提示したのち、第3~4小節で中声部が応答する。第5小節では中声部が主題を繰り返したかのように聞こえるが、実際には第6小節で8分音符の分散和音が続くことで主題から逸脱し、これが間奏を特徴づける動機となる。
第11小節で中声部が奏するのは、間奏として機能していた第5小節の変形である。しかしこれに続く2小節目は8分音符の分散和音ではなく、主題の後半部となっており、結果として第11~12小節は主題提示であることが分かる(第2提示部)。このように、主題と間奏の区別が曖昧なまま展開してゆく点が、この曲の特徴だろう。
第11番 ト短調、3/4拍子
「カンタービレ」の習得に適していると言わんばかりの抒情的な楽曲。この抒情性を裏打ちするのが、比較的長い主題と掛留が創出する不協和な響きだろう。
冒頭で提示される主題は8小節と比較的長く、ト短調の音階の下行形を核としている(第1小節:ト、第2小節:ヘ、第3小節:変ホ…第6小節:変ロ、第7小節:イ)。これに組み合わされる中声部の対旋律は3拍目からタイで繋がれ、次の小節の1拍目で不協和な響きを生み出し、3拍目で解決するよう設計されている。この不協和→解決の連続が曲全体を支配し、独特の抒情性を生み出している。また主題の冒頭部は、主要な動機として、繰り返し用いられる。
第12番 イ長調、4/4拍子
明るく愛らしい曲調をもち、フーガ的な書法で書かれている。冒頭では中声部が休止し、上声部が主題、下声部が対位主題を奏でる。この対位主題は、様々に変奏されて主題と組み合わされることになる。主題は、2小節目冒頭で属音上の保続音を含んでいる。この動機が単独で繰り返し用いられることで、低声部が比較的長い保続音として機能する(例えば第9小節~)。
曲全体は2部分に分けられるが、その後半部(第15小節~)では、完全な主題が3回しか現れず、もっぱら主題に含まれる材料の展開に充てられている。
第13番 イ短調、3/8拍子
順次進行による簡潔な主題に基づくフーガ的な楽曲。冒頭では上声部の主題に対して、中声部が5度上で応答し(第5小節~)、低声部も主題を提示する(第13小節)。間奏1(第16~20小節)を挟み、第2提示部(第21小節~)では、上声部と中声部の転回(=交換)によってハ長調とイ短調を行き来する。ここでは、分散和音に基づく新たな対位主題が低声部によって提示され、楽曲の進行を決定づける。
さらに、間奏2(第36~40小節)でも32分音符を含む新たな動機が現れ、声部間の模倣を伴って摸続進行を形成する。この動機は基本的に間奏においてのみ用いられるが、第3提示部(第41~55小節)と間奏3(第56~60小節)に続き、曲の最後で主題が再度提示される際には、この間奏の動機が対旋律として組み合わされる(第60小節~)。
第14番 変ロ長調、4/4拍子
フーガ風の書法で書かれ、前半(第1提示部:第1小節~、第2提示部:第7小節~)と後半(第3提示部:第12小節~、第4提示部:第15小節~)から構成される。
この曲の特徴は、ストレッタが多用されている点にある。ストレッタとは、一つの主題が完結する前に、次の主題が重なって入る技法を指す。すでに第3小節や第6小節において、上声部に対して下声部が畳みかけるように入っているのが分かる。これらは間奏にあたるが、後半部において主題のストレッタが見られる。
後半部では、中声部が上声部に対して、まず第12小節から1拍遅れ、次に第17小節から半拍遅れのストレッタを形成する。そして最後の主題提示である第20小節からは、中声部→上声部→下声部の順で3声全てがストレッタで主題を提示し、楽曲の頂点を形成する。
第15番 ロ短調、9/16拍子
カプリッチョ風の自由な書法による楽曲。《インヴェンション》と同様だが、特に《シンフォニア》では全体として厳格なフーガ風の曲が多いため、軽い趣をもつ曲が曲集の最後を飾る点に意外性が生まれている。この意外性もユーモアの一種と捉えるなら、まさにこの曲はカプリッチョに相応しい。
大きく2部分から成る。前半部(第1小節~)と後半部(第14小節~)にコーダ(第35小節~)が連なり、各部の間に間奏が挟まれる構造となっている。コーダの前には、第32小節にフェルマータによる一時停止が置かれ、カデンツァの可能性を暗示する。そして曲の末尾には「Finis」とあり、これをもって《インヴェンション》から始まった一連の「正しい指導」を終えたことが明記されている。
楽章等 (15)
ピティナ&提携チャンネル動画(36件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (61)

カワイ出版

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社
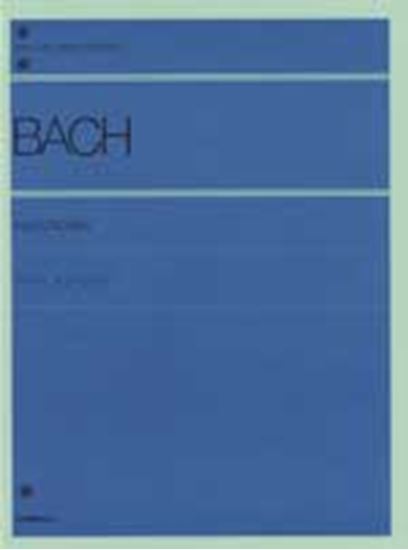
(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレー

ヘンレー

カワイ出版

(株)渓水社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)エー・ティ・エヌ

(株)全音楽譜出版社

カワイ出版

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

ヘンレー

ヘンレー

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)学研プラス

Musikverlag Doblinger

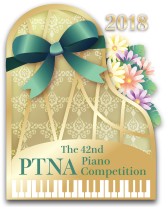 コンペ課題曲:D級
コンペ課題曲:D級  ステップレベル:応用4,応用5,応用6,応用7,発展1,発展2,発展3,発展4
ステップレベル:応用4,応用5,応用6,応用7,発展1,発展2,発展3,発展4