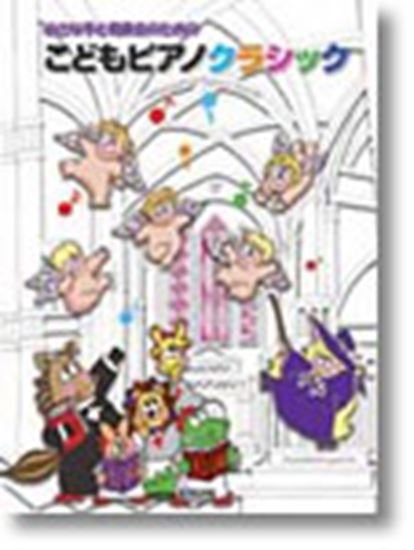チャイコフスキー : 「四季」-12の性格的描写 Op.37bis
Tchaikovsky, Pytr Il'ich : Les saisons - 12 Morceaux caracteristiques Op.37bis
作品概要
解説 (2)
執筆者 : ピティナ・ピアノ曲事典編集部
(2748 文字)
更新日:2010年1月1日
[開く]
執筆者 : ピティナ・ピアノ曲事典編集部 (2748 文字)
チャイコフスキー(1840-1893)の「四季」Op.37bis〔1876年〕は、ペテルブルクの月刊誌『ヌウェリスト(小説家)』上で“連載”された作品で、12ヶ月に対応した12の小品から成ります。季節の自然のみならず、民衆の生活をも生き生きと描写したユニークな作品で、その音楽には、祖国ロシアの自然と人々を見つめるチャイコフスキーのあたたかな眼差しがつねに息づいています。
音楽は、心あたたまる家の中の情景(「1月 炉ばたで」)で始まり、祭のにぎわい(「2月 ロシアの謝肉祭」)とともに、春が訪れ自然が目覚めると、自然の情景とそれに付随した人々の心の動きが描写されます(「3月 ひばり雲雀の歌」「4月 待雪草」「5月 白夜」「6月 舟歌」)。続いて、自然と結びついた民衆の生活が描写されます(「7月 刈入れ人の歌」「8月 収穫」「9月 狩り」)が、秋を迎え自然は枯れていきます(「10月 秋の歌」)。再び冬が訪れ(「11月 トロイカに乗って」)人々は明るい気分で1年を終えます(「12月 クリスマス週間」)。各々の小品の表題は編集者が与えたものですが、チャイコフスキーは、これらの情景を、過ぎゆく季節をいとおしむように優しい音遣いでえがき出しています。ほとんどの曲が前の曲の近親調で始められており、余韻から翌月の音楽が浮かび上がるような効果が、1年を通じた大きな流れを感得させる所以となっています。
ところで、「四季」は、特定の楽器を思わせる書法が散見されるなど、きわめて管弦楽的な発想で作曲されているので、そのオーケストレーションを意識して味わうと、鑑賞の愉しみも倍増するのではないでしょうか。実際、20世紀にソ連の指揮者・作曲家のアレクサンドル・ガウク(1893-63)が管弦楽編曲しており、スヴェトラーノフらによる録音で聴くことができますが、チャイコフスキー自身による管弦楽版が残されていればどんなに素敵だったことか、と夢想してしまいます。
「1月 炉ばたで」(イ長調)は弦楽四重奏を思わせる心あたたまる音楽で、炉ばたで暖をとりながらあれこれ思いを巡らせているようです。
「2月 ロシアの謝肉祭」(ニ長調)では打楽器も加えた大編成のトゥッティで、人々のお祭り騒ぎが描かれます。息の長いcresc.が、遠くから近づいてくる行列を生き生きと描いています。
「3月 雲雀の歌」(ト短調)は、澄み切った虚空に静かに響くひばりのさえずり。弦のしっとりとしたハーモニーに乗せて歌われるクラリネット・ファゴット・フルートの掛け合いが美しいかぎりです。
「4月 待雪草」(変ロ長調)は、スノードロップの和名で、春を告げる花と言われています。その花言葉「希望」の通り、春になり自然が目覚めた喜びが、管楽器の軽やかなリズムに乗せて、希望をこめて歌われます。
「5月 白夜」(ト長調)は、ハープの純白の響きに包まれ、優しく澄み切った音楽で、夏の白夜(現在の暦では6月)の解放感や、その美しさへの感動がえがかれています。
「6月 舟歌」(ト短調)は、チャイコフスキーのピアノ曲のなかで最も親しまれているもので、穏やかに揺れる伴奏音型が波のメタファーとなり、揺れる小舟から見上げた夏の星空への陶酔がロマンティックに歌われる名曲です。
「7月 刈入れ人の歌」(変ホ長調)は、草を刈る人々の鎌をふるうリズムにのせて、民謡風ののどかな歌が歌われます。
「8月 収穫」(ロ短調)は、弦のピツィカートのみで奏される第4交響曲スケルツォを彷彿とさせるような音楽で、農作物の取り入れで慌しい人々のようすが描写されています。穏やかな中間部は束の間の休息。
「9月 狩り」(ト長調)では、トランペットや、“狩りの楽器”ホルン(角笛)が高らかに鳴り響き、秋の狩猟の光景が力強く描かれます。3連符のリズムは狩りのメタファーです。
「10月 秋の歌」(ニ短調)は、オーボエやチェロによって、秋の愁いが愛情を込めて歌われます。中間部のデュエットは幸せな日々を回想しているかのようです。
「11月 トロイカに乗って」(ホ長調)は、一面の銀世界となった広大なロシアの雪原を、鈴の音とともに、トロイカ(馬3頭立てのそり)がさっそうと駆け抜けます。中間部のsfは、鞭のメタファーでしょうか。ラフマニノフの愛奏曲でもあった名曲です。
「12月 クリスマス週間」(変イ長調)は、クリスマスから1月6日の主顕節までの洗礼祭期を指し、静かな祝祭のムードが、新年への期待とともに描かれ、あたたかい余韻を残して1年を締めくくります。
なお、「四季」の各々の小品には詩が引用されており、聴き手が想像力をふくらませる一助となっています。
炉ばたで―1月
穏やかな 安らぎのひとすみ一隅を
うっすらくる包む 夜の闇。
暖炉のなかの かすかなほのお焔
燃えかすつきの 消えたろうそく。 ―プーシキン
ロシアの謝肉祭―2月
もうすぐ 湧きあがるよ
にぎやかな 謝肉祭の
盛大な お祭り騒ぎが。 ―ヴャゼムスキィ
ひばり雲雀の歌―3月
野原は花のさざなみ漣に揺れ
空には光の波が流れ
春の雲雀たちの歌声は
果てなき青さに満ちる ―マイコフ
まつ待ゆき雪そう草―4月
水色の 清らかな
待雪草の花
傍らに 透きとおる
消えかけの雪
過ぎ去りし悲しみによせて
最後の涙を流し
初めて夢見るのだ
また別の幸せを。 ―マイコフ
白夜―5月
なんて安らぎに満ちた夜だろう!
ありがとう、北のふるさと故郷よ!
氷におおわれた王国から
雪の降りしきる王国から
5月よ、
君はなんてすがすが清清しく、
鮮やかに飛びたつのだろう! ―フェート
舟歌―6月
岸辺に出よう。
僕らの足に波はくちづけ、
秘めやかな愁いの星が
僕らの上に光るだろう。 ―プレシシェーエフ
刈入れ人の歌―7月
肩よ うなれ、
手を振り上げろ!
南風、顔に吹きつけろ! ―コリツォフ
収穫―8月
人々は 家族みんなで
収穫にかかった。
根元まで刈り取るんだ、
背高のライ麦を!
麦束は 山のように
ぎっしりと積まれた。
荷馬車から一晩じゅう、
音楽が鳴り響く。 ―コリツォフ
狩り―9月
さぁ時間だ!と鳴るホルン角笛
狩装束の猟犬番らは
夜明けが先か 馬にまたがり
犬は一群 飛び跳ねる ―プーシキン
秋の歌―10月
秋よ、われらが粗末な庭は一面
落葉におおわれる
黄色い木の葉が風に舞い…… ―トルストイ
トロイカに乗って―11月
憂いをもって道を見るな
トロイカのあとを急いで追うな
胸の内に憂うおそ懼れを
すぐさま とわ永久にかき消せよ ―ネクラーソフ
クリスマス週間―12月
洗礼祭期のある晩に
娘たちは占った
履いている靴をすっぽりと
門の向こうへ放り上げて。 ―ジュコフスキィ
訳 岡崎卓巳
文 内藤 晃
2008/11
解説 : 山本 明尚
(6588 文字)
更新日:2019年6月25日
[開く]
解説 : 山本 明尚 (6588 文字)
《四季》は、曲集中の楽曲にみられる多彩な性格と、ロシアの生活を想起させる題名で、世界中の人々の耳と想像力を楽しませ続けており、チャイコフスキーの独奏ピアノ曲の中でも最も人気のある曲集である。
この曲集は、サンクト・ペテルブルクで音楽月刊誌『ヌヴェリスト』を編集していたニコライ・ベルナルトの依頼によって、1875年末から翌年5月までに作曲された。『ヌヴェリスト』は、サロンや自宅での演奏向けの歌曲やピアノ小品の楽譜が紙面の中心となっていた愛好家のための雑誌で、ベートーヴェン、リスト、ショパンといった西欧の作曲家の作品のみならず、グリンカ、ダルゴムィシスキー、アントン・ルビンシテインら母国人の作品も人々の楽しみに供していた。チャイコフスキーはモスクワ音楽院教授に就任して10年が経とうとしており、すでに(雑誌の表現を借りれば)「高名なロシア作曲家」となっていた。そんな彼にぜひとも人々に親しみやすい曲を作って欲しい、と、ベルナルトは申し出たわけである。チャイコフスキーはボリショイ劇場からの委嘱で《白鳥の湖》を作曲中だったが、快く依頼を受諾した。彼はすぐに「1月」と「2月」を仕上げてベルナルトに送り、最終的に「6月」から「12月」までの7曲を、遅くても1876年5月末までに一気に完成させて送った。その後、その月に相応した楽曲が、1876年の『ヌヴェリスト』の1号から12号までに掲載された。なお、今日親しまれている《四季》という題名は、1876年末に全曲がまとめて出版されたときに初めてつけられた。
よく知られているように、《四季》のそれぞれの楽曲には、各月の出来事にまつわる19世紀ロシアの人々の生活や自然に寄り添うタイトルと、エピグラフとしてロシア詩の断片が付されている。これらテキストの選定は、実はチャイコフスキーによるものではない。タイトルは、作曲依頼の時点で、すでにベルナルトによって指定されていたため、作曲者に選択の余地はすでになかった。とはいえ、チャイコフスキーは依頼への返信で、「あなたがつけてくれた題名はすべてお守りいたします」と書き送っており、そもそも題名を変更する意思はなかったようだ。また、エピグラフの詩は、ベルナルトが雑誌掲載時に、彼の元に送られてきたチャイコフスキーの完成曲に合わせて選定した。つまり、これらの詩に見られる風景描写や心理描写は、作曲時のチャイコフスキーの念頭にはなかったのである。この詩の選定にチャイコフスキーがどれくらい関与したのか、あるいはしていなかったのかは不明だが、少なくとも暗黙の了解はしていたようである。
「ベルナルトによる題名→チャイコフスキーによる作曲→ベルナルト詩の選定」という過程を考えてみると、必ずしも付されている詩がチャイコフスキーの楽曲の内容をそのまま表しているとは言えなくなる。とはいえ、これらの詩が存在意義を失くしてしまったり、解釈の邪魔になってしまったり、ということはない。それらは、同時代人がチャイコフスキーの楽曲をどのように解釈したのかを知る手がかりとして読むこともできるし、チャイコフスキー自身によっても含め、今日まで広く受け容れられてきた一般的な《四季》観、個々の楽曲の解釈をそれらに見て取ることも可能なのではないだろうか。
〈1月、小さな暖炉の傍らで〉
そして 和やかに安らぐ片隅を
夜の薄闇が包み込む
暖炉の中 残り火は消えかかり
やがて ろうそくは燃え尽きる
エピグラフは現代ロシア語の父と呼ばれる大詩人アレクサンドル・プーシキンの詩「夢想家」(1815)より、夜の安らぎの中、消えかかる火を描写した場面。
複合三部形式。主要部はイ長調。一拍目のバスを欠く主題からは、素朴さと一抹の寂しさが感じられる。強弱と旋律の音域によって、ゆるやかに息長いアーチを描いている一方で、旋律が2音や3音のスラーによって構成されていることにも注意しなければならない。中間部ではホ短調に転調する。つかの間の眠りに落ちるような下行音型と、そこから目覚めるかのような、あるいは夢の中の景色のような即興的走句による。走句の部分では、主音こそ出てこないものの遠隔な変イ長調へと転調するような身振りもみられ、幻想的な雰囲気を引き立てている。主要部分の再現につづき、終結部が最弱音・高音で静かに曲を締めくくる。
全体として弱音を中心として構成されており、曲中の最高潮でも、音量はmfを超えることがない。p、pp、さらにはpppの繊細な表現が求められる。
〈2月、マースレニッツァ〉
もうすぐにぎやかなマースレニツァ
盛大な宴が活気づく
エピグラフはヴャーゼムスキーの「異国の謝肉祭」(1853)から取られている。
題名のマースレニツァとは、大斎期直前の一週間に行われ、春を迎えるロシアの民間儀礼のことで、古くからロシア人の生活に密接に関わっていた。家ではブリヌィ(クレープに似た伝統料理)が焼かれ、伝統料理が並び、若者たちは盛大に騒ぐ。野外も遊ぶ人々で賑やかになり、縁日、見世物小屋、のぞきからくり、さらには殴り合いの喧嘩すらも、この時期の街の華となる。
楽曲は、再現部を短縮した複合三部形式。主要部は、祝祭の快活さや楽しさが全体に満ち満ちている。冒頭の賑々しい和音は、見世物小屋のアコーディオンを模していると思われる。ヘ長調の中間部では、やや落ち着くものの、半音の使い方や、中とみられるパッセージはユーモアに満ちている。
〈3月、ヒバリの歌〉
野には花々がさざめき
空には光がきらめく
春ヒバリたちの歌声は
果てしない空に満ちあふる
エピグラフはアポローン・マーイコフの詩集『野外で』(1857)より、「野に花々はそよぎ……」からの引用。初春の晴れやかな自然描写である。
ト短調による主要主題の旋律は、右手と左手で応答し合いながら進む。中間部の旋律は変ロ長調のほの明るさを備えているが、すぐにト短調に戻っていく。どちらの旋律も、装飾音やスタッカートを備えており、チチチとさえずる雲雀のイメージに合致している。
短い楽曲は全体的に憂いに満ちており、春の訪れを喜ばしく詠むエピグラフのイメージと曲調が食い違っている。これについては、例えば音楽学者の一柳は「……哀愁と希望とがないまぜになった早春の自然を、どんよりとくすんだ低い空を舞うヒバリの姿に擬えている……」(ロシア・フォークロアの会 なろうど編著『ロシアの歳時記』118頁)と、ロシアの季節感に即して解釈している。3月は冬から春へと移り変わる微妙な時期で、雪が降る日は徐々に少なくなり、冬の間に分厚く張った川の氷も溶け出し、一柳の言葉を借りれば「遠慮がちに自然が目覚め」ていく。
〈4月、雪割草〉
空色の 清らかな
雪割草の花
傍らには透き通った
なごりの淡雪
過ぎ行く哀しみに寄せる
最後の涙と
やがて訪れる幸せに寄せる
最初の夢と……
エピグラフはアポローン・マーイコフの詩集『野外で』(1857)より、「春」の全編が引かれている。
6/8拍子で書かれてこそいるが、1小節を二つに分割すると、興味深いことに、優雅なワルツであるかのように響く。長調で書かれているが、1月と同じく、しばしば強拍の伴奏を欠く書法は、ためらいや不完全さを連想させる。倚音が多用されるサロン的な旋律は、当初最上声部で提示されるが、しばしば内声へと移り変わる。やや長い中間部はニ短調で書かれており、哀愁を帯びながらも軽やかな上声が特徴的である。以上のように、主要部分にも中間部分にも、性格が統一されないアンビバレントさがある。また、強弱指示も全体として弱音に偏っており、力強さや決意のようなものは、あまり感じられない。この楽曲からは、「3月」と同じく、まだ完全に冬が明けきっていない、早春のほのかな明るさが感じられる。
〈5月、白夜〉
素晴らしき夜! すべてを包み込む安らぎ!
この北の故郷に感謝しよう!
氷の王国から 吹雪と雪の王国から
かくも新鮮で清澄な故郷の五月がやって来る
エピグラフはアファナーシイ・フェートの「まだ五月の夜」(1857)より。
夏のペテルブルクは白夜の季節である。緯度の高い帝国の北都では、太陽はなかなか沈まず、深夜でも明るい時間が続く。
とはいえ、たとえペテルブルクであろうと、五月には白夜にはならない。ベルナルトがなぜこのような題名を五月の曲に指定したかは謎であるが、エピグラフ(これも白夜とも関係ない)が「なんと素晴らしき夜!」という詠嘆から始まることを考えると、「白夜」という言葉からは、沈まぬ太陽ではなく、冬から開放された明るさの方を連想すべきではないかとも思われる(前掲書120頁の一柳の意見も参照されたい)。
三部形式の主要部分の冒頭、弱音で演奏されるト長調のアルペジオは、通常楽曲の半ばで見られるヘミオラが、拍節が不規則にしている点で意欲的な構造を持つ(3拍子系の曲の2小節を、通常の3+3ではなく2+2+2の拍節で区切ることをヘミオラという)。また、全体の小節構造もシンメトリーになっておらず、主要部分の強弱はpとppでとどまっており、やや脆く不安定な印象を受ける。中間部は2/4拍子、アレグロ・ジオコーソと標示されるテンポの早い部分で、分散和音の伴奏に乗せて、下行音型による素朴な旋律が高揚していく。
〈6月、舟歌〉
岸に立てば 寄せる波
僕たちの足に接吻するだろう
星は神秘的な哀愁とともに
僕たちの上に光を放つだろう
エピグラフはプレッシェーエフ(プレシチェーエフとも)の「歌」(1845)より。一人称複数の「僕ら」は、詩のその後の展開を読むに、若い恋人なのだろう。
ト短調の主和音による寄せては返す波のような緩やかな伴奏を前奏として、チャイコフスキーが得意とする、音階上の順次進行をベースにした旋律が奏でられる(他の例は、例えば交響曲第4番の最終楽章や、《くるみ割り人形》のパ・ドゥ・ドゥ、弦楽セレナーデの第2、3楽章などにみられる)。一般に舟歌は6/8や9/8といった複合拍子で作曲されることが多いが、興味深いことに、チャイコフスキーは4/4拍子を選択している。
短い中間部では同主長調へと転じ、次第に速度を増していき、「giocoso(快活さをもって)」という指示のもと、3/4拍子でクライマックスに達するが、その快活さは長続きせず、高音部でのきらびやかなアルペジオで中断され、主要部の再現へと回帰する。出版者ベルナルトは、このアルペジオの響きから、星の瞬きを見出し、エピグラフを選定したのかもしれない。
〈7月、草刈り人の歌〉
覚悟はいいか 俺の肩よ!
振り上がれ 俺の腕よ!
顔に吹きつけろ
真昼の風よ!
エピグラフは農村の風景や農民の労働を題材として詩にしたことで知られるアレクセイ・コリツォーフの「草刈り人」(1836)より。
チャイコフスキーはここで、夏の農村の夏の民衆生活を客観的に切り取っている。ここでは、収穫の時期を控えた季節、家畜の餌の干し草づくりのために、集団で野の草を刈り取る儀式的作業である。
頭拍を強調した素朴な主題旋律からは、仕事歌を歌いながら力を込めて鎌を振って進む人々の風景が浮かんでは来ないだろうか。コントラストをなす短調の中間部はまるで、暑い7月の野外での苦しい作業と、そこに吹き付ける一陣の風のようである――と解釈しては穿ち過ぎだろうか。
〈8月、穫り入れ(スケルツォ)〉
人々は家ごとに
収穫の準備を
育ったライ麦を
借り入れる支度を始めた
ライ麦の束は
山積にされ
あちこちの荷馬車は一晩中
キーキーと音楽を奏でる
エピグラフはコリツォーフの「収穫」(1835)より。
題名のカッコ内の「スケルツォ」という副題は、出版者ベルナルトのものではなく、チャイコフスキーが追加したもの。
7月で描かれていたのは収穫前の野良仕事だが、こちらはその後の収穫の模様である。
忙しない収穫の模様を、多彩な音響で描き出している。ロ短調という調とヴィヴァーチェの速度標示、細かいアーティキュレーションが焦燥感を煽る。ピアノで演奏される各声部は、それぞれにオーケストラの楽器が割り当てられているように響く。ニ長調の中間部は束の間の休憩の模様か、夜のしじまでの憩いか。
〈9月、狩り〉
時間だ 時間だ! 角笛が響く
狩支度の男たちは
すでに夜明けには馬に跨がり
繋がれた猟犬たちが飛び跳ねる
エピグラフはプーシキンの『ヌーリン伯爵』(1825)より。
ト長調の主題のフレーズに見られる鋭い付点音符や三連符、左手の伴奏の二声による和音は明らかに、西洋クラシック音楽に伝統的に見られる(そしてエピグラフ詩にもみられる)狩りの角笛の模倣である。そこからチャイコフスキーは発想を広げ、リズム動機はそのままに、しかしピアニスティックに幅広い音域を用いて主題を展開していく。ホ短調の中間部では、雰囲気こそ一転し、主要部分と対称をなしているが、その一方で三連符や付点は維持されている点が面白い。
〈10月、秋の歌〉
秋 憐れな庭は落ち葉におおわれている
黄ばんだ木の葉は 風に舞い落ちている……
エピグラフはアレクセイ・トルストイの「秋 憐れな庭は落ち葉におおわれている」(1858)より。
ニ短調の主題はチャイコフスキーのメロディーメーカーとしての面目躍如といえるだろう。ゆるやかな和声にのせ、哀愁に溢れた旋律が優しげに歌われる。中間部はヘ長調だが、主要主題のほの暗さはそのまま保っている。弱音を中心としてデュナーミクが構成され、それらをどのように繊細に表現するかが求められている。その極致とも言えるのが楽曲の終結部だろう。ppで響く、蠕動するような上声の動きの中、morendoの末にとうとうpppp(!)にまで達し、消えゆく。
〈11月、トロイカで〉
遥かな道を眺めて憂うな
トロイカの後を追うな
胸の内の哀しい予感は
かき消してしまいなさい
エピグラフはネクラーソフの「トロイカ」(1846)より。
トロイカとは、三頭立ての馬車や馬橇のこと。
ホ長調の主要部分では、素朴で牧歌的な旋律が奏でられ、伴奏音型によって朗々たる雰囲気へと変わり、ト長調の中間部へと移る。装飾を伴う両手の跳躍音型は、馬橇が蹄を鳴らして走る音だろうか。高音部のスタッカートを交えて再現される主題は、まるで御者が橇を走らせながら歌っているように響く。
〈12月、スヴャートキ(ワルツ)〉
ある年の洗礼祭の夕べ
娘たちが恋占いをしていた
片方の靴を脱ぎ捨てて
門の外に放り出して
エピグラフはジュコーフスキイの「スヴェトラーナ」(1813)より。
8月の「スケルツォ」と同じく、カッコ内の副題はチャイコフスキー自身によって追加されたもの。
「スヴャートキ」とは聞き慣れない言葉だが、これはロシアの暦で、クリスマスから洗礼祭前夜までの十二日間(12月25日〜1月6日)の祝祭期間を指す。引用されている詩では、この期間に特別に行われる農村の娘たちの恋占いが描かれている。
ただし、チャイコフスキーが楽曲で描いているのは、農村に住む彼女たちの素朴な輪舞ではなく、都会の様式化され、洗練された円舞のように聴こえる。
変ホ長調の主部は、ゆるやかに上行し、ゼクエンツによって下行していく主旋律が特徴的で、軽やかな朗らかさがある。トリオはホ長調に転調し、両外声のゆるやかな下行音型のかけあいによる落ち着いた部分に、fに始まる活発な部分が挟まれている。短いコーダは一旦fまで盛り上がりながらも、節度を持ってpで優雅に終結する。
(詩の翻訳は、ロシア・フォークロアの会 なろうど編著『ロシアの歳時記』に掲載された一柳富美子氏の訳を、ご厚意のもと使用させていただいた。ここに深く感謝を申し上げる。『ロシアの歳時記』は、チャイコフスキーが暮らし、愛したロシアの風土や人々の生活、フォークロア文化をまとめた書籍で、しばしばロシアならではの素材が組み込まれ、理解にある程度の背景知識を必要とすることもあるロシア音楽を解釈する際に、助けを与えてくれる一冊である。)
楽章等 (12)
ピティナ&提携チャンネル動画(33件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (46)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)春秋社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社
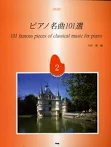
KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)タイムリーミュージック

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレ社(ヤマハ)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)学研プラス

(株)学研プラス

Musikverlag Doblinger

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

 ステップレベル:発展1,発展2,発展3,発展4,発展5,展開1,展開2,展開3
ステップレベル:発展1,発展2,発展3,発展4,発展5,展開1,展開2,展開3