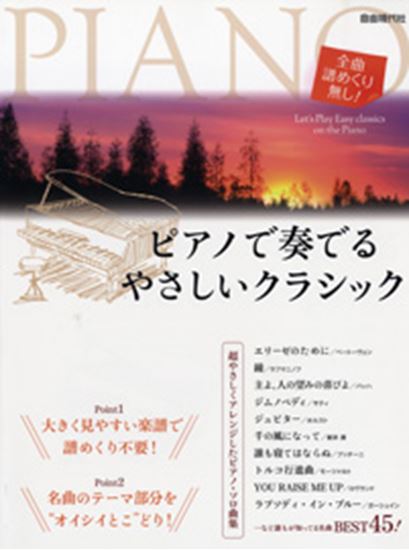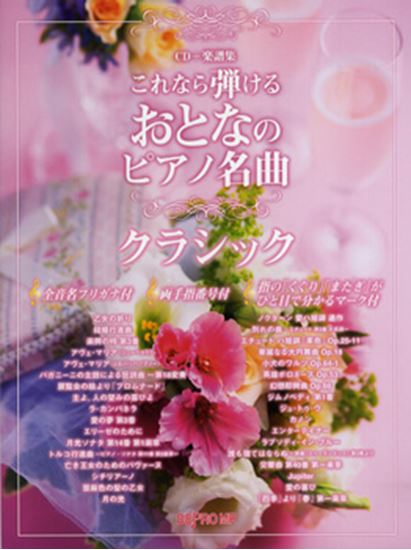作品概要
解説 (4)
解説動画 : 南 杏佳
(198 文字)
更新日:2025年7月3日
[開く]
解説動画 : 南 杏佳 (198 文字)
2024年度特級グランプリ、南杏佳さんによる解説動画を公開しました。2024年8月18日に行われた特級セミファイナルでのムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」の演奏映像を南さん自身が振り返りながら、演奏中に感じたこと、特に注意を払った点、そしてこの楽曲に対する深い思いを語ります。
※動画閲覧はこちらから https://youtu.be/r4ZzKuRFbWo?si=4OhWHXF2vv4S8naR
成立背景 : 木暮 有紀子
(896 文字)
更新日:2014年1月20日
[開く]
成立背景 : 木暮 有紀子 (896 文字)
ムーソルグスキイは、言わずと知れた「力強い一団」(日本では、「フランス六人組」になぞらえて「五人組」と呼ばれることが多い。)の一人である。
《展覧会の絵》は、彼の友人ヴィークトル・ガールトマン(日本ではハルトマンという読み方が浸透している)の遺作展から影響を受けて作曲されている。日本の音楽研究家一柳富美子によっても指摘されているが、原題は《展覧会からの絵》という意を持つ。ガールトマンの絵をそのまま音楽において描出した訳ではなく、あくまでそこからインスピレーションを受けて作られた楽曲である。
作曲期間は、1974年6月2〜22日である。しかし、楽譜の初版は1984年と作曲時期より10年遅れている。この楽譜は、リムスキー=コルサーコフによって編集され、サンクトペテルブルクにおいて出版された。
献呈は、ウラディーミル・スターソフにされている。スターソフは、「力強い一団」という名を「五人組」に与えた張本人であり、特にムーソルグスキイとの結びつきが強かった。オペラ《ホヴァーンシナ》の制作を援助し、歌曲集《子供部屋》や《死の歌と踊り》のタイトルを名付けたのも彼の功績である。
また、スターソフは第6曲の〈ザムエル=ゴールデンベルクとシュムイレ〉について、ムーソルグスキイの「反ユダヤ主義」的思想を見出だしている。ちなみに、「ザムエル」は1小節目から始まる威張り散らすような旋律に象徴されるような金持ちのユダヤ人だ。一方、「シュムイレ」は9小節目の右手部分に登場する三連譜に象徴されるようなみすぼらしく貧しいユダヤ人である。
このように、全くの別人格を持っているように描かれた「ザムエル」と「シュムイレ」だが、実は同じ名前の読み方を変えただけのものである。前者はヨーロッパ名であり、後者はイディッシュ名(つまりはユダヤ名)なのだ。つまり、このタイトルにはヨーロッパの各地に根付いて富を得たユダヤ人も、元を正せば実に貧しい出自の者なのだという意味が、暗に含まれていると解釈できるだろう。「反ユダヤ主義」的意見は《展覧会の絵》作曲当時のムーソルグスキイの書簡に散見していることも、この解釈を後押ししている。
解説 : 伊藤 翠
(3585 文字)
更新日:2013年11月15日
[開く]
解説 : 伊藤 翠 (3585 文字)
ムソルグスキー : 組曲「展覧会の絵」
1873年、急進的な建築家であり画家でもあったヴィクトル・ハルトマン(ロシア語発音では「ガルトマン」とも。1842〜1873)が若くして亡くなった。4年前に出会って以来、親友として付き合いのあったムソルグスキーは、この出来事に大きなショックを受けた。その翌年の一月、ペテルブルクの美術学校にて遺作展が開かれ、そこでハルトマンが残した数多くのスケッチや設計図、デザインを目にしたことが、この組曲の作曲動機となったと言われている。
後の研究によると、第2、4、7曲に相当するものが遺作展のカタログに見当たらず、さらに第1、3、8曲についても原画不明ということで、ムソルグスキーが組曲中の曲全てをハルトマンの遺作の忠実な印象として作曲したとは言いにくい。むしろ、ハルトマンの作品をはじめ、自分が見てきたあらゆる絵画作品にインスピレーションを受けて作られた曲だといえよう。
今日では、ラヴェルの管弦楽編曲版で演奏されることが多く、その風俗的描写や表現力の豊かさ、国民主義的な内容に焦点があてられがちである。しかし、19世紀ロシアの生んだ 独創的なピアノ音楽のひととして、注目すべき作品であることに間違いはない。
《プロムナード Promenade》
5/4拍子と6/4拍子が交替しながら、冒頭から素朴で力強い主題があらわれる。これはロシアの旋法によるもので、「ハルトマンの遺作展に足を運んだムソルグスキーの歩く様子」を表したものである。つまり、この《プロムナード》は形を変えながらこの後も曲間で挿入されるが、それはムソルグスキーが次の絵へと移動している様子を表現している。管弦楽版では、各々の《プロムナード》が異なる楽器で奏されていくという点も、興味深い。
第1曲《小人 Gnomus》
《プロムナード》の後に休みなく続けて奏される。グノムスとはロシアのおとぎ話に登場する小人の妖怪で、奇妙な格好で動き回りながら、地の底の宝を守っているという。この悪賢くいたずらっぽい小人は当時のロシア人たちに親しまれていた。ムソルグスキーの「グノムス」からはややグロテスクな印象を受ける。奇妙な足取りで歩き回る姿、地底のどこか陰鬱な雰囲気を描き出すような動機ではじまり、やがて重々しい音色となって彼らの痛ましい感情を描写しているかのようである。
第2曲《古城 Il vecchio castello》
冒頭のものより幾分やさしげな《プロムナード》を挟んでから、場面は中世の幻想へと変わる。題名の通り「古城」の前で、吟遊詩人がリュートを奏でながら歌っているのだろう。初めから終わりまで、左手が奏す哀愁ただよう音型はリュートの音色そのものである。管弦楽版ではこの左手部分はファゴット、右手の甘美な旋律はアルトサックスで演奏されている。
第3曲《テュイルリー, 遊んだあとの子供のけんか Tuilleries - Dispute d'enfants apres jeux》
テュイルリーとは、パリの中心にある公園の名である。今日でも、遊びまわる子ども達やその親たちの憩いの場として、親しまれている。この作品は重厚な《プロムナード》の後に、そんなテュイルリー公園で遊び疲れた子ども達の公論を描写している。冒頭のめまぐるしい動機は、子ども達ががやがやと言い合うさまを表しており、中間部でほんの少しだけ、表情の落ち着いた動機(14小節)があらわれるものの、またすぐに騒然とした場面に切り替わってしまう。子どもらしい描写が楽しい作品である。
第4曲《ブイドロ Bydlo》
ポーランド語で「牛の集団」を意味するブイドロであるが、終始重々しく、暗い曲調で統一されたこの曲をきけば、これが単なる「牛の集団」の描写でないことに気付くかもしれない。この言葉には「家畜のように虐げられた(ポーランドの)人々」という意味がある。この曲は「虐げられた人々」への同情と、人々の暗く激しい感情の表出なのかもしれない。しかし、この作品がそのようなものとして発表されることは、当時のロシアではタブーであった。実際、ムソルグスキー自筆の楽譜には、最初につけた題名をナイフで削り取り、書き直した痕があった。その意味をスタソフ(1824-1906 高名な芸術評論家)に問われた時、彼は「ここは『牛車』ということにしておこう」と答えたという。
第5曲《卵の殻をつけたひなどりのバレエ Ballet de poussins dans leurs coques》
第4曲の悲しげな余韻を受け継いだプロムナード、その終結部にはこの作品の動機である「ひなどり」の鳴き声が予感のように奏され、この作品に続く。今日、この組曲中で最も親しまれ演奏される機会の多い作品である。この作品の原画は、バレエ《トリルビ》の衣装デザイン画であるとはっきりしており、音楽もきわめて描写的なものになっている。冒頭での主題はひなどりの鳴き声と小刻みな動きが表現されており、後半のトリオ部分では、バレエ音楽のようなユーモラスな響きとなっている。
第6曲《ザムエル・ゴルデンベルクとシュムイレ Samuel Goldenberg und Schmuyle》
「ふたりのユダヤ人~太った男と痩せた男」という副題がついているとおり、裕福で傲慢な男ゴルデンベルクと、貧しく卑屈な男シュムイレの会話を描写した作品である。ユダヤ人の典型的な名前をもった二人と、この曲のみドイツ語表記となっているところが興味深い。
まず、威張りぶったような冒頭の主題は、ゴルデンベルクであろう。その後9小節目から、細かい音符でぺちゃくちゃと喋り出すのが、シュムイレである。やがて低音に威圧的なゴルデンベルクの声(15小節目〜)が鳴り響き、シュムイレを圧倒してしまう様子が描かれている。
第7曲《リモージュの市場 Limoges, le marche》
冒頭と同じテンポの《プロムナード》(編曲版では省略されることもある)に続いて、アタッカで始められる。この曲に相当する絵はないが、市場に集まった女性達の会話や、行き交う人々の様子を描写した曲であると解釈出来る。休みなしに動く十六分音符のリズムが特徴的であるが、管弦楽版ではそのめまぐるしく楽器を入れ替えてその動機を演奏させることで、せわしなさを表現している。
第8曲《カタコンブ-ローマ時代の墓 Catacombae - Sepulcrum romanum》
カタコンベとは、ローマ時代に弾圧されたキリスト教徒の地下の墓場のことである。ハルトマン自身が灯をともしながらその中を調べている様を描いた絵によったと考えられているが、その絵が実存したかどうかは不明である。しかし、第4曲にも通じるような重々しい和音の連続には、どこか不気味で時に怒りさえ描写されているように感じる。強弱の変化が幅広く、30小節の短い曲でありながら、印象深い余韻を残している。
これに続くのが、「死せる言葉を以て死者と共に」と題された部分である。《プロムナード》の変形であるが、《カタコンベ》の余韻から逃れがたい気持ちが表現されているのだろう。重苦しい 気分の和声から、右手のトレモロを響かせつつ次第に明るい和声へと展開していくところが印象的である。
第9曲《鶏の足の上に建っている小屋 La cabane sur des pattes de poule》
一見奇妙な題名だが、原画は時計のデザイン画で、グロテスクな鶏の二本足が台をふまえていて、その上にバーバ・ヤガーの小屋が建っているというものだ。バーバー・ガヤーもまたロシアのおとぎ話に登場する魔女のことで、ムソルグスキーはこの魔女についても空想を膨らませているようだ。
冒頭、音楽はたたきつけるような鋭い動機ではじまる。やがてその力は持続的に大きくなり、和音の連打による激しい主題となる。怪しげな時計が時を刻んでいるようにも思われるが、魔女という不気味な存在も、この曲全体のテーマとして独特な世界観を作り上げている。
第10曲《キエフの大きな門 La grande porte de Kiev》
第9曲から休みなく続けられるこの曲は、キエフに建造されることとなった大門の設計図にインスピレーションを得たと言われている。《プロムナード》にも通じるどっしりとしたこの組曲の主題にはじまり、大きく盛り上がってゆく。すると突然、31小節目からは静かなコラール風の音楽が流れる。これは、親しかった友人ハルトマンと、その才能への賛美の歌なのかもしれない。冒頭の主題とこのコラール風の主題は壮大な変奏を繰り返しながら折り重なっていき、最後にもう一度、冒頭の主題がこれまでにないエネルギーを放出させるかのようなコーダ部分となって、組曲の大きな幕を閉じる。
解説 : 齊藤 紀子
(3826 文字)
更新日:2007年11月1日
[開く]
解説 : 齊藤 紀子 (3826 文字)
副題に<ヴィクトル・ガルトマンの思い出に>とあるこの組曲は、39歳で夭折した友人の画家、ガルトマン(1834-1873)を追悼して開かれた遺作展にインスピレーションを得ており、ムソルグスキーが35歳の時に作曲された。1874年6月の3週間で完成されている。これは、他の作品にかかった時間と比較すると、非常に速いペースである。出版は、ムソルグスキーの死後5年を経てから、1886年にサンクト・ペテルブルクでリムスキー=コルサコフの校訂によりなされた。この際、ムソルグスキー独特の手法の多くが誤りとして訂正されており、オリジナル版の出版は1931年のムソルグスキー全集を待たねばならなかった。尚、この組曲は、ラヴェルやリムスキー=コルサコフによるオーケストラ編曲を通して広く世に知られている。
<プロムナード>。アレグロ・ジュスト・ネル・モード・ルッシコ・センツァ・アッレグレッツァ・マ・ポコ・ソステヌートで、4分の5拍子と4分の6拍子が混在する。ガルトマンの遺作展に足を運んだムソルグスキーの歩く様子を表している。ロシアの旋法を色濃く前面に打ち出したこの断章は、形を変えたりしながら、所々に挿入される。まず、メロディーのみが1本のラインとして提示され、その後、オクターヴや和音に重ねた厚いテクスチュアで仕立てられる。
<こびと>。プロムナードからアタッカで続けられる。曲がった脚で少々不恰好に歩くこびとを描いたスケッチにインスピレーションを得た曲と考えられている。原語の「グノームス」とは、こびとの姿をした「土の精」。左右の手による低音域のユニゾンで開始する。曲には高い緊張感がみなぎっている。
<プロムナード>とは明記されていないものの、組曲を開始したプロムナードが異なる音から始められる。モデラート・コモド・アッサイ・エ・コン・デリカテッツァと指示されている。「p」の強弱記号が多く付された静かな一節。
<古城>。プロムナードの要素を持つ挿入的な部分からアタッカで続けられる。アンダンティーノ・モルト・カンタービレ・エ・コン・ドルチェの標示。8分の6拍子で書かれている。曲は低く鳴り響く空虚5度で開始。その伴奏に乗り、哀愁を帯びたメロディーが歌われる。
<プロムナード>とは明記されていないものの、ここにもその要素を持つ部分が挿入される。やはり、異なる音から始められる。また、組曲最初の『プロムナード』が24小節であるのに対し、<古城>の前に挿入された2回めの『プロムナード』は12小節、そして今回は8小節と、その長さは短くなっている。ここでは、モデラート・ノン・タント・ペザメンテと指示されている。
<テュイルリー(遊びのあとの子どものけんか)>。プロムナードの要素を持つ挿入的な部分からアタッカで続けられる。アレグレット・ノン・トロッポ・カプリッチョーソのこの曲は、大勢の子どもと女教師のいるパリのテュイルリー公園の並木道を描いた絵にインスピレーションを得たと考えられている。これまでの音楽に比べ、軽やかなリズムが特徴的である。また、所々に見られる音階的な音の動きが、この曲の持つ推進力に寄与している。
<ブィドウォ(ブイドロ、ビドロ)>。ポーランドの牛にひかれた荷馬車の音楽である。「ブィドウォ」とは、ポーランド語で、「家畜」、「家畜のような人間」の意味があり、巨大で重々しいこの車をひく「苦役」を示唆していると考えられる。センプレ・モデラート・ペザンテのこの曲は、リムスキー=コルサコフの校訂版ではリムスキー=コルサコフの手が加えられたために「pp」で開始していた。しかし、オリジナル版では「ff」で開始し、重苦しさを一層直截的に表している。主要なラインは低音域で野太く奏でられるか、ないしは高音域でオクターヴや和音に重ねられて響く。そして、何れの場合にも、低音域に密集した和音が8分音符で刻み続けられる。
<プロムナード>とは明記されていないものの、ここにもその要素を持つ部分が挿入される。ここで特筆すべきことは、そのメロディーが<ブィドウォ>を引きずり抑圧されているかのように、途中から始められることである。トランクィッロの指示。4分の6拍子から7拍子までが混在するこのプロムナードは、最後の小節で4分の3拍子となる。
<卵の殻をつけたひなどりのバレエ>。前曲からアタッカで続けられる。バレエ作品《トリルビー》の舞台上演のためにガルトマンがイラストレーションを作成した、鎧のように卵の殻を身に纏ったカナリアのひよこたちが踊る様子にインスピレーションを得た曲と考えられている。スケルツィーノ・ヴィーヴォ・レッジェロのこの曲では、始終弱音ペダルが踏まれる。そして、高音域のみで音楽が運ばれ、一瞬の風のように通り過ぎていく。
<ザムエル・ゴルデンベルクとシュムイレ>。<卵の殻をつけたひなどりのバレエ>からアタッカで続けられる。この組曲が書かれた当時のサンクト・ペテルブルクでは、ザムエル・ゴルデンベルクは裕福なユダヤ人の典型的な名前であり、一方、シュムイレは貧しいユダヤ人の典型的な名前であったとされている。アンダンテ・グラーヴェ・エネルギコのこの曲では、付点と連音符が巧みに組み合わされたリズムが特徴的である。また、単音の連打やオクターヴに重ねられた連打も独特の雰囲気を醸し出すことに寄与している。
<プロムナード>。この組曲の冒頭以来、所々にプロムナードに基づく部分が挿入されてきたが、このように明記されたものはなかった。ここで特筆すべきことは、単音で開始せず、左右のユニゾンに重ねられていることである。また、冒頭に付された指示は、アレグロ・ジュスト・ネル・モード・ルッシコ・ポコ・ソステヌートと、この組曲を開始した<プロムナード>とほぼ等しい。また、開始音も冒頭の<プロムナード>に即しており、「f」で開始する。
<リモージュ 市場(大ニュース)>。<プロムナード>からアッタッカで続けられる。フランス南西部にある古い都市リモージュの市場で、フランス人の女性たちが激しく言い争う様子を描いた絵にインスピレーションを得た作品と考えられている。アレグレット・ヴィーヴォ・センプレ・スケルツァンドのこの曲では、「f」を基調としており、頻繁に付されたスフォルツァンドが、市場の活気ある喧騒を伝えている。
<カタコンブ(ローマの墓)>。カタコンブとは、地下に掘られた共同墓地のことである。ローマと明記されているものの、この曲のインスピレーションとなった絵は、パリのカタコンブをランタンの光をあててじっと見つめるガルトマン自身が描かれたものと考えられている。ラルゴの指示がなされたこの曲は、4分の3拍子で書かれ、付点2分音符を主体としている。また、しばしばフェルマータを伴う。ディナーミクの変化は幅広く、僅か30小節の曲でありながら、印象深い余韻を残す。
<死者の言葉をもって死者とともに>。<カタコンブ(ローマの墓)>からアタッカで続けられる。自筆譜では、この曲を表す語句、「死者の言葉をもって死者とともに」は非常に小さく添え書きがなされているにすぎない。そして、ラテン語で綴られている。アンダンテ・ノン・トロッポ・コン・ラメントの指示がなされているが、拍子は明記されていない。とは言え、各小節には、規則的に6つの4分音符が配置されている。僅か21小節のこの曲も先立つ<カタコンブ(ローマの墓)>と同様に、「pp」のトレモロの深い響きによって印象深い余韻を残す。
<にわとりの足の上に建つ小屋(バーバ・ヤガー)>。この曲のインスピレーションを得たと考えられているガルトマンのスケッチでは、にわとりの足の上に妖婆の小屋の形をした時計が描かれている。ムソルグスキーは、そこに臼の上に乗って進む「バーバ・ヤガー」を付け加えた。「バーバ・ヤガー」とは、森の中に住み、人をつかまえ手はその肉を食する痩せた妖婆のことで、鉄製の臼に乗り、杵で漕いで箒でその軌跡を消しながら進むとされている。尚、この曲の原題は、「吹けば飛ぶようなあばら屋」という意味も持つ。アレグロ・コン・ブリオ・フェローツェの4分の2拍子で書かれたこの曲では、左右のユニゾンを主体としたホモ・テクスチュアを築く部分が多い。そして、これに該当しない部分では、非常に幅広い音域を扱っている。後半からはアレグロ・モルトとなり、推進力が一層増す。
<英雄の門(首都キエフにある)>。<にわとりの足の上に建つ小屋(バーバ・ヤガー)>からアタッカで続けられる。この曲のインスピレーションを得たと考えられているガルトマンの下絵では、スラヴ風のかぶと型の丸屋根をした、古ロシア的石造り様式のキエフ市のための門が描かれている。しかし、この設計図は、結局、具現されることはなかった、尚、スケッチや水彩画のみならず、舞台装置や衣装のデザインも手かげたガルトマンの本職は、建築家であった。アレグロ・アッラ・ブレーヴェ・マエストーソ・コン・グランデッツァの指示がある。組曲中最も規模が大きく、音楽内容も雄大なものと言えよう。全体的に、重厚な和音によって響きが生み出され、オクターブも多用される。後半からは、メーノ・モッソ・センプレ・マエストーソとなり、終結部分では、グラーヴェ・センプレ・アッラルガンドとなり、壮大な響きをもって組曲全体を締めくくる。
楽章等 (11)
編曲・関連曲(3) <表示する>
ピティナ&提携チャンネル動画(45件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (69)

(株)音楽之友社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社(ポケットスコア)

(株)音楽之友社

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)リットーミュージック

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)リットーミュージック

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)リットーミュージック

(株)オンキョウパブリッシュ〇

(株)オンキョウパブリッシュ〇

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)共同音楽出版社

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)オンキョウパブリッシュ〇

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント
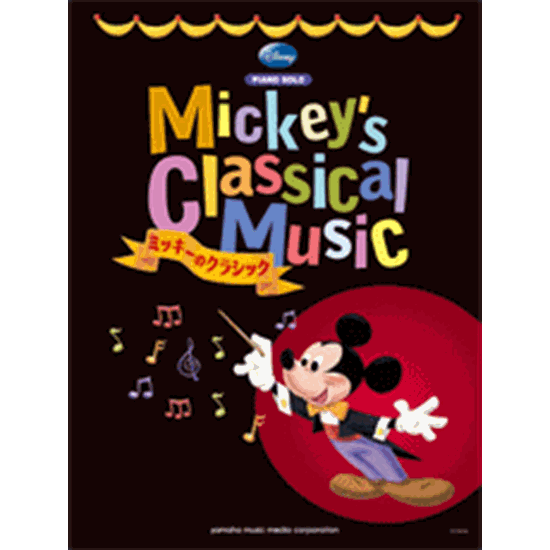
(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

デプロMP

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド

(株)共同音楽出版社

ミュージックランド
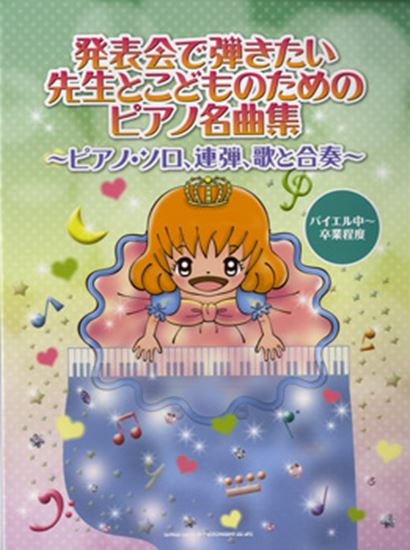
(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックメディア

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(有)ティーダ

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
![小学生のための ピアノ名曲集C [ブルグミュラー程度] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/1765.jpg)
(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

ミュージックランド

(有)中央アート出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

Musikverlag Doblinger

Peters


![組曲「展覧会の絵」 [全曲] - 演奏動画のサムネイル](http://i.ytimg.com/vi/2flnCaoWon8/mqdefault.jpg)
![組曲「展覧会の絵」[全曲] - 演奏動画のサムネイル](http://i.ytimg.com/vi/rPIuItJa1Ko/mqdefault.jpg)