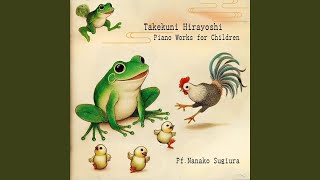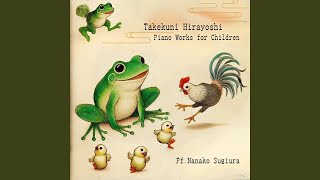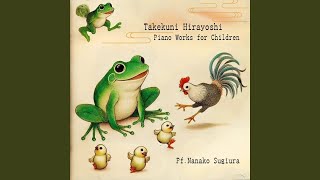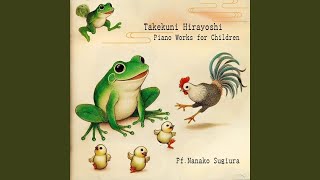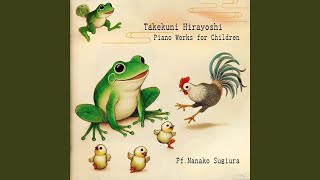作品概要
出版年:1979年
初出版社:カワイ出版
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:子供のための作品
総演奏時間:34分10秒
著作権:保護期間中
解説 (2)
演奏のヒント : 清水 篤
(1201 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 清水 篤 (1201 文字)
13. 子守歌 (Lullaby)
■平吉 毅州について 平吉毅州(1936-1998)は、現代作品の他にも『気球にのってどこまでも』や、合唱(組)曲『海の不思議』『わが里程標』『若い翼は』など合唱の重要なレパートリーを残した作曲家です。子供のためのピアノ作品も多く、この「子守歌」も『虹のリズム』という25曲からなる曲集に収められています。全曲の中でも真ん中にあたる13曲目に置かれており、長い1冊の曲の中の休憩、お昼寝、のような役割を持たされています。
子守歌、と題されている通り、全曲を通してmfより音量が上がることもなく、穏やかで暖かい音楽的空気をもっています。音量差を出すためには美しいp、ppが必要ですし、ペダルを含む響きの中で、深く柔らかい音色が求められています。また、倚音(強拍に濁った音が弱拍で解決する和音外音)が大変印象的です。一瞬の濁りに何を感じるか、その音からの流れの作り方、その辺りに表現上の課題があるといえます。曲は大まかに二部構成(1〜23小節目、23〜39小節目)で成り立っています。
■1〜7小節目 最初の主要なテーマが3小節、少し息の短いフレーズが1、2、3の積み重ね、の2要素によって出来ています。細切れにならないよう、左の低音の順次進行(ラ→ソ→ファ→ミ→レ→ド→シ)に上手く乗せましょう。4〜5小節目のような内声の倚音はBassとの7度のぶつかりをよく聴いて味わうとよいでしょう。
■8〜14小節目 最初の7小節とほぼ同じですが、後半は平行調(fis moll)に繋がっています。また、IIの和音が調号通りだと減三和音になるはずが、dにシャープがついて短三和音とされています。より甘い感じの悲しさを演出している部分です。
■15〜22小節目 転調が始まります。Bass・和音度は3度ずつ上行していきますが、途中で一旦音量がpに落とされているのに注意。内声の2度でぶつかる倚音はここでも美しく濁らせたいところです。
■23〜32小節目 Es durに落ち着いて新しいテーマが始まるように思いますが、最初の形を膨らませた音型です。ただ、同音反復の後の跳躍が3度から4度に拡げられています。より強い(深い)感情が込められているものと推理します。和声的には前半4小節がI→VI→Iと元に戻る(停滞する)進行なのに対し、次の4小節は主調のA durを目指して次々に動いていきます。音量面でもdecresc.とcresc.で対称的に作られています。31小節目には最初のメロディーが最後に現れます。rit.がつけられているのは名残を惜しんでいるのでしょうか。
■33小節目〜 主調でb.23の進行を繰り返すと思いきや、とても印象的で旋法風の進行を見せて幻想的に曲を終えます。最後の付加6の和音はfis音が強すぎると主和音の役目が弱くなってしまうので注意しましょう。
演奏のヒント : 大井 和郎
(1734 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (1734 文字)
13. 子守歌
まずこの楽譜は大変緻密に書かれており、作曲家から演奏者への細かな要求がよく解ります。筆者は、この作曲家の意図を探るため、直接本人とのコミュニケーションを模索していたのですが、既にこの作曲家はお亡くなりになっておりました。あとは、作曲家の書法から判断していかなければなりません。
ペダルマーキングを見てみると、ペダルを1小節間踏みっぱなしにする事で生ずる多少のメロディーラインの濁りよりも、音の伸びを優先するマーキングですね。従って、多少の濁りは気にせず、印象派のような、少し音がぼやけた、水彩画のような描写を再現して良いのではないかと思います。
筆者が最も興味のある書き方が左手下方部に書かれるダイナミックマーキングです。通常は大譜表の真ん中に書かれるのですが、このように、左手にのみ書かれると言うことはそれなりの意味があります。よく見ると、大譜表の真ん中に現れる、通常のダイナミックマーキングは17小節目以降に初めて現れます。
単純に解釈をしますと、左手に書かれてあるダイナミックマーキングは、左手も右手同様メロディーラインとして扱うべきなのではないかと筆者は考えていますが、まずは1小節目から16小節目までを見てみましょう。1-16小節間、ダイナミックマーキングは全て左手に付けられています。そして左手をよく見ると、各小節の1拍目が「付点2分音符」で書かれていますね。例えば1-5小節間、左手1拍目の付点2分音符と、2拍目に来るテノールの音符は別声部で書かれいます。
ペダルマーキングをご覧下さい、ほぼ、殆どの小節は1小節間、よほどの濁りが生じない限りは踏みっぱなしになっていますね。ということは、1拍目の音は嫌でもペダルで伸びてしまいますので、わざわざ付点2分音符で書かずに、4分音符で書いても同じように伸びます。では作曲家は何故ここに付点2分音符を用い、左手を2声にかいているのでしょうか?
筆者の想像になりますが、作曲家はバスの声部を1つのメロディーラインとして扱って欲しかったと推測できます。要するに、テノールの音よりも、バスの音を強調して欲しい、あるいはバスだけは絶対にかすれないでハッキリ出して欲しいという意図であると思います。そしてこれら左手のバス音以外に、作曲家が大きなダイナミックを付けている場所が、6-7小節間、と、13-14小節間です。よく見るとこれら2つの小節間には同じ素材があることにお気づきでしょうか?8分音符2つに2分音符、または8分音符2つに4分音符2つ。この素材こそ、作曲家が強調したかったであろう素材かと思います。そしてこの素材が現れるとき、メロディーライン(最高声部)は決まって音価の大きい音符が書かれていますね。本来であれば、これら音価の大きい音符は(特にタイで次の小節にも繋がれている音符は)、左手の音量を落とし、右手の伸びる音を聴かすように弾くのですが、この曲の場合、長い音価のメロディーが登場したとき、左手のダイナミックは逆に大きくなっていて、この左手の素材を強調するように書かれてあると思います。
17小節目以降、ダイナミックマーキングは大譜表の真ん中に現れます。以降、再び左手にダイナミックマーキングが現れるまでは、通常のバランスをとり、左手を小さく、右手を大きく弾きます。 そしてもう1つ注目したいのがテヌートマーキングです。これは曲前半のみに登場して、後半には出てきません。テヌートマーキングはその音を少しだけたっぷりと伸ばすマーキングですね。そしてそれは、前半左手の2拍目の音に書かれていますね(1,2,3,8,9,10小節目)。
しかしながら、この2拍目の音だけを長めに伸ばしますと、3拍子のリズムを崩すことになります。察するにこのマーキングは、音をよく伸ばして、音をよく響かせて欲しいという作曲家の意図があったと推測できます。バスも大切ですが、テノールの声部もバス同様に十分伸ばして欲しいという意味であると思います。
曲は転調を繰り返し、突然ショッキングな調に変わって主題が演奏されます。学習者の皆様は、それぞれの調によって弾かれる主題を全て同じように弾くのではなく、調によってカラーを変えてみましょう。
楽章等 (25)
ピティナ&提携チャンネル動画(76件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(25件)
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (19)

カワイ出版

カワイ出版

(株)音楽之友社

(株)共同音楽出版社

(株)共同音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)サーベル社

(株)学研プラス

(株)学研プラス

(株)学研プラス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)学研プラス

 ステップレベル:基礎3,基礎4
ステップレベル:基礎3,基礎4