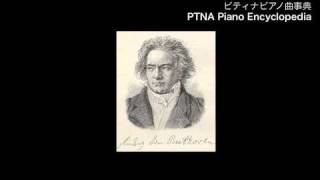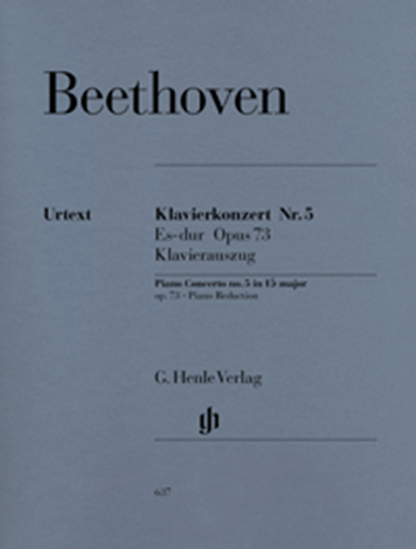ベートーヴェン : ピアノ協奏曲 第5番「皇帝」 変ホ長調 Op.73
Beethoven, Ludwig van : Konzert für Klavier und Orchester Nr.5 Es-Dur Op.73
作品概要
出版年:1811年
献呈先:Rudolf Johannes Joseph Rainer, Erzherzog von Österreich
楽器編成:ピアノ協奏曲(管弦楽とピアノ)
ジャンル:協奏曲
総演奏時間:37分00秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (2)
執筆者 : ピティナ・ピアノ曲事典編集部
(797 文字)
更新日:2010年1月1日
[開く]
執筆者 : ピティナ・ピアノ曲事典編集部 (797 文字)
1800年頃からの十数年間はベートーヴェンの創作の絶頂にある中期にあたり、交響曲第3番「英雄」、第5番「運命」や第6番「田園」、弦楽四重奏曲「ラズモフスキー」の3曲や「大公」トリオ、ピアノ・ソナタ「ワルトシュタイン」、「熱情」、「告別」、ピアノ協奏曲第4番、ヴァイオリン協奏曲などの名曲、大曲が次々に書かれている。
このピアノ協奏曲第5番もこうしたベートーヴェンの創作意欲の大きさが反映した、巨大で力強い作品に仕上がっている。この曲の別名「皇帝」は、ベートーヴェンによる命名ではなく、出版人のJ.B.クラマーによものである。
初演は1811年11月28日、ライプツィヒ・ゲヴァントハウスにて、独奏はJ.F.シュナイダーによって行われた。尚その翌年、ベートーヴェンの弟子でピアノの教則本でも有名なチェルニーの独奏によって、ウィーンでも演奏された。
□第1楽章 アレグロ 変ホ長調 4分の4拍子
曲は協奏風のソナタ形式で書かれている。第4番のピアノ協奏曲では独奏ピアノで曲が始まるという新しい試みを見せているが、この第5番では、オーケストラの力強い主和音のあとすぐにピアノのカデンツァ風のパッセージを華々しく登場させている。これは主題ではなく単なる序奏にすぎないが、その後は風格のある第1主題と、初め短調で奏でられる第2主題とがエネルギッシュに発展して行く。
□第2楽章 アダージョ・ウン・ポーコ・モッソ ロ長調 4分の4拍子
自由な変奏曲形式で書かれた、優しく美しく落ち着いた緩徐楽章。前後の華麗な楽章の中で、素朴で味わい深い音楽がしっとりと奏でられて行く。最後は変ホ長調に移り、第3楽章の主題がゆっくり示され、切れ目なく第3楽章に突入する。
□第3楽章 アレグロ 変ホ長調 8分の6拍子
先の楽章で現れた主題がフォルテで爆発的に開始され、ロンド・ソナタ形式を形成していく。豪快で力感に溢れた華やかなフィナーレ。
解説 : 鐵 百合奈
(1862 文字)
更新日:2019年10月6日
[開く]
解説 : 鐵 百合奈 (1862 文字)
「皇帝」という通称はヨハン・バプティスト・クラーマーが広めたもので、ベートーヴェン自身による命名ではない。作曲されたのは1808~09年、皇帝ナポレオンが次々とヨーロッパを侵略していく時期で、ベートーヴェンが暮らすウィーンもフランス軍に攻め込まれ、1809年5月に占領された。疎開せずにウィーンに留まったベートーヴェンは、フランス軍の砲撃に苛まれながら筆を進めた。皇帝への賛美とは対極の精神で作曲されたと言えよう。
元来、協奏曲というジャンルは、演奏者数を多く要するために実演の機会が独奏曲などに比べると少なく、それゆえに、一聴しただけで聴衆の心をつかむ外連味を必要とし、多くの聴衆に受け入れられるために、すでに定着している人気の様式で作曲されるものだった。ベートーヴェンはその慣行を破り、内面の精神性に満ち、時代を先取りした書法を盛り込んで、この第5番を作曲した。
初演(非公開)は1811年1月13日、ウィーンのロプコヴィツ侯爵宮殿で、指揮はシュルツ、独奏はルドルフ大公(ベートーヴェンの高弟かつ援助者)が務めた。公開演奏の場では、1811年11月28日にライプツィヒのゲヴァントハウスでフリードリヒ・シュナイダー独奏、1812年2月12日にはウィーンのケルントナートーア劇場にてカール・チェルニー独奏で演奏された。 時代がベートーヴェンに付いていけなかったのか、これらの実演は失敗。後世、フランツ・リストが多く演奏会でとりあげ人気曲となった[1]。
第1楽章
Allegro 変ホ長調 4/4拍子
協奏ソナタ形式を踏襲しながらも、斬新な構想を多く持つ大規模な楽章。独奏ピアノのカデンツァ風の導入がオーケストラ総奏との対決のように編まれる。第11小節~オーケストラが威厳のある第1主題を始め、第2主題を同主調(第41小節~)と主調(第49小節~)で奏でる。第1主題の素材による推移(第57小節~)の後、対位法的なコデッタ(第78小節~)に導かれ、独奏楽器が現れる。ピアノソロによる第1主題は、装飾的な変奏が施された上に優しい曲想に変化しており、ピアノソロが高音域で奏でる第2主題は、浄化された天上の響きを思わせる。推移部に現れるピアノソロの下行音型(第217小節~)も、清流の水音のような清らかさを持つ。冒頭のような勇壮さは展開部のクライマックスで姿を見せ(第304小節~)、ここにベートーヴェンの反骨精神、反戦精神を見ることができるかもしれない。再現部の手前のピアノソロで、祈りが天に昇って消えていく。
第2楽章
Adagio un poco mosso ロ長調 4/4拍子
三部形式。主部はすべてを包み込む寛容さと、敬虔な響きを湛えている。弱音器付きの弦楽器から始まり(弦楽器はこの第2楽章を通して弱音器付きで奏される)、音量が増した第9小節目で管楽器が加わる。第16小節目からの中間部で初めてピアノが登場し、なめらかで美しい下行音型を聴かせる。
再現部(第45小節~)では、弦楽器はピッツィカートにまわり、ピアノが主導権を持って音楽を牽引していく。そして、極めて印象的な箇所…第3楽章への推移の部分となる。第79小節、主音のHをファゴットが意味深長に延ばし、第80小節でホルンが半音下のBに受け継ぐ。そのBによって変ホ長調へ誘い込まれたピアノが、第3楽章の主題を夢見心地で幻想的に奏する。
第3楽章
Rondo Allegro - Piu allgero 変ホ長調 6/8拍子
ロンド・ソナタ形式。夢から目覚め、快活な主要主題をピアノが奏し、引き継いでオーケストラも主要主題を歓喜に満ちて奏する。その勢いを保ったまま、走句的なピアノソロが飛び込み(第42小節)、上がっていく。頂上の高音域に達した後はdim.でするりと緊張を解き、dolceの優しく柔和な楽想が現れ(第49小節)、第72小節で新たな楽想が再びdolceを付されて登場し、第78小節でさらにもう一度dolceが書き込まれる。この楽想(第72小節~)は属調の変ロ長調であることから、主題としての性格は際立ってはいないものの、従来は副主題として解釈されてきた。筆者はこの付近にdolceが三度も執拗に記されていること、第49小節からの楽想のキャラクターが際立っていることから、第49~93小節あたり全体を、副主題群として捉えている。その後、主要主題が様々な表情付けを施されて奏され、最後は晴れやかに駆け抜ける。
[1] 本解説内の譜例は、Breitkopf社の旧全集を使用。
編曲・関連曲(1) <表示する>
ピティナ&提携チャンネル動画(18件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (11)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)リットーミュージック

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)リットーミュージック

日本楽譜出版社
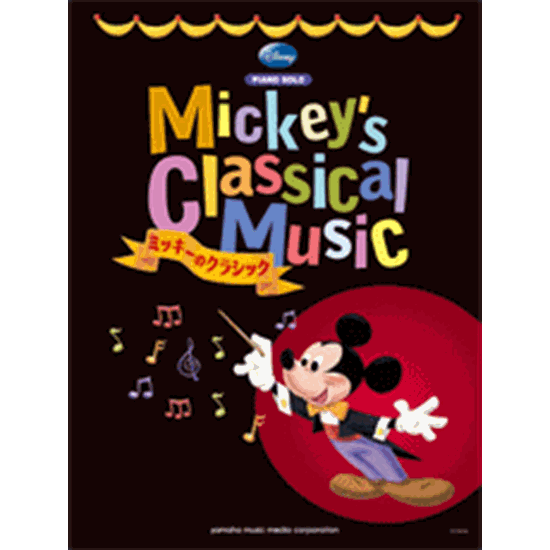
(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス