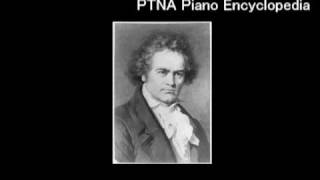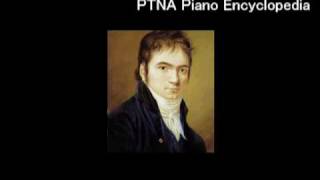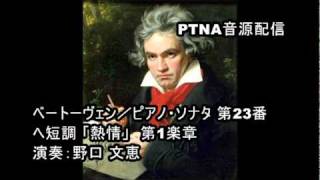ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.23 "Appassionata" f-moll Op.57
作品概要
出版年:1807年
初出版社:Bureau d'art et d'industrie
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:22分00秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (1)
楽曲分析 : 岡田 安樹浩
(2640 文字)
更新日:2009年2月1日
[開く]
楽曲分析 : 岡田 安樹浩 (2640 文字)
【総説&楽曲分析】
1805年に完成したと推定されるこのソナタは、彼が1803年に入手したエラール製のピアノで作曲されたと考えられている。幅広いダイナミック・レンジと最低・高音域の重点的な使用が、この新しい楽器の特性を活かした結果と見られるからだ。そしてその劇的表現には、当時ベートーヴェンが取り組んでいたオペラ《フィデリオ(レオノーレ)》の表現の応用を見て取ることもできる。そのように見ると、この楽曲におけるヘ短調と調の選択とその陰鬱な響きは、《フィデリオ》第2幕冒頭の牢獄の場面の響きへと通じていることに気づかされる。
なお、自筆譜はパリ音楽院所蔵であるが、ファクシミリが出版されており、これを見ると第3楽章に数多くの修正が認められる。一気に書き上げた第1・2楽章に対して試行錯誤を重ねたことがうかがえる。
(第1楽章)8分の12拍子 ヘ短調 ソナタ形式
[提示部]
主要主題は、特徴的なリズム・パターンによる主和音の分散和音と属和音上のトリル音型という2つの動機からなり、これがすぐにナポリII度の調(変ト長調)で繰り返される。第5交響曲Op.67の第1楽章で中心的に用いられる、いわゆる「運命の動機」も低音域に姿を見せる。
和音の上行連打を挟みつつ主題が確保された後、変ホ音の同音連打による推移部が変イ長調の副次主題を準備する。
主要主題における分散和音のリズム・パターンと類似した変イ長調の副次主題の提示に続き、低音域での分散和音のなかに主要主題後半のトリル音型を取り込んだ変イ短調のもう1つの副次主題があらわれる。切れ間なくコデッタへなだれ込み、高音域の細かい分散和音と低音域へ下降する長い音価の分散和音によって、5オクターヴ隔たった変イ音に収束する。
[展開部]
提示部の反復はなく、提示部最後の変イ音を異名同音の嬰ト音に読み替えてホ長調に転調する。まず主要主題がホ長調であらわれ、後半の動機(トリル音型)が発展的に繰り返される。次に前半の動機(リズム的分散和音)がホ短調、ハ短調で展開され、変イ音の同音連打へたどりつく。これは紛れも無く提示部の推移部分であり、続いて変ニ長調で第1の副次主題があらわれる。
この副次主題が変ロ短調、変ト長調へと発展し、変ト音を嬰へ音に読み替えてロ短調を一瞬経由して主調であるヘ短調の二重ドミナント、そしてドミナントへと進行する。
導音上の減7和音(属9和音の根音省略形ともいう)の幅広い音域の分散和音、高音域と低音域で繰り返される変ニ音→ハ音の「運命の動機」が再現部を導く。
[再現部]
「運命の動機」から引き続く低音域でのハ音、すなわちヘ短調の属音の連打の上に主要主題が再現される。同主長調であるヘ長調で確保されたのち、推移を経てヘ長調、ヘ短調で再現される。
[終結部]
結句は5オクターヴ隔たったへ音へは収束せず、そのまま細かな分散和音と低音域に主要主題前半の動機が発展的に繰り返される。変ニ長調へ転じて第1副次主題があらわれ、ヘ短調へ戻るも、すぐにナポリII度の和音からはじまる分散和音のデンツァ風の楽句が挿入される。「運命の動機」が繰り返されるなか、Piu Allegroとなって第1副次主題がヘ短調であらわれ、最弱音(PPP)へ沈み込んで終結する。
提示部の主題がすべて主要主題から導き出されている動機展開技法のほか、展開部の提示部との構造上の共通性、終結部が第2の展開部にまで拡大されている点など、多くの面で円熟したベートーヴェンのソナタ形式楽章の姿がみてとれる。
(第2楽章)4分の2拍子 変ニ長調 変奏曲形式
8小節からなる2つの楽句が、それぞれ反復記号によって繰り返される計32小節の主題と、4つの変奏からなる楽章。
第1変奏はシンコペーション・リズムが基本となり、第2変奏では16分音符、第3変奏では32分音符を基調としており、徐々に音価が細かくなってゆく。第4変奏では冒頭とよく似た形で主題が回帰する。減7和音が弱奏と強奏で2度鳴り響くと、切れ間無く第3楽章へ突入する。
(第3楽章)4分の2拍子 ヘ短調 ソナタ形式
[提示部]
前楽章に引き続き、減7和音の付点リズムによる連打によって導入される。主要主題は拍頭の音が第1楽章の主要主題と共通しているほか、ナポリII度和音上で繰り返されることも、第1楽章の主要主題と通低しており、この楽曲全体が第1楽章の主要主題から導き出されているといってもよいかもしれない。
副次主題は属調のハ短調であらわれるが、これもナポリII度の和音によって特徴づけられている。
[展開部+再現部]
このソナタでは展開部以降が反復記号によって繰り返される構造になっている。
展開部はもっぱら変ロ短調で書かれており、主要主題が発展的に扱われた後、リズム的特長をもつ新たな動機があらわれる。ヘ短調で再び主要主題をあつかい、属保続音(ハ音)が主調を完全に準備する。
再現部では主要主題、副次主題ともヘ短調で再現され、反復記号によって展開部の冒頭へ戻る。
[終結部]
第1楽章のような「第2の展開部」としての終結部というよりは、むしろ器楽的に発展し、華々しく楽曲を締めくくる要素が強い。Prestoとなり、和音連打による楽句、分散和音の和声型にささえられた主要主題によって全曲を閉じる。
第1楽章の発展的なソナタ形式に対し、第3楽章では提示部の2つの主題の調性関係と展開部+再現部の調性関係が、それぞれ主調→属調/下属調→主調というシンメトリカルに構成され、古典的な2部分ソナタの構成が強く意識されているように思われる。
そもそもソナタ形式の展開部とは、提示部の主調→属調という関係に対して、再現での主調回帰へむけた移行プロセスの部分であり、経過的な部分であった。それゆえ、提示部の主題とは関係のない経過的な楽句がはさみこまれることもしばしばある。しかし、このソナタの第3楽章展開部にみられるような、主題的特徴をもつような動機の挿入は、こうした伝統的なソナタ形式の枠組みのなかでは語れない。
第1楽章終結部を「第2の展開部」として拡大する構成法や、第3楽章展開部における新動機の登場は、すべて《交響曲第3番》「英雄」Op.55の構成に通じている。
この作品でベートーヴェンは、エラール製ピアノによって得られた幅広いダイナミック・レンジと音域、そして交響曲的な展開技法と構成法を融合させることで、ピアノ・ソナタのジャンルにおいて新たな一歩を踏み出したといえよう。
楽章等 (3)
ピティナ&提携チャンネル動画(45件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(11件)
楽譜
楽譜一覧 (14)

(株)全音楽譜出版社

(株)春秋社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)音楽之友社

ヘンレ社(ヤマハ)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

Barenreiter

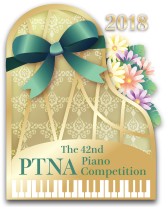 コンペ課題曲:F級
コンペ課題曲:F級  ステップレベル:展開2,展開3
ステップレベル:展開2,展開3