ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.21 "Waldstein" C-Dur Op.53
作品概要
出版年:1805年
初出版社:Bureau d'art et d'industrie
献呈先:Graf Ferdinand Ernst von Waldstein
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:24分30秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (2)
執筆者 : 岡田 安樹浩
(584 文字)
更新日:2009年2月1日
[開く]
執筆者 : 岡田 安樹浩 (584 文字)
1803年にパリのエラールから新しいピアノを贈られたベートーヴェンは、この楽器と格闘することになった。
それまでウィーン式アクションのピアノに親しんでいた彼にとって、目新しいイギリス式アクションのピアノは扱いづらい代物だったのだろう。傑作ぞろいのこの時期にあって、ピアノ・ソナタの創作は――――2つの傑作の存在ゆえにあまり意識されないが――――停滞している。近年では、その傑作のひとつ《ヴァルトシュタイン》が本当にエラール製ピアノだけで作曲されたのか、疑問視する声もある。
この《ヴァルトシュタイン・ソナタ》は当初、およそ8分の演奏時間を要するアンダンテ楽章を第2楽章にもっていた。しかしベートーヴェンは、これをより短い「導入 Introduzione」に置き換えた。その理由は、演奏時間の長大さに対する不満にこたえた結果だと伝えられているが、この作曲家が他者の助言に従って曲を改変したと信じることは難しい。「導入」というピアノ・ソナタでは見慣れない章題、そして当時のベートーヴェンがオペラの作曲に取り組んでいたことから、ここには劇音楽との接点が見出される。実際この楽曲全体を支配する曇りの無いハ長調は、オペラ《フィデリオ(レオノーレ)》のフィナーレの響きを思わせる。なお当初の第2楽章は、現在《アンダンテ・ファヴォリ》WoO.57という独立した作品として出版されている。
解説 : 鐵 百合奈
(1869 文字)
更新日:2019年10月6日
[開く]
解説 : 鐵 百合奈 (1869 文字)
1700年頃にクリストフォリの発明によって生まれたピアノは、18世紀後半から19世紀の半ばまで進化し続けた。ベートーヴェン(1770~1827年)は、まさにピアノの過渡期に生き、さまざまなメーカーの楽器製作者たちと親交を結んで助言し、楽器の進化に直接影響を与えた。また、当時の最新のピアノに触れることによって、楽器から作曲のインスピレーションを得ることもあった。
1803年、エラール社からベートーヴェンにピアノが贈呈される。これはイギリス式の近代的なフォルテピアノで、F1~c4の5オクターヴ半の音域を持ち、4本の足ペダルを備えていた(それまでベートーヴェンが使用していたウィーン式のフォルテピアノのダンパーは、当時はまだ膝レバーで操作するタイプだった)。このピアノに触発され、《ワルトシュタイン》や《熱情》などの中期のピアノ・ソナタの傑作が生み出された。
《ワルトシュタイン》は当初、演奏時間10分ほどのアンダンテが第2楽章として据えられていたが、「導入Introduzione」と題された短いアダージョに差し替えられた(元のアンダンテは後年、独立した楽曲として《アンダンテ・ファヴォリ ヘ長調 》WoO 57と題され出版された)。作曲は1803~04年に行われ、1805年に出版された[1]。
第1楽章
Allegro con brio 4/4拍子 ハ長調
ソナタ形式。力強い生命力を秘めた和音の同音連打で始まる。長2度下の変ロ長調へ意外な転調をし、溝に落ちたような感覚を覚えるが、すぐにハ短調に戻る。第14小節からは空気が澄むようなトレモロとなり、長2度上がってニ短調に。推移部はさらに長2度上のホ短調に進み、コラール風の第2主題はホ長調で提示。これは第1主題の長3度上の調(遠隔調)だが、それを感じさせない巧みな推移によって、天上的な幸福感に安心して包まれる。第1主題を展開し、第112小節目からはハーモニーの色合いを重ねて音型のフォルムをぼかし、谷底を漂う霧のように低音がうごめく中から、右手の煌めく音列がほとばしり、再現部に到達。第2主題の再現は主調から短3度下のイ長調で、構築的な三度音程による調設計が徹底される。コーダは意外な転調と衝撃的なsfを繰り返し、第2主題と第1主題の三度目の登場で締めくくられる。
第2楽章
Introduzione. Adagio molto 6/8拍子 ヘ長調
深淵から立ちのぼってくるような夢幻的な導入。第10小節目から低弦の響きを想像させる豊かな歌が流れ出し、管楽器を思わせる音階の断片が対位法的に重なる。第17小節目から導入が再現されるが、かつて休符だったところに合いの手が入り、思わず心の声があふれ出てしまったかのよう。次楽章のロンドにむかって途切れることなく連綿と続き、最後のGで光が射す。このGを属音として、切れ目なく終楽章へ続く。
第3楽章
Rondo. Allegretto moderato - Prestissimo 2/4拍子 ハ長調
ロンド・ソナタ形式。泉から流れる音のような分散和音を右手が奏でる上で、始源から湧き出た地の歌を交差した左手が歌う。主題部分はペダルを長く踏み続けるよう指示され、ペダルを使用しない他の部分と好対照である。主題のモティーフによる推移もペダルによる幽玄な響きで奏され、第113小節で主題が幸福感を増して回帰。ハ短調に暗転して第2エピソードとなり、三連符の波が交錯し、主題が勇壮に展開される。アルペジオの幽玄な響きがppで織りなされた後、突然視界が開け、主題が感動的なffで現れる。喜びにあふれた第3エピソード(第345小節目~)で高潮すると、神秘的な静けさがたまゆらのごとく束の間訪れ、コーダに。オクターヴでのグリッサンド(現代のピアノは鍵盤が重いため、両手に分けてスケールとして奏することも※)や、旋律を弾きながらのトリルなど超絶技巧を駆使し、華麗に終わる。
※筆者の指遣いの例
[1] 本解説内での譜例は、以下のものを使用:Beethoven, Ludwig van. Klaviersonaten. Edited by Norbert Gertsch & Murray Perahia. Fingering by Perahia. München: Henle, 2012.
楽章等 (3)
ピティナ&提携チャンネル動画(19件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(7件)
楽譜
楽譜一覧 (12)

(株)全音楽譜出版社

(株)春秋社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)音楽之友社

ヘンレ社(ヤマハ)

Barenreiter

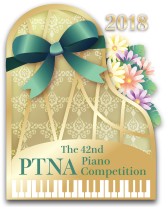 コンペ課題曲:F級
コンペ課題曲:F級  ステップレベル:展開1,展開2,展開3
ステップレベル:展開1,展開2,展開3



















