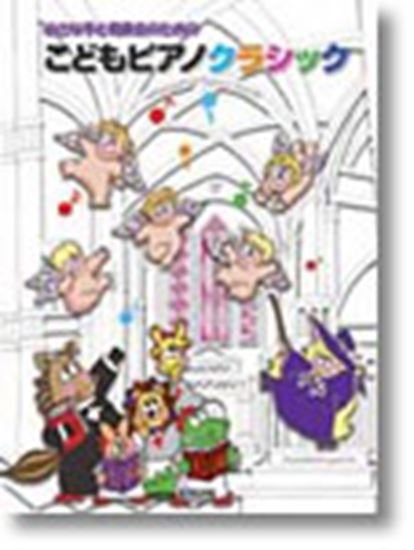作品概要
出版年:1922年
楽器編成:ピアノ合奏曲
ジャンル:種々の作品
総演奏時間:25分00秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (2)
総説1 : 中西 充弥
(4992 文字)
更新日:2015年6月9日
[開く]
総説1 : 中西 充弥 (4992 文字)
【総説その1】 日本では多くの方が学校での音楽鑑賞の時間に聴かれたことがあろう。CDもたくさん出ており、演奏会で聴く機会も多い。そのため、我々は何か良く知っているつもりになるけれども、実は何も知らない、これほど謎に満ちた曲は珍しい。唯一確実に言えることは、サン=サーンスが生前「白鳥」を除いて公開演奏、出版を禁止したことである。この経緯についても、不明と言わざるを得ない。なぜなら、明らかにしても良いほどの禁止理由なら、そもそも禁止する必要もないからである。サン=サーンスは死後の遺産管理を彼の秘書に託しており、この優秀な秘書のおかげで、多数の書簡が現在まで保存されるとともに、おそらく、人目に触れさせたくない余りに個人的な内容の文書は破棄された可能性が高い。というわけで、禁止理由に触れた書簡は不思議なほどに残っておらず、もちろん、星の数ほどのサン=サーンスの著作物にも言及されることはなかった。謎である。このことは別途詳しく検討することにしよう。
この曲は、1886年、チェリストのシャルル・ルブークが企画した私的な演奏会(1886年3月9日の謝肉祭の肥沃の火曜日(マルディ・グラ))のために書かれたが、ルブーク自体はあまりぱっとしない人物で、チェリストというより、演奏会シリーズの企画者として当時知られていた。しかし、初演のメンバーにはそうそうたる演奏家が集まった。作曲家本人とルイ・ディエメールのピアノ、ポール・タファネルのフルートなどである。ちょうどこの時期は、「オルガン付」の《交響曲》の作曲時期と重なり、本人の書簡にも息抜きとして《謝肉祭》の作曲を楽しんでいる様子が窺える。
現在日本では《動物の謝肉祭》というタイトルが定着しているが、謝肉祭とはカーニバルである。リオの有名なカーニバルを思い浮かべて頂いて問題ない。フロート車(山車)を伴った華やかなパレードであるが、このイメージを持って頂くと、容易に各曲のタイトルの説明がつく。副題として〈動物学の大幻想曲〉とあり、天文学や植物学など自然科学にも造詣の深かったサン=サーンスの鋭い視点で、動物たちの行進を「観察」しているのである。 当サイトはピアノ曲の紹介サイトであり、四手版の解説を書くべきところであるが、この版は作曲家の死後別人の手によって編曲、出版されたものであり、本人のお墨付きを得ていない。また、四手ピアノで演奏する際に重要なことは、原曲のオーケストレーションの色彩感を表現することにあるから、原曲の解説を行うこととする。
〈序奏と堂々たるライオンの行進〉
ライオンは百獣の王であるから、「ロイヤル・マーチ」であり、堂々として威厳のあるメロディーが弦楽器のユニゾンで、次いで第一ピアノの両手のユニゾンで奏でられる。伴奏に第三音を欠く空虚五度の和声持続音(と言っても、ピアノでは音を長く保持できないので、代わりに和音の連打)が見出だされるが、このユニゾンのメロディーとそれを支える空虚五度の持続音というコンビは、すでに歌劇《サムソンとダリラ》中の有名なバレエ〈バッカナール〉中にも見出される、サン=サーンスの「オリエント」様式のひな形なのである。何てステレオタイプで紋切型な、と誹りも受けるかもしれないし、また当時は植民地時代であったので、「上から目線だ」と批判されがちなのであるが、作曲家本人は頻繁に外国旅行し、異国の文化も積極的に学ぼうとしていたので、どちらかというと、当時の聴衆の知識レベルに合わせたと言った方が良いであろう。なぜなら、サン=サーンスがいくら世界中で実際に各地の音楽を聞き、研究をしてその成果を自作の中で披瀝しても、聴衆の知識、教養が追い付かなければ、それとは認識してもらえないからである。例えば、19世紀末パリでは日本趣味が流行するが、美術の分野では実際にモノが輸入され、オリジナルを手に取ってみることができるのに対し、レコードもない時代、異国の音楽を手軽に聴くことは大変難しく、当時の人々の認識もまだ低かったことを考慮頂きたい。ちなみに、ここでいう「オリエント」とはフランスから見ての「東洋」であり、ギリシャ・ローマ(の古典文化)も既にフランスにとって「東」であり、当時流行したスペイン趣味にしても、イスラム文化の残り香を伝えるという意味で当時のオリエンタリスムの一翼を担っていた。ライオンと言えばアフリカであるが、アフリカも当時のフランス人にとって「オリエント」であり、この雑駁な一括りも、ヒト・モノの交流が困難な時代の小さな世界観を反映しているのである。
〈雌鶏と雄鶏〉
起承転結にあてはめるなら、まだ「承」なので、毒はなく純粋な描写音楽である。ただ、現在は日本でもスポーツウェアのブランドマークでお馴染みになっているが、鶏とはフランス、フランス人の象徴であり、親しみ深いものであるから、先頭集団に位置するのは当然のことなのである。後にプーランクも動物をテーマにした《典型的動物》というバレエ作品を作曲するが、この中の〈二羽の雄鶏〉では当時の占領下の時代を反映して、愛国的なメッセージが埋め込まれたりするのである。「コココココココケー、コココココココケー」と小刻みに鳴いているのが雌鶏で、それを断ち切るかのように高らかに「コッケコッコッコー」と鳴くのが雄鶏である。ちなみに、擬音語は各言語でまちまちであり、フランス語では鶏は「ココリコ」「コクリコ」と鳴くのだが、この四音節にサン=サーンスの鶏の鳴き声(音符の数)は対応していない。交響詩《死の舞踏》で朝一番を告げる鶏も五音節で鳴く。「コッココッリコー」ということであろうか…。
〈らば(アジアノウマ)〉
アジアノウマは中近東からモンゴルにかけて存在する種で、日本では馴染みがないため便宜上ロバ、ラバ等訳されているが、上述の荒涼とした大地に適応して生息している種であるから、運動能力は高く、速足で駆け回ることができるのである。原曲でもピアノ奏者二人による一オクターブ離れたユニゾンとなっており、さながら「かけっこ」である。
〈亀〉
まず、ここで押さえておくことは、これは「カーニバルのパレード」なのである。仮装行列が登場するのである。そしてフロート車の上で亀が何に扮するかと言うと…フリフリのドレスから短い脚を振り上げ…られないと思うのだが、脚を出して一生懸命フレンチカンカンを踊っている踊り子なのである。見ている観衆はワッハッハ…というのがこの曲の主眼である。亀の歩く速さにテンポを落とされて隠されたテーマは「天国と地獄」の邦題で有名なオッフェンバックのオペレッタ《地獄のオルフェ》からのものである。穿った見方ではオッフェンバックを批判しているという説もあるが、そこまで考える必要はないであろう。何故なら、当時はオペラとオペレッタの間には格式の点で大きな差があり、完全に棲み分けされた業界であったのだが、サン=サーンスはもとより大衆的なオペレッタには眼中がなく、あくまでオペラでの成功を願ったからである。
〈象〉
こちらもパロディーとして有名であるが、ベルリオーズの《ファウストの劫罰》より「妖精の踊り」とメンデルスゾーンの《真夏の夜の夢》の「スケルツォ」の引用がされている。どちらも妖精がテーマであるから、象たちはあの巨体にかわいらしい妖精の羽を付けて行進しているのである。このシュールな光景を思い浮かべてワッハッハ…と笑って頂きたい。そしてこれは純粋に仮装行列の視覚的なおかしみの効果を狙ったものであり、ベルリオーズを批判している、等の穿った見方はやはり不要である。ベルリオーズは若き日のサン=サーンスを引き立ててくれた恩人の一人であり、敬愛する作曲家の一人であったからだ。
〈カンガルー〉
カンガルーはそのピョンピョン飛び跳ねる様を音楽で表現した描写音楽であり、曲も短いためそれ以上の意味はないであろう。
〈水族館〉
水族館は動物か、というともちろんそうではない。冒頭で説明したように、これはカーニバルの行進であり、魚を歩かせることはできないので、フロート車に水槽を載せているのである。水族館のトンネル水槽ですいすい泳ぐ魚たちを見上げる光景は何とも幻想的であるが、その様子と印象を描写している。オーケストレーションとしてはやはり最初に注意を引くのはグラス・アルモニカ(グラス・ハープと同じ発音原理の楽器)の音であり、これが曲のトーンを支配しているけれども、実は陰にこっそり忍び込ませてあるフルートの中低音域も見逃せず、ドビュッシーの《牧神の午後への前奏曲》以降、印象派等で多用されるフルートの用法を先取りしている。
〈耳の長い登場人物〉
何とも意味ありげなタイトルがゆえに、多くの憶測を呼び、敵対する批評家を揶揄しているのではないか、との説もあるが、作曲家本人の証言がないので、謎としか言いようがない。少なくとも、確実なのは、このタイトルと実際の曲(ヴァイオリンによるヒハーンといういななき)を聞いてフランス人が真っ先に思い浮かべるのがロバであるということである。よって、このタイトルは動物当てゲームであるとするのが一番無難な回答であるが、実はフランスでは、ロバはのろまの代名詞なのである。かつてフランスの学校では、宿題をしてこないような不真面目な生徒の懲罰の一つとして「ロバ帽子」があった。ロバの耳をかたどった帽子を被せて教室の隅などに立たせるのである。タイトルには「登場人物」とあるから、もしかしたら、誰かにロバ帽子を被せてカーニバルの行進させている図なのかもしれない。だとすれば、公然のさらし者にしているわけなので、かなり屈辱的なものであり、それだけ憎い人物がいたのであろうか。もともとこの曲は内輪の集まりのために書かれた曲であるから、当事者の間では「ああ、あいつのことか」と聞きながらニヤニヤしていたのかもしれないが、今となっては謎である。
〈森の奥のかっこう〉
森の奥でひっそり隠れるカッコウの鳴き声が遠くから聞こえる情景である。フロート車に木々を載せて行進しているのだが、カッコウは恥ずかしがり屋なので外に出ず、逃げ出さないので、次の曲のような鳥籠が必要ないのである。但し鳴き声しか聞こえない。カッコウの鳴き声を模倣するクラリネットは舞台袖で演奏し、視覚的にも音響的にも距離感を演出する。ピアノはウナ・コルダで演奏して、幻想的な森のうっそうとした様子を和音の厚みで表現する。
〈大きな鳥籠〉
打って変わって、普通の鳥は放っておくと空に飛んで行ってしまうので、フロート車に大きな鳥籠を設えているのである。作曲家が観察し、目で追っている鳥は縦横無尽に鳥籠中を飛び回り、その様子がフルートによって描かれるが、弦楽器のトレモロがその他の鳥の羽音を表し、ピアノによってさえずりが表現される。
〈ピアニスト〉 総説その2にて
〈化石〉
「大きな鳥籠」までが起承転結の「承」であり、「耳の長い登場人物」の意味ありげなタイトルの謎を除いては、動物たちがカーニバルの(仮装)行列をするという視覚的な有様を音楽という聴覚的な効果に移し替えることでおかしみを表現してきた。ここから二曲は動物と呼ぶには抵抗のある変なものが登場する「転」である。やはり、この二曲は《動物の謝肉祭》にとって最も重要な曲であるから、別に章立てしてお話することにする。
〈白鳥〉
学校の音楽鑑賞のおかげで、クラッシック音楽のファン以外にも大変馴染みのある曲である。残念ながら、初演の夕べを企画し、初演時にチェロを弾いたルブークは、チェリストとしてはそれ程有能な人物ではなかったようである。とはいえ、会の主催者として花を持たせるために終曲の直前にこの美しい曲が配置されたと考えてよいだろう。それまでのブラック・ユーモアに対する口直し、清涼剤としても機能しており、曲の構成は巧みに練られている。
〈終曲〉
これまではカーニバルのパレードを間近で観覧してきたのだが、ここでは少し高いところから全体を俯瞰している。実際曲中に現れるモチーフはライオン、らば(アジアノウマ)、鶏、カンガルー、ロバであるが、一応全員揃い踏みということで華やかにパレードが締めくくられる。
総説2 : 中西 充弥
(3078 文字)
更新日:2015年6月9日
[開く]
総説2 : 中西 充弥 (3078 文字)
【総説その2】
〈ピアニスト〉
フロート車にピアノとそれを練習する奏者が乗り込んでいる様子である。楽譜には、作曲家ではなく出版社(ジャック・デュラン)の注記として「初心者の下手な演奏を真似するように」とあるが、作曲家もそれを想定していたであろう。作曲家紹介の概説でサン=サーンス自身もピアニストとして活躍したことを述べたが、よって、これは一種の自虐ネタでもある。華やかなステージの陰で、毎日地味な基礎練習に追われる哀れな演奏家の日常を活写しているのである。内容自体は非常に分かりやすいネタであるが、そもそも、この曲は《動物の謝肉祭》の制作動機と密接に関わっている。
もともと、この作品はサン=サーンスがニーデルメイエル宗教音楽学校でピアノ教師を務めていた頃(1861~1865年)この学校の生徒たちのために着想されており、この哀れな〈ピアニスト〉たちのモデルはニーデルメイエル校の生徒たちに他ならない。どれくらい哀れだったかと言えば、後に同校で勉強した作曲家、アンリ・ビュッセルの回想録からの引用を読んで頂けるとその情景がありありと目に浮かんでくる。「広い長方形の(練習)室に入ったとき、私はまったく驚いてしまった。壁に向かって十五台の竪型ピアノがずらりと並び、それぞれが同時に別の音楽を奏していたからである。それは、すさまじさのある轟音と言うべきものであって、私たちが室内に入ってもやまないのであった。けれども、校長の命令の身振りによって、十五人のピアノ奏者たちは、ぱっと手をとめた。その超多調的な交響には、バッハとベートーヴェンとモーツァルトがさわがしく同居していたが、それらがすこしずつ合間をおいて途絶えていった。」(アンリ・ビュッセル著、池内友次郎訳編『パリ楽壇70年』音楽之友社1966年)
《動物の謝肉祭》中においてピアノが二台必要な理由は、室内アンサンブルに豊かな響きが欲しかったことはもちろんだが、この「超多調的な」雰囲気にインスピレーションを得た、〈ピアニスト〉のネタを実現するには複数台のピアノが必要だったことも大きな要因であると考えられる。またこの作曲の経緯を知った上で、もう一度〈らば(アジアノウマ)〉を見返すと、まだあどけない学生たちが共同練習室で一緒に速弾き競争をしていた図なのでは、とも想像される。
〈化石〉
ピアニストはまだ「生きている生物」であるからよいが、さらに混迷の度を深めるのが〈化石〉の謎である。化石と言っても、アンモナイト、三葉虫、始祖鳥…と色々あるが、ここで作曲家が想定しているのはティラノサウルスのような恐竜である。本人が自筆譜にイラストまで描いている。
ということで、何の化石か、という問いはあっさり解決するのだが、この恐竜は一体何の象徴かという問題が出てくる。ここまで様々なブラック・ユーモアを見てきて、この〈化石〉において何もないわけがないのだが、作曲家本人の直接証言が無い以上、その答えとして断言できるものは見当たらない。以下は私の解釈を述べさせて頂く。まず、冒頭にサン=サーンス自身の《死の舞踏》のテーマが出てくるが、シロフォンで演奏され、骨をカチカチ言わせながら恐竜の化石が死者の踊りを踊っている様子が提示される。続いて、フランス人ならだれでも知っている民謡、《大事なタバコ》、《きらきら星》、《月の光》が引用されるのだが、この平和でメルヘンな世界は、これまでのブラック・ユーモアに比べると何か胡散臭く、嵐の前の静けさといった印象を受ける、その期待を見事に裏切らず、《死の舞踏》のテーマが再び演奏された後の第二部にとんでもないジョークが待ち受けるのである。それはクラリネットの旋律である。これは二つのメロディーが繋ぎ合わされて出来ているのであるが、前半部分は《シリアに旅立ちながら》という曲である。日本人はもちろん聴く機会はまずないし、現在のフランス人にも存在自体忘れ去られているような曲であるが、実はこれ、ナポレオン三世の母のオルタンス妃が口ずさんだメロディーをもとに作られた曲であり、第二帝政期には国歌の代わりとしてナポレオン三世の前で盛んに演奏されたものなのである。彼は、普仏戦争に敗れ、イギリスに亡命してそのまま彼の地で亡くなったのだが、つまり、今となっては力を失って骨しか残っていない恐竜(モンスター)とはナポレオン三世のことであった。そして、そんな彼が発するメッセージというのが後半部分となる。ロッシーニの歌劇《セビリアの理髪師》より、ロジーナのアリア「ウナ・ヴォーチェ・ポコ・ファ」である。ヒロインのロジーナが自分を家の外に出さない後見人の手から逃れ、自分の恋を成就させるのだと決意を表する場面である。すなわち、イギリスに亡命したままフランスに帰れなかったナポレオン三世が、墓の中で、フランスに戻って天下を取り返すぞと息巻く、負け犬の遠吠えの歌なのであり、そこでワッハッハ…という笑いが起こったと考えられる。サン=サーンスの周囲には第二帝政期間中、歌手ポーリーヌ・ヴィアルドのように亡命を余儀なくされ、不遇の時代を送った人がいたのである。そしてここで振り返ってみると、先に出てきたフランス民謡はナポレオン三世の望郷の歌だったのかもしれない。
※「《動物の謝肉祭》の生前の出版、演奏禁止の理由」
よって、ここまで説明すると、サン=サーンスが遺言の中で、《動物の謝肉祭》の出版、演奏を生前禁止した理由が納得できるのではなかろうか。それは、政治的な理由である。ナポレオン三世とその皇子は既に亡くなっていたとはいえ、ボナパルティストの残党の火はまだくすぶっていた時代であるから、万が一、世の中が変わって、〈化石〉の意味を知られてしまったら、不敬の罪で作曲家の公的な立場は非常に危なくなる恐れがあったのである。実際、《動物の謝肉祭》の初演が終わってからすぐにこの曲の評判は広まり、リストすら聴きたがった程である。よって、作曲者の知らないところで勝手に演奏会が企画され、大慌てで中止を求める書簡が残るなどしている。サン=サーンスのこの神経質な対応はこの曲がただの曲ではないことを裏付けている。 しかし、これは少し深読みし過ぎた説と取られるかもしれないので、最後にもう少し当たり障りのない回答をしておこう。
サン=サーンス自身、この曲について書簡の中で、「滑稽なもの」と表現しており、《動物の謝肉祭》はまさに冗談音楽であった。このような例は、モーツァルトの《音楽の冗談》K.522に既に例があるが、あくまで身内のネタであり、生前に公開してしまうと自らの名声に傷をつけてしまう恐れがあった。
また、18世紀フランスにおいては、エリート文化と大衆文化の乖離が始まったが、その中で、野蛮な大衆文化とみなされたものの一つに、共同体の規律を犯した者の家に行ってどんちゃん騒ぎをする「シャリヴァリ」という儀礼があったが、これと同じく下品で無秩序なものとされたのが「カーニバル」であった。この曲はもともと学生たちのために着想されたものであり、若気の至りというか、若者のどんちゃん騒ぎの要素が残っている。よって、オペレッタのような大衆的な成功に関心を寄せなかった教養人(オネットム)として、サン=サーンスは大衆的な《動物の謝肉祭》を人前に出したくなかったと考えられる。サン=サーンス自身、この曲が「受ける」ことは重々承知していたので、それによって他の「真面目な」作品が取り上げられなくなることを恐れたのである。
楽章等 (14)
ピティナ&提携チャンネル動画(22件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (71)
![双頭の鷲の旗の下に[やさしいピアノ・ソロ]世界のマ-チ2 - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/129.jpg)
ハンナ(ショパン)

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

カワイ出版

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)リットーミュージック

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)共同音楽出版社

(株)タイムリーミュージック

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

(株)リットーミュージック

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社
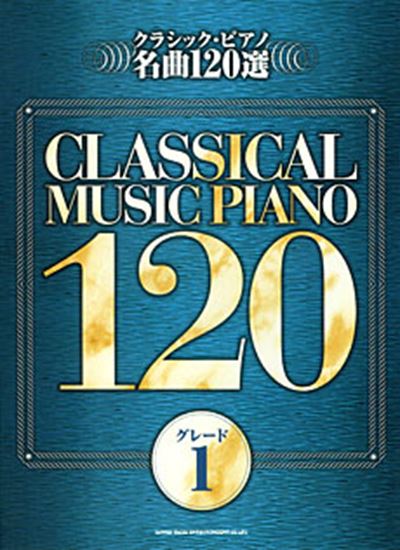
(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ドリーム・ミュージック・ファクトリー(株)

(株)共同音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド

(株)ヤマハミュージックメディア

カワイ出版

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)自由現代社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド

(株)全音楽譜出版社

(株)スーパーキッズレコード

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

インターナショナル・ミュージック社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)レッスンの友社

(株)共同音楽出版社