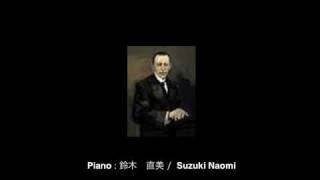作品概要
出版年:1911年
初出版社:Gutheil
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:前奏曲
総演奏時間:46分30秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (1)
執筆者 : 和田 真由子
(2202 文字)
更新日:2007年9月1日
[開く]
執筆者 : 和田 真由子 (2202 文字)
ラフマニノフは、《前奏曲 作品3-2》、《10の前奏曲 作品23》、《13の前奏曲 作品32》をのこしており、これらの計24曲の作品は、それぞれ異なった調性でかかれている。作品23からおよそ7年後にあたる1910年に、モスクワで作曲された。作品23と比較すると、近代的な手法の影響もみられるが、基本的には情緒的な性格をそのまま受け継いでいる。
1.ハ長調 / 13 Preludes op.32-1 C dur アレグロ・ヴィヴァーチェ
一分半ほどの短い曲。3連音符のリズムが曲を貫いており、その上に旋律がきかれる。全音音階を扱った和声が大胆に使用され、技巧的にも難易度は高い。
2.変ロ短調 / 13 Preludes op.32-2 b moll アレグレット
冒頭の静かな主題からはじまるが、この付点のリズムが全体を通して扱われている。拍子や速度を変化させ、微妙なニュアンスをつくりながら、音楽は次第に高まりをみせる。
3.ホ長調 / 13 Preludes op.32-3 E dur アレグロ・ヴィヴァーチェ
力強い冒頭から始まる。トッカータ風で、全体的に華やかで豊かな響きをもった曲。最後は静かに曲をとじる。
4.ホ短調 / 13 Preludes op.32-4 e moll アレグロ・コン・ブリオ
3部形式による。演奏時間も長く、難易度が高い。フォルテで奏されるオクターブと、3連音符で奏される厚みのある和音がかけあいながら曲が進行する。中間部にうつり、8分の9拍子、ピウ・ヴィーヴォで3連音符が軽やかな動きをみせ、拍子を変えながらフォルテッシモに向かう。続いて、レントで歌われるのは、ロシアの叙情歌の旋律である。再び主部に戻り、より一層激しさを増して、クライマックスを形成する。徐々に静まり、冒頭の楽想を再現したのち、ピウ・ヴィーヴォで、そして消えるように曲を閉じる。和音は太く、温かみがある音で、バランスよく奏されたい。
5.ト長調 / 13 Preludes op.32-5 G dur モデラート
穏やかな雰囲気の左手の分散和音にのせて、右手で美しい旋律を奏でる。細かい音の動きは鳥の声を模している。全体的に静かだが、華やかなカデンツァも印象的である。広く愛奏されている魅力的な作品。ラフマニノフの録音も残っている。
6.ヘ短調 / 13 Preludes op.32-6 f moll アレグロ・アパッショナート
情熱的・悪魔的な音の動きが印象的な練習曲風の作品。ダイナミックの変化が効果的な作品。
7.ヘ長調 / 13 Preludes op.32-7 F dur モデラート
3部形式による。同型の全曲を通してリズムパターンが使用されており、その上と下でそれぞれ旋律がゆったりと歌われる。
8.イ短調 / 13 Preludes op.32-8 a moll ヴィーヴォ
激しく、印象的な2小節の導入部分をもつ。そのままの勢いで、16分音符がめまぐるしく動き、全曲を貫いている。持続音を用いた、かけあがるような左手が曲の情熱的な雰囲気をより一層もりあげている。
9.イ長調 / 13 Preludes op.32-9 A dur アレグロ・モデラート
外声部がデュエットの形でかかれている。和音が多く重なり、それぞれを弾き分けるのには高度なテクニックが必要である。和音の厚みのある豊かな響きを大切にしたい。「ピウ・ヴィーヴォ」のコーダでは、右手のアルペッジョで微妙に変化をつけながら、静かに曲を閉じる。
10.ロ短調 / 13 Preludes op.32-10 h moll レント
悲しみを感じさせるような旋律がゆったりと静かが歌われ、しだいに音量を増していく。中間部では、和音が重ねられ、非常に壮大で豊かな音色が求められる。また後半でみられる長大なカデンツァがうみだす音響は、幻想的な雰囲気をつくりだしており、印象的である。
11.ロ長調 / 13 Preludes op.32-11 H dur アレグレット
弱起の技法や、フレージングなどにより独特なリズムの面白みが与えられている。短いが、優雅で愛らしい小品。
12.嬰ト短調 / 13 Preludes op.32-12 gis moll アレグロ
前奏曲集の中で最も広く親しまれている傑作の一つ。雪でおおわれた大地をソリが鈴を鳴らしながら走る様子を表しているといわれる。テンポが劇的に変化するのが特徴である。全曲を貫くめまぐるしい分散和音に対して、旋律は豊かな音で、たっぷりと歌う。ラフマニノフの録音が残っているが、当時の録音機器は回転速度が違っていたため、現在のレコードプレーヤーで聞いた演奏は、実際のものよりも速くなっていることに注意が必要である。
13.変ニ長調 / 13 Preludes op.32-13 Des dur グラーヴェ
この曲も、前奏曲集の中で最も有名な曲の一つ。3部形式によっている。冒頭から荘重な主題は、しだいにリズム的な動きをみせる。メノ・モッソの中間部を経て、アレグロ、ピウ・ヴィーヴォと、音楽は激しい高まりをみせる。再び登場する主部は、非常に華やかに装飾され、ポーコ・ピウ・ヴィーヴォではピアノの限界に達するともいえるほど豊かで厚みのある音響が要求されている。演奏時間は7分前後で、前奏曲集をしめくくるにふさわしい大曲である。
楽章等 (13)
ピティナ&提携チャンネル動画(20件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (8)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

ショット・ミュージック(株)

ブージー & ホークス社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社

 ステップレベル:発展4,発展5,展開1,展開2,展開3
ステップレベル:発展4,発展5,展開1,展開2,展開3