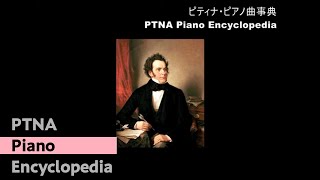作品概要
解説 (3)
解説 : 稲田 小絵子
(103 文字)
更新日:2019年1月6日
[開く]
解説 : 稲田 小絵子 (103 文字)
アレグレット、変イ長調、3/4拍子。
冒頭は同主短調の変イ短調で始まる。トリオ部分は嬰ハ短調つまり冒頭の下属調(異名同音)をとる。異名同音を利用した転調が、スムーズでありながらも印象的な進行をもたらしている。
解説 : 髙松 佑介
(575 文字)
更新日:2019年4月8日
[開く]
解説 : 髙松 佑介 (575 文字)
第4曲:アレグレット、変イ短調、4分の3拍子
主部―トリオ部―主部という三部形式を取り、各部とも和音を様々に用いて構築されている。
主部は変イ短調で始まり、右手の分散和音と第2拍を強調した左手のリズムで構成される。これら動きのある4小節と、動きに歯止めをかける四分音符の2小節が交互に繰り返された後、四分音符による和音の連続が8小節続くと、不意に変イ長調へと転じる。長短調の突然の転換は、シューベルトの好んだ手法だ。変イ長調になると、四分音符のフレーズが現れなくなり、さらに冒頭では2小節単位だった分散和音が1小節単位に縮まることで、切迫の効果が生まれる。これを土台として、低声部に初めて旋律的な主題が現れ(第47小節)、不協和音(第68小節)へと徐々に高揚する。それが静まると、例の主題が三連音の分散和音を伴って高声部に奏でられ(第72小節)、十六分音符の分散和音が回帰して主部を閉じる。
トリオ部は、変イ音を嬰ト音として読み替え、嬰ハ短調となる。ここで旋律を支えるのは、分散和音ではなく、和音の連打である。トリオ部も三部形式を取るが、主部が同主長調で回帰し(第139小節)、長短調の転換が行われる。
主部が回帰すると、コーダはなく、変イ長調のまま2つの和音によるカデンツで堂々と締めくくられる。第1曲とは異なり、一義的な長調での終止となっている。
演奏のヒント : 大井 和郎
(794 文字)
更新日:2025年10月9日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (794 文字)
あまりにも有名な即興曲ですが、起こりやすい問題を挙げてみます。まずテンポの問題です。テンポは場所によって変えない様にして下さい。典型的なのは、1〜4小節間がもの凄く速く、5〜6小節間がもの凄く遅いという演奏です。これでは果たして何拍子の曲かさえも判らなくなります。テンポは1つにして、その中で表現をして下さい。もう1つ、よく起こりうる事で、曲自体のテンポをもの凄く速く設定してしまう学習者がいます。アレグレットです。アレグロではありません。決して速くなりすぎない様にしてください。
47小節目以降、左手にメロディーラインが来ます。この時、47〜49小節間には、非和声音が1小節につき、たった1つだけ存在します。それは3拍目裏拍の8分音符で、経過音の役割を果たしています。この8分音符は非和声音ですので、解決音によって和声そのもは変化するものの、例えば、47小節目の非和声音Gは、48小節目でFに解決すると考えます。その時、そのFには決してアクセントは付けない様にしてください。以下同様です。1拍目の音符にはアクセントを付けず、2拍目の音符で音量を上げる用にして下さい。
加えて、これはこの曲に限らず、シューベルトの多くの曲に共通して言えることでもありますが、とにかく繰り返しが多くあることが特徴で、その繰り返しを、1回目と2回目全く同じように演奏するのではなく、何かしら変化が欲しいです。冒頭1〜2小節間と3〜4小節間でさえも、何かしらの微妙な変化が欲しいです。そして、長調が短調になる部分、あるいはその逆、の部分はカラーの変化が欲しいです。とにかく、同じように平坦に弾かないことが、シューベルトの場合特に重要です。
ピティナ&提携チャンネル動画(7件)
楽譜
楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)学研プラス

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

Musikverlag Doblinger