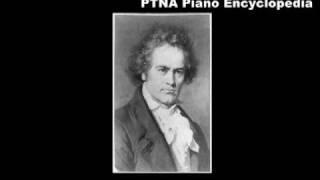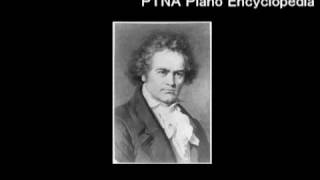作品概要
出版年:1825年
初出版社:Schott
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:バガテル
総演奏時間:19分30秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (2)
執筆者 : 岡田 安樹浩
(524 文字)
更新日:2009年7月5日
[開く]
執筆者 : 岡田 安樹浩 (524 文字)
この作品には、異なる時期に書きつけられた3種類のスケッチと、浄書譜が存在する。これらは1823年から24年にかけて書かれたもので、同時期には『ディアベリのワルツによる変奏曲』が作曲されている。
6曲からならこのバガテルは、1曲目のスケッチの欄外に「小曲の連作Ciclus von Kleinigkeiten」と書き込まれていることから、通して演奏されることが意図されていたことがわかる。
全体は、ゆったりとしたテンポでアリオーソ風の楽想を中心とした楽曲と、急速なテンポによる楽曲とが交互に配置されており、このような配列は後期の弦楽四重奏曲(嬰ハ短調Op.131など)にみられる。また、第1・3曲の途中に挿入されるカデンツァ風の走句も、後期のピアノ曲に多数認められるものである(Op.110など)。
楽曲相互の調性関係は、第1曲ト長調から第2曲ト短調への同主調関係にはじまり、VI度調(長3度下)の第3曲変ホ長調、つづいて第4曲ロ短調は同主短調のVI度調(変ハ短調)の異名同音読み換え、第5曲ト長調はVI度調、そして終曲の変ホ長調は同主短調のVI度調と、ベートーヴェンが積極的に導入している上下3度の関係調とその異名同音読み換えによって関連づけられている。
解説 : 鐵 百合奈
(2418 文字)
更新日:2019年10月6日
[開く]
解説 : 鐵 百合奈 (2418 文字)
バガテル Bagatelleとはフランス語から来た言葉で、「ささいなこと」「取るに足らないもの」という意味である。バガテルと題された作品集は、作品33、作品119、作品126と三つある。この中で、作品126のみは、ベートーヴェン自身が楽譜の冒頭に「小曲たち」(複数形。Kleinigkeiten)と書き込んでおり、短期間で続けて作曲されたこと、調性の配置の工夫、全6曲の曲想の関連などから、連作として構想されたことは明らかと言える。このバガテルは、交響曲第9番を作曲した後の1823年から1824年に書かれ、ベートーヴェンの最後のピアノ作品となった。彼は初版の出版社であるショット社に「非常に精巧で、私がこのジャンルで書いた中で最高のものだ」と書き送っている。第2番以降、長3度ずつ下行していく調設計がなされ、全体の構成に均整がとれており、短いながらもまさに最後の精華と言えるだろう[1]。
第1番 Op.126-1 ト長調
Andante con moto 歩く速さで、動きをもって
Cantabile e compiacevole 歌うように、そして楽しそうに気持ちよく
冒頭のコラール風の8小節が、自由に変奏されていく。第9小節目からは弦楽伴奏を伴うソロ歌唱のよう。それが第17小節目からは弦楽三重奏を思わせ、第21小節目l’istesso tempo「1拍の長さを変えずに同じ速さで」以降、器楽的なテクスチュアにほどけていき、第30小節目molto ten. non troppo presto「とてもテヌート(音を充分に保持して)で、速すぎずに」から優雅なカデンツァになる。音が舞い遊んで戻ってきたテーマはさらに豊かな彩色を施されて変容し、命を得たバスが2オクターヴ半もの広範囲を降りていく。曲尾は左右の手が交差し、大切なものを両手でそっと包み込むように終える。
第2番 Op.126-2 ト短調
Allegro 快速に
焦燥と緊張が張りつめた走句と切実な祈りの歌が、間髪をいれずに交互に繰り返される。この曲想と構成は、モラヴィア(現在のチェコの一部)に生まれた後世の作曲家ヤナーチェク(1854~1928年)の《草かげの小径》第10番〈梟は飛び去らなかった〉に似ている。モラヴィア地方には、「瀕死の人の住居にはふくろうが留まり、それを追い払えなければ助からない」という言い伝えがあり、アルペジオはふくろうを追い払う手の動きである。ベートーヴェンの秘書シンドラーはモラヴィア出身であり、ベートーヴェンはこの言い伝えを知っていたのかもしれない。いずれにせよ、死を招くふくろうを追い払うようなアルペジオの冒頭のモティーフは重要である。中間部はcantabile「歌うように」で、幸せな頃の美しい記憶が回想されるが、冒頭のモティーフが割り込み、亀裂が入るにつれ現実に引き戻されていく。
第3番 Op.126-3 変ホ長調
Andante 歩く速さで
Cantabile e grazioso 歌うように、そして優雅に
第1・2番のト調から、長3度下の調である変ホ長調が設定されている。中期のピアノ・ソナタの緩徐楽章を思わせる楽想から始まり、Bのオクターヴによる保続音の後、薄布を翻すようなカデンツァが現れ、それからは浮遊する後期の語法で書かれている。透徹した煌めきが天上の音楽のようで、この上なく美しい。最後は残り香が儚く漂う。
第4番 Op.126-4 ロ短調
Presto 極めて速く
第3番からさらに長3度下のロ短調(第3番の変ホ長調を異名同音の嬰ニ長調に読み換えて考える)。ロ短調は不吉な調であり、ここでも悪魔的に打ち付けるような曲調となっており、とくに属音Fisの連打(冒頭のアウフタクトや、第21小節目、第25小節目など)が不気味。幸せに満ちたロ長調の中間部(第52小節目~)は、初期のピアノソナタ第7番第2楽章第36小節~の、切々と訴えるように歌う極めて印象的な楽想と、右手の音形が同じである(左手は《田園》風の音型)。ベートーヴェンが、昔の曲を回想して掬い上げ、救済を与えているのであろうか。
第5番 Op.126-5 ト長調
Quasi allegretto アレグレット(やや快速に)のように
涼しいそよ風が吹く、舞曲風の牧歌。穏やかな流れにたゆたい、万華鏡のように明暗の調に揺らぐ。情感に溢れた右手の歌と、それに優しく相槌を打つ左手の重音が仲睦まじく、ほほえましい。中間部(第17小節目~)は慈しみに満ちたハ長調となり、cresc.とともに左右の音域が離れていく。最後は両手とも高音域で、冒頭の牧歌を神秘的にささやく。
第6番 Op.126-6 変ホ長調
Presto 極めて速く - Andante amabile e con moto 歩く速さで愛らしく、そして動きをもって - Tempo Ⅰ 冒頭のテンポで
冒頭のプレストは4+2の6小節で疾風のように過ぎ去り、続く主部は3小節を基本単位としている。空虚5度の左手の上で右手が控えめに言いよどむ前楽節6小節(第7~12小節目)と、豊かな弦楽四重奏のような後楽節6小節に続いて、ゆったりとした舞曲風の左手の上を右手の三連符がひらひらと漂う3小節の短いコデッタが付加される。第22小節目からコデッタの三連符のモティーフが展開された後、空虚5度が三連符になり謎めいた雰囲気になって前楽節が再現され、後楽節は広音域にわたって3度の重音が昇っていくという、原型をほぼ留めないほどの変容が施されている。コデッタだけが同じ音型のまま再現し、さらに展開していき、はらはらと天から舞い落ちてきて、鏡に映るように下行していく前楽節に沈み込む。着地したかと思いきや、冒頭の一陣の風が吹き抜け、すべては泡沫(うたかた)の夢だったと気づかされる。
[1] 本解説内の譜例は、Breitkopfの旧全集を使用。
楽章等 (6)
ピティナ&提携チャンネル動画(15件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(8件)
楽譜
楽譜一覧 (6)

(株)春秋社

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Peters

 ステップレベル:発展4,発展5,展開1,展開2,展開3
ステップレベル:発展4,発展5,展開1,展開2,展開3