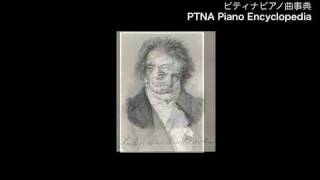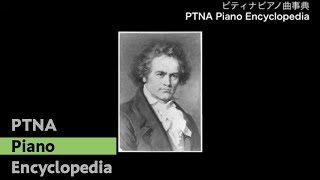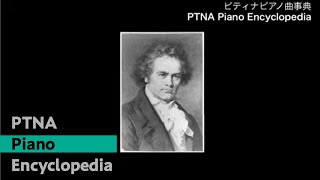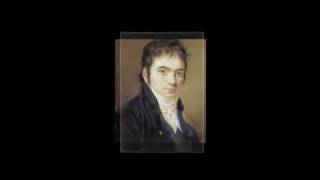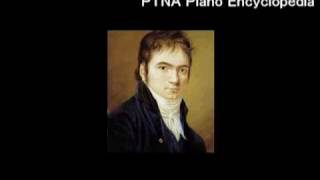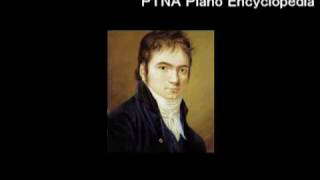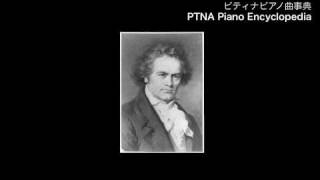ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 Op.110
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.31 As-Dur Op.110
作品概要
解説 (1)
執筆者 : 岡田 安樹浩
(869 文字)
更新日:2009年7月1日
[開く]
執筆者 : 岡田 安樹浩 (869 文字)
Op.109同様、簡潔でコンパクトにまとめられたソナタ形式の第1楽章と、それとは対照的な広がりをもった自由なフーガによる第3楽章という楽曲構成をもっている。
1821年の末には一応の完成をみたが、フィナーレをさらに推敲した結果、最終的な完成は22年の春頃となった。
第1楽章 4分の3拍子 変イ長調 ソナタ形式
叙情的な主要主題は、付点リズムをもつ4声書法による前半4小節と、歌唱風の旋律を単純な和声的伴奏が支える後半6小節からなる。アルペジオによる推移(第12小節~)を経て、副次主題(第28小節~)が属調であらわれる。
展開部(第40小節~)は主要主題前半4小節の動機によって構成され、ヘ短調、変ニ長調、変ロ短調を経て、再現部(第56小節~)で主調の変イ長調へ至る。
推移のアルペジオ音型を伴って主要主題が再現され、後半が下属調へ移される。ホ長調での推移(第70小節~)を経て主調で副次主題が再現される。コーダでは推移のアルペジオがふたたびあらわれ、その余韻の中に楽章を閉じる。
第2楽章 4分の2拍子 ヘ短調
スケルツォ風で3部分形式による楽章。中間部は変ニ長調へ転じ、和音の動きが中心的な役割を果たす主部と対照的に、バスとソプラノの2声部書法が中心となっている。コーダにおけるピカルディ終止は、第3楽章冒頭へのドミナントの役割を果たしている。
第3楽章 序奏 4分の4拍子/フーガ 変イ長調 8分の6拍子
前楽章の終結和音がドミナントの役割を果たし、変ロ短調で開始されるAdagioの序奏は、レティタティーヴォにつづいて変イ短調の「嘆きの歌Klagender Gesang」となる。極めて声楽的な序奏に対し、主部のフーガは古い声楽様式ではなく、きわめて器楽的な様式による自由な3声フーガである。
中間部(第114小節~)で「嘆きの歌」がト短調で回帰し、これを挟んだ後半はト長調となって主題の反行形によってフーガが築かれる。間もなくト短調へ転じ、そこから徐々に対位法的な様式から離れ、主調の変イ長調へ戻ってフーガ主題の動機展開へと発展して楽曲を閉じる。
ピティナ&提携チャンネル動画(41件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(10件)
楽譜
楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)春秋社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ヘンレ社(ヤマハ)

ヘンレ社(ヤマハ)

Barenreiter

 ステップレベル:展開2,展開3
ステップレベル:展開2,展開3