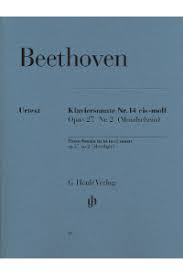ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第14番 「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.14 "Sonata quasi una fantasia"(Mondscheinsonate) cis-moll Op.27-2
作品概要
解説 (2)
執筆者 : 小崎 紘一
(965 文字)
更新日:2010年1月1日
[開く]
執筆者 : 小崎 紘一 (965 文字)
ベートーヴェンのピアノソナタの中でも、そのポピュラーな旋律によって広く親しまれている、1802年の作品。ベートーヴェンが書き記したのは「幻想曲風ソナタ」という部分であり、「月光」の呼び名は詩人ルードヴィヒ・レルシュターブにより寄せられたコメント(「ルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のよう」)から採られている。レルシュターブはシューベルトのリートを作詞していることなどで知られている。
第一楽章の厳かさ・精神性はそのロマンティシズムと相まって夜曲としてのイメージを想起させるかもしれないが、それだけでは説明のつかない諦観とでもいうべきトーンで覆われている。それが第三楽章で激しい昂ぶりをもって展開されるとき、この感情の噴出が極私的なものに起因している可能性が示唆される。嵐、稲妻、そういった人間が抗えない猛威の中で地を踏みしめるベートーヴェンの姿が見える。
作曲家が作品を生み出す経緯はさまざまである。献呈、憧憬、望郷、反体制、そして勿論人間関係。ベートーヴェンにとっても例外ではなく、この作品を捧げたジュリエッタ・グイッチャルディへの想いがこの作品を性格づけている。知人への手紙では「愛らしい、魅惑的な娘」と打ち明けることもあった彼女の存在は、彼の人生にとって非常に明るい契機となっていた。ただ、前述の手紙の中では身分の違いを理由にこの恋が成就しないであろうことも告白している。また、数ある書簡集の中でも、ベートーヴェンがグイッチャルディに宛てた手紙は見当たらない。ベートーヴェンが自らの心情を音に独白させたかのようなこのソナタは、月の光のような円やかな印象よりも、人生と決然として向き合う作曲家ベートーヴェン、そのあまり見ることのない背中を眺める思いがする。
当時のベートーヴェンは、ピアノソナタを始め弦楽四重奏曲など、従来のジャンルを咀嚼、研究しながら新たな作曲上の問題に取り組もうとする、ある意味で過渡期を潜っている。この作品に関しても幻想曲というタイトル通り、即興的な要素が持ち込まれたり、初めて意識的にペダル(当時は肘梃子)の使用(第一楽章)を細かく明記したりと、さまざまなアイデアを聴くことができる。この時期の諸作の数々は同年、ハイリゲンシュタットにて遺書を作成した後に踏み入れることになる傑作の森として芽吹くことになる。
解説 : 丸山 瑶子
(2776 文字)
更新日:2019年3月3日
[開く]
解説 : 丸山 瑶子 (2776 文字)
全体解説
1801年作曲。作曲家が同年春から秋に使った「ザウアー・スケッチ帳」に終楽章のスケッチが見られる。また第一楽章の数小節の楽想は、1793/94年に使用した「カフカ・スケッチ帳」に書かれたスケッチとの類似性も指摘されている。初版は1802年3月にヴィーン、ジョヴァンニ・カッピ社から刊行された。カッピ社が当初Op. 27, no. 1とno. 2に用いた表紙が共通であったため(最初、第1番、第2番の番号は手書きで付された)、多くの初期出版譜で両作品の番号付けが逆になるという事態が起こった。なお、初演記録は残っていない。
作品はユーリエ・グイッチャルディ伯爵令嬢に献呈された。彼女はベートーヴェンと親しかったブルンスヴィック家の親戚で、ベートーヴェンは好意から、ユーリエに無償でピアノを教えていた。彼女はベートーヴェンの方では相思相愛と思っていた相手であり、作曲家の秘書シンドラーのベートーヴェン伝では誤って「不滅の恋人」と目されていた。
自筆浄書譜はほぼ完全な形で残っているが、最初と最後のページが欠けてしまっている。したがって自筆譜に書かれたタイトル表記については不明である。しかし「幻想風ソナタ」という表記は初版以来のものであり、作曲家のオーセンティシティは疑い得ない。これはベートーヴェンがピアノ・ソナタの伝統的な型を破り、幻想曲のように自由な構想のソナタを書いたことの表明と解釈されている。一方、「月光」の通称は1830年代のL.レルシュタープの文学作品『テオドール。音楽的スケッチ』における第一楽章の詩的な性格づけに由来する。また19世紀のベートーヴェン研究者のヴィルヘルム・フォン・レンツ(1809~1883)によれば、作曲家が庭園で伯爵令嬢に即興演奏したという逸話から、ヴィーンでは「園亭のソナタ」という通称もあったとのことである。
なお、現在の出版譜では第3楽章にペダル記号が使われていることが多いが、本作品の作曲当時のヴィーンでは、まだペダル付きのピアノは一般的ではなかった。ベートーヴェンが好んだヴィーンのヴァルター製ピアノでも、変音装置は、膝でレバーを押し上げる「膝てこ」による操作だった。ベートーヴェンの自筆譜においても初版譜においても、本作品第3楽章はペダル記号ではなく「con sordino」「senza sordino」と言葉で指示されている。
各楽章解説
第1楽章 Adagio sostenuto 2/2拍子 cis-Moll
ピアノ・ソナタの冒頭楽章は急速楽章が一般的である。「幻想風」の表題に鑑みれば、独立した緩徐楽章を冒頭楽章に据えるのは、モーツァルトのK331といった前例があるとはいえ、作曲家が意図的に慣習に反した楽章選択と見做せる。楽章形式は旋律と和声に基づいて、前奏(第1-5小節)、A(第5-42小節)、B(第23-42小節)、A’(第42-60小節)、後奏(第60-69小節)と区分できる。全体は「月光」の由来である詩的解釈を誘うロマン派的な音楽言語に満ち(例えば、舟歌を想起させる一様な三連符、前奏と後奏を持つ歌唱的な旋律線など)、メンデルスゾーンの《無言歌集》に先んじる例と考えられている。
ピアノという楽器の発展や演奏に関しては変音装置の扱いが注目される。もしモダン・ピアノで、楽章冒頭の「この小品pezzo[楽章の概念は後世のものである]全体を極めて繊細にソルディーノ(消音装置)なしで演奏すること」という指示にしたがい、ダンパーを上げっぱなしで(つまり右ペダルを踏みっぱなしで)演奏したら、残響が醜い不協和音を生むのは必至である。しかし当時のフォルテ・ピアノは音の減衰が速く、指示通りに演奏すれば、むしろ得も言われぬ響きが生まれるだろう。また楽章を通して変音装置を使うのは、ペダルや膝てこ以前の、手動ストップで操作する変音装置の歴史を反映しているとも指摘されている。
第2楽章 Allegretto 3/4拍子 Des-Dur
複合三部形式。両端楽章のcis-Mollに対してエンハーモニックの関係にあるDes-Durを主調としたのは、第一楽章の楽章タイプと並んで、作曲家が慣習からの逸脱を図った調選択だろう。また楽章冒頭が主調主和音の基本形ではなく、第3音Fを低音とする第一転回形で始まる点にも、和声的工夫によって極度の単純さを避けようとする姿勢が窺える。
主部の冒頭主題はレガートとスタッカートという対照的なアーティキュレーションを持つ2小節の交替から成り、ここにはop. 26の第2楽章との類似が指摘されている。冒頭8小節は直後に変化反復されるが、ここでの旋律のシンコペーションがトリオ部の旋律構造と共通し、楽章全体の統一に寄与している。
トリオ部の冒頭と末尾は属音ないし主音の保続低音によってパストラル風の性格が与えられている。これによる主和音の和声的安定は、主和音の第一転回形から始まる主部とのバランスをとる措置と考えられる。初めて保続低音が無くなる反復記号後は、右手も順次進行を含まぬ五度ないし四度の跳躍音形が連続し、前後の部分と対照を成す。
第3楽章 Presto agitato 4/4拍子 cis-Moll
ソナタ形式。非旋律的な分散和音(Aとする)の忙しない動きと、次第に間隔を狭めるsfと和声変化によって、楽章冒頭から音楽は急速に高揚する。ドミナントの保続音の後、第11小節から移行部に入る。第21小節からAとは対照的な旋律的主題(Bとする)が属調gis-Mollで現れる。しかし副主題に期待される調の安定性は低く、すぐに低音が半音階的に下行してgis-Mollから離れていく。gis-Mollが再び明確かつ安定的になる第43小節からは、楽章冒頭以降ほぼ途切れなかった16分音符が消えて8分音符が基準のリズムになると同時に、テクスチュアもそれまでと対照的なホモフォニックな和音の連続に変わる。小結尾(第57小節~)はBに基づく。
短い展開部では、主題A、Bが提示部と同じ順番で現れたのち、第21小節の旋律から派生した動機が楽章主調のドミナントgisの保続音上で変奏され、再現部が和声的に準備される。再現部は移行部の省略により主題Bの主調再現が簡潔に準備されている。
コーダ(第159小節〜)の構成は主題A、Bが提示部と同じ順で現れる点などで展開部と対応するが、既出主題の間には前触れもなく即興的パッセージが挿入される。ここに表題の「幻想曲風」の特徴を指摘できるだろう。急速なパッセージがスピードを減じ、展開部末尾(第100〜101小節、コーダ第188〜189小節)と対応する低音の二度上行(コーダでは半音上行)でドミナントに達すると、主和音への解決とともに再び小結尾の楽想が現れる。
楽章等 (3)
編曲・関連曲(1) <表示する>
Piano Duo piaNA(佐久間あすか・西本夏生): 月光ソナタ・ラテンバージョン
総演奏時間:2分20秒
ピティナ&提携チャンネル動画(49件) 続きをみる
参考動画&オーディション入選(13件)
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (83)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)春秋社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)リットーミュージック

(株)音楽之友社
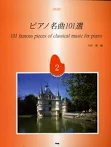
KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

(株)学研プラス

ミュージックランド

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)タイムリーミュージック

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

ミュージックランド

デプロMP

(株)全音楽譜出版社

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)自由現代社

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド
![ビギナーのためのピアノ/名曲シリーズ1 [ピアノソロ] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/1852.jpg)
ハンナ(ショパン)

(株)音楽之友社

ヘンレ社(ヤマハ)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)共同音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Barenreiter

Musikverlag Doblinger

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

 ステップレベル:発展1,発展2,発展3,発展4,発展5
ステップレベル:発展1,発展2,発展3,発展4,発展5
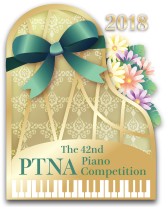 コンペ課題曲:F級
コンペ課題曲:F級