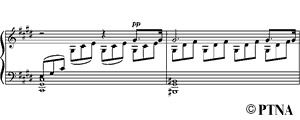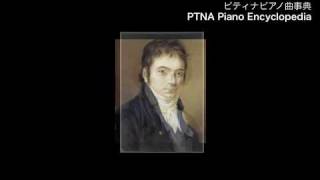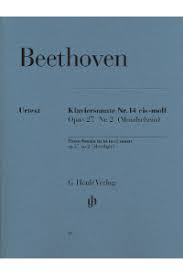ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第14番 「月光」 第1楽章 Op.27-2
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.14 "Sonata quasi una fantasia"(Mondscheinsonate) 1.Satz Adagio sostenuto
作品概要
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:6分30秒
著作権:パブリック・ドメイン
ピティナ・ピアノステップ
23ステップ:発展1 発展2 発展3 発展4 発展5
楽譜情報:40件解説 (2)
解説 : 丸山 瑶子
(618 文字)
更新日:2019年3月5日
[開く]
解説 : 丸山 瑶子 (618 文字)
第1楽章 Adagio sostenuto 2/2拍子 cis-Moll
ピアノ・ソナタの冒頭楽章は急速楽章が一般的である。「幻想風」の表題に鑑みれば、独立した緩徐楽章を冒頭楽章に据えるのは、モーツァルトのK331といった前例があるとはいえ、作曲家が意図的に慣習に反した楽章選択と見做せる。楽章形式は旋律と和声に基づいて、前奏(第1-5小節)、A(第5-42小節)、B(第23-42小節)、A’(第42-60小節)、後奏(第60-69小節)と区分できる。全体は「月光」の由来である詩的解釈を誘うロマン派的な音楽言語に満ち(例えば、舟歌を想起させる一様な三連符、前奏と後奏を持つ歌唱的な旋律線など)、メンデルスゾーンの《無言歌集》に先んじる例と考えられている。
ピアノという楽器の発展や演奏に関しては変音装置の扱いが注目される。もしモダン・ピアノで、楽章冒頭の「この小品pezzo[楽章の概念は後世のものである]全体を極めて繊細にソルディーノ(消音装置)なしで演奏すること」という指示にしたがい、ダンパーを上げっぱなしで(つまり右ペダルを踏みっぱなしで)演奏したら、残響が醜い不協和音を生むのは必至である。しかし当時のフォルテ・ピアノは音の減衰が速く、指示通りに演奏すれば、むしろ得も言われぬ響きが生まれるだろう。また楽章を通して変音装置を使うのは、ペダルや膝てこ以前の、手動ストップで操作する変音装置の歴史を反映しているとも指摘されている。
演奏のヒント : 大井 和郎
(1491 文字)
更新日:2019年12月20日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (1491 文字)
多くの課題が要求される第1楽章です。この楽章で人を惹きつけるにはどうしたら良いでしょうか?
テンポ
まず、テンポからお話しします。この1楽章は4拍子ではありません。2拍子です。ですから2拍子を感じて演奏しなければならないのですが、多くの失敗例としては、この楽章をゆっくり弾きすぎてしまい、その結果多くの問題が発生してしまいます。Adagio Sosutenuto で2拍子です。では一体どのくらいのテンポで弾けば良いのでしょうか?ここからは筆者の考えや好みになります。
次に説明する「流れ」の問題で、4分音符=65位で演奏すれば、速すぎず、かつ流れを失わずして済みます。
ベートーヴェンの設定したAdagioというテンポ設定は、メトロノームを頼りにしているものではないことが証明できます。それは3楽章の188ー189小節間に付けられているAdagioのマーキングです。こちらの場合はさらに、4/4拍子ですから、4拍数えなければなりません。もしも、1楽章で設定したテンポがAdagioで、この場合、1小節2拍分のクリックになりますから、それを基に、これら3楽章の188ー189小節間を1小節4クリックで弾いてみると、如何にナンセンスであるかが解りますね。1楽章のAdagioと3楽章のAdagioでは全くテンポが異なることがわかります。
察するに、ベートーヴェンは、Adagioのマーキングを、単純に、「特に遅く」 という意味で書いていることがわかりますね。
流れ
筆者はこの楽章の最大に重要なポイントはこの「流れ」であると思っています。それは3連符を絶対に止(と)めない事に尽きます。この楽章の最後の2小節を除き、殆どの小節は1拍分以上の休符もなく、3連符で埋め尽くされています。最後の2小節を除き、実際に休符が書かれているのは。5小節目、9ー10小節間、29小節目、31小節目、66小節目の5カ所しかありません。そしてこれらの休符は、ほぼ、右手のメロディーラインの為の休符であります。
故に、3連符を止(と)めない事が大事なのですが、典型的な例として3連符が止まってしまう箇所があります。それは5小節目以降に書かれている、付点8分+16分 のリズムの部分です。このリズムが来ようが、3連符は絶対にタイミングを狂わしてはいけません。この箇所で、付点のリズムに惑わされ、必要以上に時間を取ってしまう学習者が多くいます。
32小節目以降、35ー36小節間をピークに、音楽はテンションを上げていきます。そして、41小節目までで一区切りとなりますが、この間も基本的に3連符を止めてはいけません。強いて言えば、35ー36小節間の最高音を弾くときに、若干、テンポを引っ張る程度です。
強弱
全体に、弱音器を付けたように という指示があるように、ppが基本的なダイナミックの楽章になります。この楽章ではpマーキングが最も大きい音量を示すマーキングになります。しかしながら、全く平坦な音楽になってはなりません。pやppの範囲内でコントロールをします。35ー36小節間もダイナミックマーキングは書かれておりませんが、筆者であれば、35ー36小節間は、mf辺りまでは持って行きたいところです。
バランス
メロディーラインと3連符がほぼ同じ音量、同じ音質で演奏する奏者は後を絶ちません。メロディーラインと3連符はハッキリと区別を付けます。一度メロディーラインのみ単旋律で弾いてみましょう。このようにゆっくりな曲になると、メロディーラインが把握出来ていない事も発生します。単旋律で弾いてみるときは、多少速いテンポで弾いてみましょう。
編曲・関連曲(1)
中谷 幹人: ピアノ・ソナタ 第14番「月光」第1楽章(原曲:ベートーヴェン)
 ステップレベル:応用6,応用7,発展1,発展2
ステップレベル:応用6,応用7,発展1,発展2
ピティナ&提携チャンネル動画(18件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (40)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)リットーミュージック

(株)音楽之友社
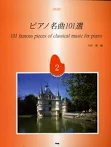
KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)リットーミュージック

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)リットーミュージック

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

(株)リットーミュージック

ハンナ(ショパン)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

ミュージックランド

ヘンレ社(ヤマハ)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)共同音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス