ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.1 f-moll Op.2-1
作品概要
解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(1997 文字)
更新日:2009年1月1日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (1997 文字)
ベートーヴェンはボン時代にネーフェに師事した成果として、既に《3つの選帝侯ソナタ》WoO.47を作曲、出版していたが、作品番号(Opus-Zahl)づけがなされる本格的なソナタの創作に着手したのは1792年にヴィーンでハイドンに師事するようになってからのことである。1793年にハイドンがイギリスへの演奏旅行に出発すると、ベートーヴェンはおそらくボン時代から暖めていたであろう作品の創作に着手する。このソナタもそうしたものの1つで、第2楽章の主題が《ピアノ四重奏曲》WoO.36-3における第2楽章の主題から転用されている。
全4楽章からなり、全楽章がヘ調に統一された構成はバロックの組曲の名残りを感じさせる。またヘ短調という調性の選択は、当時としては異例である。というのも、この時代におそらく用いられていたであろう「テンペラメント」という調律方法(現在の平均律とは異なる)では、調号が4つ以上の調性では響きの濁りが強くなるため、中間楽章の調性としては用いられても、主要楽章の調性としては用いないのが一般的であった。こうした点にも、ベートーヴェンの独創性の一端を垣間見ることができる。
(第1楽章)ヘ短調 2分の2拍子 ソナタ形式
明瞭なアレグロ・ソナタ形式であるが、主題の調性選択に既に後年のベートーヴェンを予感させる試みがみてとれる。提示部と展開部+再現部がそれぞれ反復されるハイドンやモーツァルトのソナタによくみられる、古典的なソナタ形式である。
[提示部]
マンハイム・ジャンプと呼ばれる上行する主和音のアルペッジョと、下降する装飾的な音型、そして1拍目に休符を置くことで拍節感のズレを生み出す和音の刻みによって特徴づけられる主要主題に対し、属音上でなだらかに下降する副次主題は変イ長調である。主調のヘ短調に対し、変イ長調は短3度の関係にあり、一般的な近親調関係では平行調にあたる。
この後、主要主題の分散和音要素と副次主題の下降音型の要素をバス声部とソプラノ声部に共有するもう1つの副次主題が変イ長調であらわれた後、主要主題の変形によるコデッタが置かれ、変イ長調に終止する。
[展開部+再現部]
展開部ではまず主要主題の要素が変イ長調であらわれ、増6の和音を介して変ロ短調へ転調する。下降する副次主題がゼクエンツ風に繰り返され、変ロ短調からハ短調を経由し、変イ長調に転調すると、提示部にはみられなかった楽想が経過的に挿入される。
やがてヘ短調の属音上に主要主題の装飾音型が断片的にあらわれ、再現部を準備する。
装飾音型に導かれて主要主題が再現するが、ここでは冒頭で提示された際と特徴的だった拍節のズレが修正されている。副次主題は共に主調のヘ短調で再現さる。
(第2楽章)ヘ長調 4分の3拍子
アダージョの緩叙楽章。付点八分音符+十六分音符のアウフタクトと6度(または3度)のオブリガートをともなう順次下降の主題が変奏されながら繰り返される。
主調(ヘ長調)から平行調のニ短調、属調のハ長調をめぐり、ヘ長調へ回帰し、じょじょにターンによる装飾と短い音価による装飾が多用されてゆく変奏技法はモーツァルトを彷彿とさせる。
(第3楽章)4分の3拍子 メヌエット:ヘ短調-トリオ:ヘ長調
トリオとダ・カーポを有する典型的なメヌエットだが、調性は第1楽章と同じヘ短調である。6度(および3度)の響きを基調とする仄暗い音響と、ユニゾンによる強奏が対比的に置かれている。
トリオは同主調のヘ長調に転調し、2声および3声の幾分自由な転回可能対位法を用いた楽想が反復される。
(第4楽章)ヘ短調 2分の2拍子 ロンド・ソナタ形式
プレスティッシモのフィナーレは、前半(提示部)と後半(展開部+再現部)がそれぞれ反復されるロンド・ソナタ形式(A-B-A-B-C-A-B-C-A-B)。
[提示部]
三連音符の分散和音上に和音が刻み付けられる主要主題によって開始される。主要主題はこのp(ピアノ)とf(フォルテ)の対比によって特徴付けられる和音動機と、これとは対照的な同音反復と4度跳躍を特徴にもつ3声部書法による動機からなっている。
副次主題は属調のハ短調で提示される。このオクターヴ順次下降する副次主題でも三連音符の分散和音が背景となっている。コーダは主要主題の上下(三連音符の伴奏と和音動機の配置)が転回された形で形成される。
[展開部+再現部]
展開部はまず変イ長調で新たな主題が提示される。1拍目に休符を置く和音の刻みによる伴奏形は第1楽章の主要主題に通じている。この主題がオクターヴ化されるなどして繰り返されたのち、主要主題の三連音符をともなった和音動機が断片的にあらわれ、これに導かれるように再現部に至る。このブリッジ手法も第1楽章と通じているとみてよいだろう。
副次主題も主調のヘ短調で再現され、コーダも同様にヘ短調で簡潔にしめくくられる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(942 文字)
更新日:2025年10月9日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (942 文字)
この作品は、まだベートヴェンが本領を発揮せず、ハイドンの影響を受けている作品ですが、ベートーヴェンらしさは十分に感じる事が出来る作品となっています。このソナタ第1楽章を弾くコツとしては、全てを「弦楽4重奏」に置き換えて考える事です。ところがそれが全く頭の中に無い学習者が演奏をすると、すぐに、弦楽アンサンブルをベースにしていない弾き方であることが明白に判ります。
例えば11〜14小節間。ト音記号を第1第2ヴァイオリン、ヘ音記号をビオラとチェロで演奏すると仮定したとき、ヘ音記号部は音が弦によって切れ目無く伸ばされ、かつ、アタックが全く無いことがわかります。故に、それを真似てピアノで弾くようにします。そうすると、ト音記号部分も含め、全音符に対してアクセントを付けるような行為は無くなるはずです。12小節目は、第1ヴァイオリンのDesを聴き続けて13小節目に入るようにします。そうすると、Desを延ばすためには、第2ヴァイオリンは決して大きすぎない方がDesを邪魔しない事がわかります。縦に考えず、1声1声、横に考えます。全てこのように考えます。
15〜20小節間も同じです。特に気をつけたいのが、18〜19小節間の右手のオクターブ進行で、これはペダルで切れ目無くつなぎ、しかし左手の和音も濁らずにという細かい配慮が必要になります。
そして、とても誤解されているマーキングがスフォルツアンドというマーキングです。これは「その音だけ特に強く」と学んでいる人が大変多くいます。実際には、「その強弱の範囲内で少しアクセント」が正しい理解の仕方です。つまりは、フォルテのセクションにスフォルツアンドが書いてあればかなり大きいのですが、pのセクションにスフォルツアンドが書いてあったときはほんの少しだけアクセントを付けるという解釈で理解して下さい。
故に、22小節目、24小節目などのスフォルツアンドは、少しだけアクセントと考えます。
いずれにせよ、全てを弦楽4重奏として考えてみて下さい。それをイメージして、真似てみて下さい。
楽章等 (4)
編曲・関連曲(1) <表示する>
中谷 幹人: ピアノ・ソナタ 第1番(原曲:ベートーヴェン)
 ステップレベル:応用6,応用7,発展1,発展2
ステップレベル:応用6,応用7,発展1,発展2
ピティナ&提携チャンネル動画(16件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (12)

(株)全音楽譜出版社

(株)春秋社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレ社(ヤマハ)

(株)音楽之友社

Barenreiter

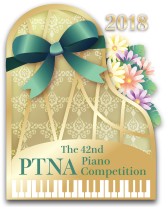 コンペ課題曲:E級
コンペ課題曲:E級 



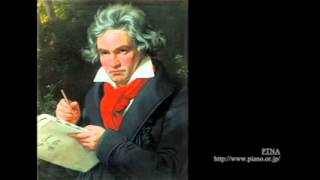


![ベートーヴェン・ピアノ作品集1 ソナタ集[歴史的注解付批判校訂版] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/391.jpg)



