作品概要
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:曲集・小品集
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (1)
演奏のヒント : 大井 和郎
(1150 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (1150 文字)
初めての舞踏会
この曲を演奏するにあたり注意点はいくつかあるのですが、まずは分析してみましょう。曲は3部形式で、ABAになります。 A 1-16小節間 B 17-24小節間 A 25-32小節間 となります。最初のAから見て行きましょう。1-8小節間、9-16小節間にきれいに分かれます。この曲の長はD-durですが、どちらもドミナントで終わっていることに注目します。メロディー音は1小節目、右手のE、3小節目、右手のD、5小節目、右手のCisと順次進行で下行し、7小節目2拍目の右手Aに達します。そして9-16小節間もメロディーに関しては全く同じ事が繰り返されます。
筆者がかなり悩んだのは保続音のAです。1小節目、3小節目、5小節目、6小節目、にそれぞれAが出てきますね。本来であればこれは、例えばリストのラ・カンパネラのような保続音に過ぎず、メロディーでは無いと考えます。ところがこの楽譜はメロディーラインと同じ声部に保続音が書かれてあり、これをメロディーと考えるのかどうかかなり悩み、未だに答えは出ていませんが、筆者であればこの一連のAをそこまで強調することは無いと思います。即ち:Fis G E A A A とメロディーを考えるよりは、Fis G E と考えた方が理に適うような気がします。
ここが議論を呼ぶところです。そして更に厄介なことが8小節目と16小節目に起こります。各小節の1拍目に書かれてある2分音符のAは、どうしてもメロディーラインと考えなければおかしな事になってしまいます。それは前の小節3拍目のEがメロディーと考えた時、このEでぷっつりとメロディーが切れてしまうのは大変不自然だからです。もっと飛躍して考え、メロディーは7小節目と15小節目の2拍目のAで終わっていると考える事もできますね。そのほうが理に適うような気もします。その場合、故に、次のEと次の小節1拍目のAはレゾネンス(余韻)と考えます。
メロディーラインとレゾネンス、保続音がクリアーに分かれて書かれておりませんのでとても解りづらいですが、分析は個々の判断に委ねても良いと思います。
さて前半Aの部分ですが、一見1-8小節間と9-16小節間は同じに見えますが、決定的な違いは13-14小節間の左手です。1-8小節間はD-dur、9-16小節間はA-durに転調しています。テンション的には後半の方が高いと感じ、前半の方は穏やかに感じられますね。
中間部、いきなりF-durに転調します。18小節目をピークにして徐々に下行していきます。同じことを21小節目から始まり24小節目のフェルマータで中間部を終えます。
再現部(25-32小節間)で、29-30小節間は今までに出てこなかった高いピッチになります。少し音量を上げます。
ピティナ&提携チャンネル動画(24件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (15)

(株)全音楽譜出版社
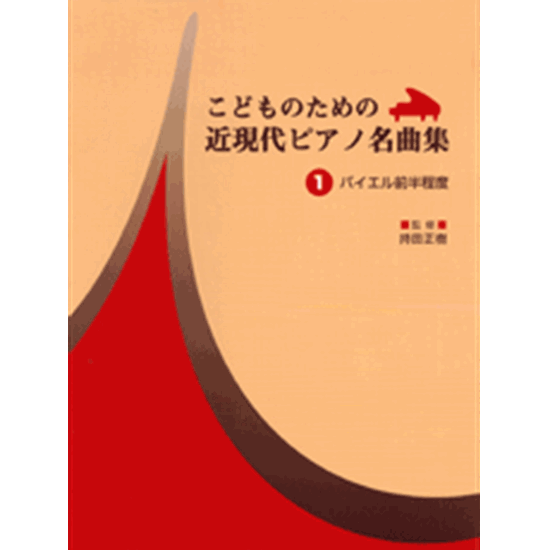
(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)学研プラス

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)レッスンの友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

 ステップレベル:応用2
ステップレベル:応用2


















