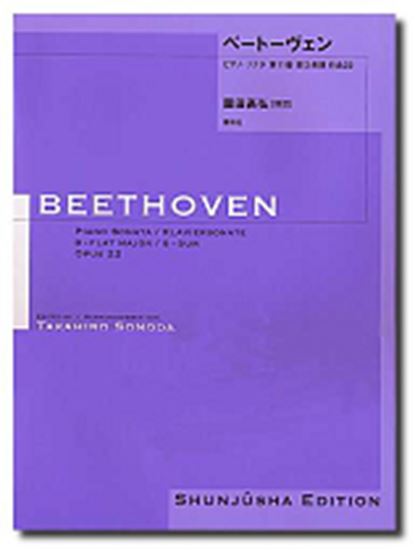ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第11番 変ロ長調 Op.22
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.11 B-Dur Op.22
作品概要
解説 (1)
執筆者 : 岡田 安樹浩
(1323 文字)
更新日:2009年2月1日
[開く]
執筆者 : 岡田 安樹浩 (1323 文字)
1800年に完成されたこのソナタは、1799年に着手されていたと考えられてきたが、近年では着手も1800年になってからだと考えられている。
さまざまな実験を試みながらも、伝統的な「ソナタ」の枠組みをまもって作曲してきたベートーヴェンが、その枠組みを破る前の最後の作品である。次作のOp.26では、ソナタ形式楽章そのものを排除するという新たな一歩を踏み出している。
(第1楽章)変ロ長調 4分の4拍子 ソナタ形式
[提示部]
主要主題はスタッカートで上行してゆく軽快な性格の動機と、レガートで順次下降する動機からなる。バスの刻みと和音のトレモロ、上声部の跳躍するレガートの3度重音と低声部の音階や2度の反復音型など、弦楽合奏からのリダクションを思わせるような推移を経て、ヘ長調で副次主題があらわれる(第31小節~)。
副次主題は2オクターヴでの3度重音によっており、第3拍目にアクセントが置かれている。分散和音パッセージやオクターヴ・トレモロ奏法による経過句を経て、コデッタでは決然とした4オクターヴ・ユニゾンでの順次上下降のあとに主要主題の動機が一瞬顔を出す。
[展開部+再現部]
主要主題の動機とコデッタにおけるユニゾン動機が交互にあらわれながら発展する。主要主題の動機は分散和音へと溶解し、コデッタのユニゾン動機から発展したと思われる音階パッセージによって再現部へ移行する。
再現部は主要主題、副次主題ともに主調(変ロ長調)であらわれ、コーダも拡大されることなくストレートに楽章を閉じる。
(第2楽章)変ホ長調 8分の9拍子
和音の刻みの上に装飾的パッセージが展開されるAdagioの緩叙楽章。変ホ長調の主題と属調の変ロ長調による2つの主題をもつ。
中間部(第31小節~)では最初の主題を構成する動機が展開され、後半部分(第47小節~)では、両主題が主調である変ホ長調で再現される。
この調性プランと構成法は極めてソナタ形式に近く、緩叙楽章にソナタ形式を持ち込む試みが行われていることが伺える。
(第3楽章)変ロ長調-ト短調 4分の3拍子 メヌエット
舞踏形式による楽章だが、この作品ではスケルツォではなくメヌエットを置いている。メヌエット主部は付点リズムと前打音つきの装飾的な音型によって構成されており、トリオの中間部は「短調Minore」と記されており、平行調のト短調へ転調する。絶え間なく動き回る16分音符の音型と第2拍目に強勢を置いた和音動機によっている。
(第4楽章)変ロ長調 4分の2拍子 ロンド
軽快に動き回るロンド主題は、内声に属音(ヘ音)が絶えず保持されている。アルペジオの経過句を経て、オクターヴのシンコペーション主題が変ロ長調であらわれる(第25小節~)。アルペジオの経過楽想の後にロンド主題の動機が反復され、ロンド主題が回帰する(第50小節~)。
これに続く部分は、ロンド形式では通常新たな主題が提示されるが、ここでは素材の発展、展開にあてられている(第68小節~)。ロンド主題の再現(第120小節~)においてもかなりの変奏技法が盛り込まれており、属調主題の再現の後もう一度ロンド主題があらわれ、さらに動機を発展的にあつかったコーダで楽曲を閉じている。
楽章等 (4)
ピティナ&提携チャンネル動画(10件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (12)

(株)春秋社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ヘンレ社(ヤマハ)

(株)音楽之友社

Barenreiter

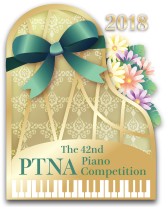 コンペ課題曲:E級
コンペ課題曲:E級  ステップレベル:発展4,発展5,展開1,展開2,展開3
ステップレベル:発展4,発展5,展開1,展開2,展開3






![ベートーヴェン・ピアノ作品集2 ソナタ集[歴史的注解付批判校訂版] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/127.jpg)