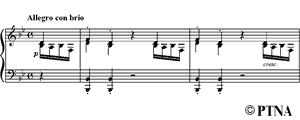ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第11番 第1楽章 Op.22
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.11 1.Satz Allegro con brio
作品概要
解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(458 文字)
更新日:2019年2月16日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (458 文字)
(第1楽章)変ロ長調 4分の4拍子 ソナタ形式
[提示部]
主要主題はスタッカートで上行してゆく軽快な性格の動機と、レガートで順次下降する動機からなる。バスの刻みと和音のトレモロ、上声部の跳躍するレガートの3度重音と低声部の音階や2度の反復音型など、弦楽合奏からのリダクションを思わせるような推移を経て、ヘ長調で副次主題があらわれる(第31小節~)。
副次主題は2オクターヴでの3度重音によっており、第3拍目にアクセントが置かれている。分散和音パッセージやオクターヴ・トレモロ奏法による経過句を経て、コデッタでは決然とした4オクターヴ・ユニゾンでの順次上下降のあとに主要主題の動機が一瞬顔を出す。
[展開部+再現部]
主要主題の動機とコデッタにおけるユニゾン動機が交互にあらわれながら発展する。主要主題の動機は分散和音へと溶解し、コデッタのユニゾン動機から発展したと思われる音階パッセージによって再現部へ移行する。
再現部は主要主題、副次主題ともに主調(変ロ長調)であらわれ、コーダも拡大されることなくストレートに楽章を閉じる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(694 文字)
更新日:2025年10月9日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (694 文字)
この第1楽章はかなり有名な曲に入ると思いますが、一般的に犯しがちなミスを述べます。この第1楽章も、やはり、弦楽4重奏を意識する部分が多々あり、そのような箇所では、弦楽4重奏を真似て演奏されて然るべきです。例えば、14〜15小節間、30〜43小節間、143〜146小節間等です。その他、左手がバスを保ち(オルガンポイント、ペダルポイントと呼ばれる技法)56〜61小節間等です。こういう部分は弦楽器を意識し、声部の独立を目指して下さい。
その他ポリフォニーの話になりますが、27〜30小節間の右手が、聴衆に、Fis A C Fis B G Des C A G E F と聞こえてしまってはおしまいです。フォルテと書いてあろうが、内声はppにすることで声部の独立ができますので、結果、Fis A C B—- A G E F と聞こえるように弾いて下さい。
次に、30小節目2拍目から始まる4声体の進行。これは先ほど述べたように、弦楽4重奏を同意できるのであれば、楽譜に書いてあるアーティキュレーションを守って下さい。つまりは、30小節目3拍目からフレーズは始まり、31小節目2拍目までで一区切りです。ここで一度切らなければなりません。その上で、31小節目4拍目から32小節目2拍目までで一区切り、ここで一度切り、次を始めます。これはヴァイオリンのボーイングと考えます。決してこれらを全部繋いでしまわないようにしてください。
編曲・関連曲(1)
鈴木 光介: 《Even Be Hot ホットこともありえます》 第7曲 ホットこともありえます
総演奏時間:1分30秒
ピティナ&提携チャンネル動画(3件)
楽譜
楽譜一覧 (2)

(株)全音楽譜出版社

ヘンレ社(ヤマハ)