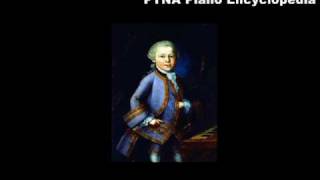モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第10番 ハ長調 K.330 K6.300h
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.10 C-Dur K.330 K6.300h
作品概要
解説 (1)
執筆者 : 岡田 安樹浩
(1057 文字)
更新日:2009年11月1日
[開く]
執筆者 : 岡田 安樹浩 (1057 文字)
旧来このソナタは、続く2つのソナタ(イ長調 K.331、ヘ長調K. 332)とともに、パリで作曲されたと考えられてきた。しかし、近年の研究成果(ヴォルフガング・プラートやアラン・タイソンらによる自筆譜の研究)によって1783年にウィーン、またはザルツブルクで作曲されたことが明らかとなった。
現在クラクフの図書館に保存されている自筆譜は、第2楽章の第60小節の後半から64小節までが欠落している。その他、多くの箇所で、初版のアルタリア版(1784年ウィーン)強弱記号や奏法記号に差異が認められるため、新モーツァルト全集では自筆譜を底本に、アルタリア版から多くを採用している。
第1楽章 4分の4拍子 ハ長調 ソナタ形式
32分音符による音階と装飾音型、16分音符の分散和音を素材とする主要主題で開始される。装飾的なパッセージによる移行部(第19小節~)を経て、第34小節より属調で副次主題があらわれる。主要主題と副次主題双方の素材からなるコーダ(第54小節~)によって、ト長調で前半を閉じる。
後半部分(第59小節~)は、まずト長調からイ短調へ転じ、再びト長調を経由して主要主題の主調再現(第88小節~)を迎える。移行部の変形(第109小節)によって、属調ではなく主調にて副次主題を再現(第121小節~)する。
第141小節からのコーダは、前半の終結部分に後半部分冒頭の移行楽想が回帰して楽章を閉じる。
第2楽章 ヘ長調
前半8小節、後半12小節がそれぞれ反復記号によって繰り返される主題には、第1楽章の主題を想起させる素材が盛り込まれている。中間部(第21小節~)では同主短調のヘ短調へ転じる。6度および3度の重音や16分音符による保続バスを特徴とした主題の変奏が行われ、再びヘ長調で主題が再現(第41小節~)されると、コーダ(第61小節~)では中間部分の変奏が主調で回帰する。
第3楽章 ハ長調 ソナタ形式
8分音符を基調とした軽快な主要主題は、16分音符の分散和音伴奏による確保を経て、16部3連音符のパッセージへと発展する。移行部(第21小節~)の後、副次主題(第33小節~)があらわれる。
後半部分(第69小節~)の冒頭を開始する動機は、おそらく副次主題後半部分の同音連打の音型(第59小節)の拡大形であろう。こうした何気ない部分の素材を発展させる点は、モーツァルト独特のものといえるかもしれない。すぐに主要主題の主調再現(第96小節~)をむかえ、副次主題の主調再現(第132小節~)を経てコーダ(第160小節~)へと至る。
楽章等 (3)
ピティナ&提携チャンネル動画(24件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (15)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)音楽之友社

(株)共同音楽出版社

Musikverlag Doblinger

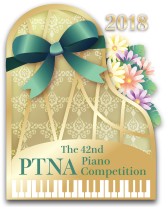 コンペ課題曲:E級
コンペ課題曲:E級  ステップレベル:発展1,発展2,発展3,発展4,発展5,展開1,展開2,展開3
ステップレベル:発展1,発展2,発展3,発展4,発展5,展開1,展開2,展開3