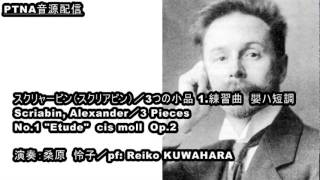作品概要
楽曲ID:
2552
作曲年:1887年 楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:曲集・小品集
総演奏時間:5分20秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (1)
執筆者 : 伊藤 翠
(665 文字)
更新日:2013年11月15日
[開く]
執筆者 : 伊藤 翠 (665 文字)
更新日:2013年11月15日
[開く]
スクリャービンの作品としては 1883 年( 11 才)時のカノン、12 才時のノクターンが最初期のものであり、1886 年 14 才の時点では《幻想ソナタ 嬰ト短調》(作品番号なし)、翌年 から 1889 年にかけては《ピアノソナタ 変ホ長調》(作品番号なし)といった大規模な作品にも着手した。これら二作品とほぼ同時期に作られたのが、《3つの小品》(op. 2)である。
少年時代からショパンやリストを敬愛していたと伝えられ、この頃のピアノ作品における旋律の発想や書法には、両者から大きな影響がみられる。とりわけショパンの影響は大きく、作風のみならず練習曲や前奏曲、マズルカといったジャンル選択からも察せられる。
《練習曲》op. 2-1
1887年、14歳の頃の作曲。この小品集の中で最も有名であり、今日でも演奏される機会の多い作品である。「練習曲」という題名に注目するならば、ホモフォニックな伴奏形と旋律部分の弾き分けを目指した曲であるといえる。冒頭2小節の主題が何度も、ショパン作品を思い起こさせるような転調で繰り返される。
《前奏曲》 op.2-2
《練習曲》と同じく1887年の作品である。1分程度の小曲。ショパン《前奏曲》の構成に則って冒頭2小節の主題による繰り返しとなっている。楽譜の表記は3/4拍子であるが、音楽は9/8拍子のように聴こえる。
《マズルカ風即興曲》op. 2-3
前曲の《練習曲》《即興曲》とは構成が異なり、マズルカ風のテーマを主題としたロンド形式の作品。そうした形式の選択もショパン作品において特徴的である。
執筆者:
伊藤 翠
ピティナ&提携チャンネル動画(7件)
楽譜
楽譜一覧 (5)

スクリアビン ピアノ曲集1 エチュード集(全曲) SCRIABIN
(株)全音楽譜出版社
(株)全音楽譜出版社

2ページで弾ける クラシックピアノ小品集3
ハンナ(ショパン)
ハンナ(ショパン)

スクリアビン ピアノ曲集1 エチュード集(全曲)
(株)全音楽譜出版社
(株)全音楽譜出版社

ピアノのための ロマン後期・近代・現代の名曲集 1
(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

【ミュッセ】前奏曲 Op.2-2
Neil A. Kjos Music Company
Neil A. Kjos Music Company