ハイドン : ソナタ 第62番 変ホ長調 Hob.XVI:52 op.82
Haydn, Franz Joseph : Sonate für Klavier Nr.62 Es-Dur Hob.XVI:52 op.82
作品概要
解説 (1)
執筆者 : 齊藤 紀子
(838 文字)
更新日:2007年8月1日
[開く]
執筆者 : 齊藤 紀子 (838 文字)
ハイドンのピアノ・ソナタの中で最後期に書かれた作品(1794年作曲、1798年出版)。華やかさ、盛り上がりに富んだ充実した一曲になっている。長年仕えたエステルハージ家を離れた後の、大成功したロンドン訪問など、傑作が多く生まれた時期である。主題がはっきりと位置づけられた明確な形式をもち、華々しさ、落ち着いた繊細さなど、楽章ごとに異なる表情をみせる。
伯爵、公爵に仕えることの多かったハイドンが、エステルハージ家の楽団解散により自由な音楽家となってから、1794年に作曲された。全3楽章から成る。
第1楽章はアレグロの4分の4拍子で変ホ長調。fの主和音の密集配置で開始する。ディナーミクが楽章全体を通して目まぐるしく変化することが特徴的である。第27小節からは、高音域に第2主題が現れ、展開部(44小節~)ではまずこの主題が展開される。第2主題は左右のスタッカートが特徴的で、スラーの付された第1主題と対照を成す。また、展開部の開始2小節は、この楽章の冒頭から引き出されているが、フェルマータが付されている。このようなフェルマータの扱いは、ハイドンの弟子のベートーヴェンのピアノ・ソナタに引き継がれていると言えるであろう。
第2楽章はアダージョの4分の3拍子でホ長調。第1楽章の半音高い調で書かれていることは興味深い。3部形式となっており、中間部(第19小節~)では同主短調のホ短調で書かれている。そして、この中間部の中間にはト長調も顔を出す。所々に、装飾音の手法で書かれた上行する音階が見られることが特徴的である。
第3楽章はプレストの4分の3拍子。第1楽章と同じ変ホ長調で、ロンド形式で書かれている。これまでの2つの楽章が和音で開始したのに対し、この楽章は主和音の第3音の単音を5回反復して開始する。また、随所にフェルマータによる一時停止が見られる。更に、この楽章では、クレッシェンド及びディミヌエンドが一度も記されておらず、その過程を経ないディナーミクの変化、対比が特徴的である。
楽章等 (3)
ピティナ&提携チャンネル動画(25件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (11)
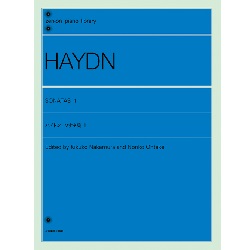
(株)全音楽譜出版社

ヘンレー

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

ヘンレー

ヘンレー

ヘンレー

ヘンレ社(ヤマハ)

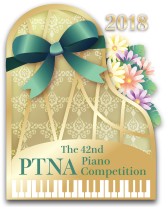 コンペ課題曲:F級
コンペ課題曲:F級  ステップレベル:発展5,展開1,展開2,展開3
ステップレベル:発展5,展開1,展開2,展開3















