作品概要
解説 (4)
総説 : 井澤 友香理
(585 文字)
更新日:2014年3月19日
[開く]
総説 : 井澤 友香理 (585 文字)
全12曲から成るピアノ小品集。1880 年代半ばに作曲を師事していたフェリペ・ペドレルの影響を受け、スペイン民族主義を意識して作曲された最初期の作品である。グラナドスはこの作品集の一部 (第 1 集、 第 1~3 番のみ) をバルセロナにて行った自身初の公開演奏会で披露し、ピアニストとしてだけでなく、作曲家としての名声も高めた。特に同時代のフランスの作曲家ジュール・マスネは、この作品の楽譜のコピーをグラナドスから受け取った際、作曲家グラナドスを「スペインのグリーグ」と呼び、称賛した。
グラナドスの作品の中ではこんにちよく知られており、特に第 5 番〈アンダルーサ〉は演奏機会が多い。管弦楽、ギターなど様々な編曲もされている。
1 曲ずつにタイトルが付けられているが、グラナドスの孫弟子に当たるピアニスト、アリシア・デ・ラローチャによると、グラナドス自身が付けたものは 4 曲目〈ビリャネスカ〉、7 曲目〈バレンシアーナまたはカレセーラ〉のみである。他の曲のタイトルは、バルセロナの出版社、ユニオン・ムシカル・エスパニョーラ Union Musical Española によって後に付けられたものなので注意が必要である。全ての曲が当時グラナドスと親交のあった人物に献呈され、その中には後に妻となるアンパロ・ガルや、ロシア五人組の一人、セザール・キュイらが含まれている。
成立背景 : 井澤 友香理
(507 文字)
更新日:2014年3月19日
[開く]
成立背景 : 井澤 友香理 (507 文字)
この作品の成立には、グラナドスが 1880 年代半ばに師事していたフェリペ・ペドレルが大きく関わっている。ペドレルはこんにち「スペイン国民楽派の父」と呼ばれる作曲家・音楽学者で、スペイン固有の音楽様式の確立を試みていた。グラナドスはこの作品において既存の民謡をそのまま引用することはしていないが、スペイン国内の音楽におけるあら
ゆる要素を意識していることは明らかである (例えば第 3 曲〈ファンダンゴ〉はその名の通り、フラメンコで用いられる典型的なファンダンゴのリズムを基調とし、第 5 曲〈アンダルーサ〉には、スペインにおける音楽を語る上で不可欠な楽器であるギターの奏法が模倣されている)。
本作は、パリに留学していた 1887 年 (20 歳) ~ 1889 年頃作曲が始められ、1890 年に完成したと考えられている。同年、バルセロナの出版社カーサ・ドテシオ (現在は同地の出版社ユニオン・ムシカル・エスパニョーラ Union Musical Española に引き継がれている) から 3 曲ずつ 4 巻に分けて出版され、同年 4 月 20 日バルセロナのテアトレ・リリックで作曲家自身によって初演された。
演奏のヒント : 菊地 裕介
(3087 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 菊地 裕介 (3087 文字)
スペイン舞曲集より アンダルーサ Op.37-5
■はじめに "Andaluza" は、作曲者自身がつけたタイトルではないが、あたかもフラメンコ(アンダルシア地方の伝統芸能)のサパテアード(足打ち)や拍手のコントラティエンポ(裏打ち) が聞こえてくるような空気がこの名づけをもたらしたのだろう。ちなみに"Playera"もアンダルシアの歌の名である。(砂浜の、という意味から転じて今日ではT シャツのことを指すらしいけれど…)ピアノのための作品であるが、これらの特性によくマッチすることから、ギターでの演奏の機会も非常に多い。
■自分ならではのストーリーを組み立てよう グラナドスの最初期の作品であるが、もっともポピュラーなもののひとつであろうこの曲の全体は、限られた楽想が連歌のように韻を踏んで繰り返されるシンプルな三部形式となっている。楽想自体もシンプルなものが多いが、それだけに自由な発想の可能性が広がり、噛めば噛むほど味が出る。名品として親しまれるゆえんであろう。
以下のごときストーリー的描写も、あくまでも筆者の構想にすぎないので、何らの正当性をも持ちえないが、演奏家による楽譜の「楽しみ方」の一つの事例として、着眼点等を参考にされて各自の世界を作られたい。
●序奏~ 序奏のバスのステップはアッチャカトゥーラ的に装飾され「ジャンジャンジャン!」、右手におかれたコントラティエンポ「ンパンパンパ…!」と合わせてスペイン風の気分を盛り上げる。これに導かれる主旋律の動機もスペインに由来する舞曲サラバンドのリズムの面影を残し、気楽さの内にそこはかとなく気高さを備えている。(アンダルシアの夜は、歌い、舞い、語りかけ、祈るのだ。) この旋律はアウフタクトの3音(「ラララ♪」…といった雰囲気で)の順次上行(x )ののち、ひとたびH へ長3度ジャンプするが、その後はH-A-H-Aを往復した挙句、結局最後のAのアクセントがもたらす下行圧力が、性急なカデンツを導く。(両外声が反行ではあるものの、ユニゾンである点も独特である。) やや強気で「つれない」旋律であるが、しかしこのことがこの旋律に秘められた発展性をもたらし、のちの高揚をもたらすのである。 繰り返されて第8小節ではこれが6 度下行し平行調(III度調)のG-dur への束の間の転調をもたらすが、その後すぐ両外声に平行5 度を多発させるオルガヌム的に大胆で古風な和声進行でもとのe-moll へと向けやや強引に引き戻され(変終止的)、素朴ゆえに神秘と魔力に満ちた異国情緒を、いっそう掻き立ている。
●11小節目~ 第11小節からも再び繰り返しであるが、左右のリズムは反転しており、また第13小節ではそれまでの最高音であるC に達し(これで冒頭のx とも一致する)、バスも7 度上行することと相まってやや強気さが潜み、本音が見え隠れするようなセンチメンタルなムードを醸すが(Ⅱ7)、やはりすぐにカデンツを指向する。ただしここでは3/8拍子の1小節が挿入され、カデンツはよりクラシカルで完全な形を見せている。カデンツのあとは、第13小節の4つの音からなる本音(H-A-H-C) が完全4度下(Fis-E-Fis-G) であきらめのようにこだまするのだが、3回目はx にあたる3音が装飾を伴ってピカルディー終止的に長調に転じ、束の間の笑顔を見せる。(何だか一抹の嘘くささも感じさせるのだが…)
● 20小節目~ 第20小節において10度下で長調を断定する支えを得ているのだが、主旋律はその直後に自ら疑念を捨てきれず長調の支えをC で固辞するが(準固有和音)、これを乗り越えて単独で最高音にD に達し、言わば大見得を切る形となる。常に準固有和音の影がちらつくものの、第22小節までは内声が長調的な逞しさを補強しようとしているが、第23小節のpiù p でこれにも疑いが生じ、結局は慎み深い短調に戻るのである。(実は最初のx のアウフタクト以来、ソプラノの旋律は一度たりとも長調の構成音を歌っていない!)第30小節に再びみられるピカルディー終止のx は、第18小節とまったく同じものであるが、これらのプロセスを経た後にあってはややフェイントを内包する「忍従」のようにも聴こえないだろうか?
● 32小節目~ 第32小節から始まるB では、テンポをAndanteに緩め、同主長調のE-dur に転調するが、旋律自体はA のものを縮約したものがサラバンドのリズムともどもオスティナート的に使われる。加えてA では一時的なものにとどまった平行旋律が、ここでは終始10度あるいは6度下に寄り添っているので、信頼感があり一時の安堵を覚えることだろう。ところで、サラサーテのヴァイオリン曲"Playera" は「祈り」として親しまれているが、このグラナドスの"Playera" の、特にこの部分が、チャイコフスキーの「朝の祈り」の冒頭と同じ動機で、やや同じムードを持つことは、偶然の一致だとしても興味深い。 * 譜例(チャイコフスキー冒頭2小節)
内声に同調して第39 小節から見られる下行する旋律はぴったりペンタトニック(五音音階)にマッチしており、その素朴で潔白なムードを演出するのに一役買っている。(同意の相槌Cis-H とともに寄り添うA-Gis はこのペンタトニックからはハミ出るが…)この潔白なモティーフは違ったアクセントやニュアンスを伴って、全終止のカデンツを持つもの、持たないもの合わせて幾度も慈しむように繰り返され、最終的にppに達する。相槌の噛ませ方などを駆使して、このようなリピートにどれだけの即興性を持たせられるか、演奏者が試されるポイントでもあろう。「~だろう。~でしょう。~であろう。~じゃないか。~であるまいか。」 日本語でもいろいろな語尾のニュアンスが、あるものだ。
● 48小節目~ 第48小節からはほぼ、以上の16小節の繰り返しだが、細かい音価やニュアンスの変化は不注意の産物か、はたまた即興性のあらわれか…(余談だが、グラナドスの自作自演とされているピアノ・ロールの録音を聴くと、その優れた即興性と、楽譜との差異の多さに驚かされることだろう。) 決定的な変化は第63小節からの潔白モティーフの6回目の(!)繰り返しにおいて、ソプラノのCis に内声はC で対立し(対斜)、少なくともペンタトニックは明白に打ち消され短調を方向付けることである。まだ長調へ戻る可能性を完全には捨てきってはいないものの…(準固有和音かもしれないので) こうして再帰するA は、ほぼ完全な再現であり、相違点はほぼ曲が終わる第95小節にわずかにみられるリズムの左右反転(第11-12小節に類似)のみである。
●再現 最終的には、百聞は一見に如かず。こうして書きながらも筆者の脳裏には、学生時代にアンダルシアを数度にわたって訪ねた時の思い出がよみがえる。旅行とはただ漫然と移動するだけではない。コンクールやコンサートが目当てであっても、風土や文化、そして言葉についてある程度の予習をしてから行ったものだ。もちろん、レパートリーとしていくばくかのスペイン音楽を携えて… まだアンダルシアを体験していない方は、ぜひこの曲を入口として旅に出てみられては?今はインターネットでいくらでも情報が手に入るからこそ、しばし現地の人々とともに生活されてみてはいかがだろうか?きっと一生残る財産になるだろう。
執筆者 : 齊藤 紀子
(843 文字)
更新日:2007年10月1日
[開く]
執筆者 : 齊藤 紀子 (843 文字)
各々3曲から成る4つの曲集により構成された全12曲の舞曲集。既成の曲を利用することなく、各舞曲を独創的に創造している。尚、各曲のタイトルは、アメリカで出版された楽譜に基づいている。
第1曲目の<メヌエット>は、ト長調の4分の3拍子。リズミカルで力強い性格を持つ。
第2曲目の<オリエンタル>は、ハ短調の4分の3拍子。印象深いアルペジオに乗り、哀愁を帯びたメロディーが歌われる。
第3曲目の<サラバンダ>は、ニ長調の4分の3拍子。この舞曲は、バロック期の洗練されたサラバンドとは印象が異なり、エネルギーがみなぎる、より原初的な舞曲である。
第4曲目の<ビリャネスカ>は、ト長調の4分の2拍子。<ビリャネスカ>とは、「村人の歌」の意味である。この曲は、牧歌的な雰囲気を持ち、鈴の音が印象的である。
第5曲目の<アンダルーサ>は、ホ短調の8分の6拍子。ギターの編曲により、この曲集の中最も名高い作品となった。ギター風の伴奏と、哀愁を帯びたメロディーが組み合わされる。
第6曲目の<ロンダリア・アラゴネーサ>は、ニ長調の4分の3拍子。「ロンダリア」とは、「民族的な弦楽団」を意味する。
第7曲目の<バレンシアーナ>は、ト長調の4分の3拍子。「バレンシア」は、オレンジの産地として有名なスペイン東海岸の町の名である。躍動的で、変化に富んだ曲。
第8曲目の<アストゥリアーナ>は、ハ長調の4分の2拍子。スペイン北部にあるアストゥリア地方の舞曲である。明るく快活な性格を備えている。
第9曲目の<マズルカ>は、変ロ長調の4分の3拍子。ポーランド的なマズルカとはやや異なり、スペインらしい、躍動感溢れる舞曲である。
第10曲目の<悲しき舞曲>は、ニ長調の4分の3拍子。様々な表情を持ち、変化に富んだ曲となっている。
第11曲目の<サンブラ>は、4分の3拍子。ト長調で記譜されているが、音楽としてはフリギア旋法が特徴的である。<サンブラ>とは、グラナダ地方のムーア人の舞曲。
第12曲目の<アラベスカ>は、イ短調の4分の3拍子。
楽章等 (12)
ピティナ&提携チャンネル動画(11件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (11)

(株)音楽之友社

(株)音楽之友社

ハンナ(ショパン)

ハンナ(ショパン)

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

Musikverlag Doblinger

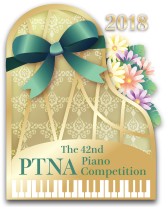 コンペ課題曲:F級
コンペ課題曲:F級  ステップレベル:発展4
ステップレベル:発展4










