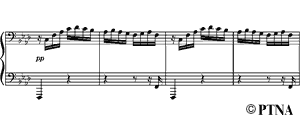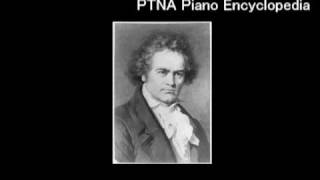ベートーヴェン : ピアノ・ソナタ 第23番「熱情」 第3楽章 Op.57
Beethoven, Ludwig van : Sonate für Klavier Nr.23 "Appassionata" 3.Satz Allegro ma non troppo
作品概要
解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(989 文字)
更新日:2019年1月14日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (989 文字)
(第3楽章)4分の2拍子 ヘ短調 ソナタ形式
[提示部]
前楽章に引き続き、減7和音の付点リズムによる連打によって導入される。主要主題は拍頭の音が第1楽章の主要主題と共通しているほか、ナポリII度和音上で繰り返されることも、第1楽章の主要主題と通低しており、この楽曲全体が第1楽章の主要主題から導き出されているといってもよいかもしれない。
副次主題は属調のハ短調であらわれるが、これもナポリII度の和音によって特徴づけられている。
[展開部+再現部]
このソナタでは展開部以降が反復記号によって繰り返される構造になっている。
展開部はもっぱら変ロ短調で書かれており、主要主題が発展的に扱われた後、リズム的特長をもつ新たな動機があらわれる。ヘ短調で再び主要主題をあつかい、属保続音(ハ音)が主調を完全に準備する。
再現部では主要主題、副次主題ともヘ短調で再現され、反復記号によって展開部の冒頭へ戻る。
[終結部]
第1楽章のような「第2の展開部」としての終結部というよりは、むしろ器楽的に発展し、華々しく楽曲を締めくくる要素が強い。Prestoとなり、和音連打による楽句、分散和音の和声型にささえられた主要主題によって全曲を閉じる。
第1楽章の発展的なソナタ形式に対し、第3楽章では提示部の2つの主題の調性関係と展開部+再現部の調性関係が、それぞれ主調→属調/下属調→主調というシンメトリカルに構成され、古典的な2部分ソナタの構成が強く意識されているように思われる。
そもそもソナタ形式の展開部とは、提示部の主調→属調という関係に対して、再現での主調回帰へむけた移行プロセスの部分であり、経過的な部分であった。それゆえ、提示部の主題とは関係のない経過的な楽句がはさみこまれることもしばしばある。しかし、このソナタの第3楽章展開部にみられるような、主題的特徴をもつような動機の挿入は、こうした伝統的なソナタ形式の枠組みのなかでは語れない。
第1楽章終結部を「第2の展開部」として拡大する構成法や、第3楽章展開部における新動機の登場は、すべて《交響曲第3番》「英雄」Op.55の構成に通じている。
この作品でベートーヴェンは、エラール製ピアノによって得られた幅広いダイナミック・レンジと音域、そして交響曲的な展開技法と構成法を融合させることで、ピアノ・ソナタのジャンルにおいて新たな一歩を踏み出したといえよう。
演奏のヒント : 大井 和郎
(588 文字)
更新日:2025年10月9日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (588 文字)
あまりにも有名な第3楽章ですので、学習者が犯しやすいミスから述べます。冒頭の表示記号通り、Allegro ma non troppaで、決してテンポを最初から暴走しないこと。ゆっくり目に始めるようにするのですが、この「ゆっくり目」の中に、強い緊張感が欲しいのです。この楽章はまさにそれが命です。Pでもゆっくり目でも緊張感を出せるか否かで演奏が決定します。どうしたらそれが再現できるのか、考えてみて下さい。
次に流れについて。この第3楽章にはいくつかのピークポイントがあります。これらのピークポイントに向かって「方向性を定めること」が重要なポイントになります。1つ目のピークポイントは、112小節目、2つめのピークポイントは、176小節目、そして3つめが、308小節目から始まるCodaのセクションで、ここで始めてテンポをPrestoにします。
この楽章は決して幸福を表現する楽章ではありません。いずれ死を迎えなければならない、人間の運命に対する反逆と理解します。
多くの音源がありますが、個人的には、ラザール・ベルマンのレコーディングをお勧めします。大変緊張感に満ちた演奏となっています。是非お聴き下さい。
ピティナ&提携チャンネル動画(12件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (3)

ヘンレ社(ヤマハ)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社