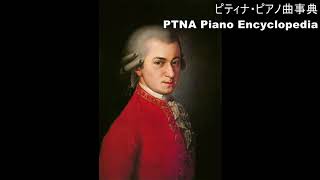作品概要
解説 (2)
執筆者 : 稲田 小絵子
(492 文字)
更新日:2008年10月1日
[開く]
執筆者 : 稲田 小絵子 (492 文字)
ピアノ・ソナタ第14番ハ短調と共に1785年に出版された。モーツァルトの自作品目録によれば、ソナタの作曲は84年10月14日、幻想曲は翌85年5月20日である。幻想曲は本来、導入曲としての用途があったため、この作品は、ソナタの出版に際して、その前奏のために作曲されたものと考えられる。これら2曲は現在でも1セットとして扱われることが多いが、モーツァルト自身が幻想曲のみを演奏することもあったことから、独立した2つの作品と考えて問題ないだろう。
献呈はテレージア・フォン・トラットナー。当時モーツァルトが借りていた家(いわゆる「フィガロ・ハウス」)の家主夫人である。彼女はまた、モーツァルトのピアノの生徒でもあった。
作品は転調を頻繁に繰り返し、幻想曲の名にふさわしく自由に展開してゆくが、テンポの変化によって5つの部分に分けられる。すなわちアダージョ、アレグロ、アンダンティーノ、ピウ・アレグロ、アダージョである。最初のアダージョはさらに、重苦しいハ短調と明るい響きのニ長調の2つに分割できる。地から這い上がるようなこの冒頭主題が最後に回帰し、ハ短調ソナタへの橋渡しとなって作品を閉じる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(861 文字)
更新日:2025年10月9日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (861 文字)
この幻想曲を弾くにあたって2つの事を覚えておいてほしいです。1つは、これまで他のモーツアルトの作品でも述べてきたことですが、強弱記号を鵜呑みにしないことです。状況状況に合わせてフォルテとピアノの音量を調節してください。そして2つ目は、この規模の大きな幻想曲を弾く場合、曲全体に弦楽器をイメージして欲しいという事です。
1つ目の注意点ですが、例えば冒頭、1小節目の1拍目にフォルテが来ますが、その後すぐピアノマーキングが書いてあります。フォルテの部分だけは楽器数が多く、そのあと楽器数が少なくなるのかも知れませんが、ラフマニノフやリストのようなフォルテではなく、チェロや低音の楽器が柔らかく演奏するフォルテのイメージであり、決して硬く鋭いフォルテではありません。もしかしたら1小節目から2小節目1拍目までは同じアンサンブル(楽器)かも知れません。少しだけ1小節目1拍目にアクセントを付ける感じで、ベートーヴェンのようなスビトフォルテを避けます。その後、2小節目、2拍目裏拍から、木管がppで出ます。このように全ての音符をピアノの為ではなく、オーケストラの楽器にたとえて、オーケストレーションを試してみて下さい。それが、多くの異なった音色を生みます。
36小節目のフォルテも、弦楽器のフォルテと考え、決して鋭く、硬いフォルテではありません。しかし55小節のような部分はtuttiと考えますので、この場合は多少大きめのフォルテにします。このように状況に応じて音量を決定してみて下さい。特に決まりはありませんので、奏者が感じたオーケストラのイメージでフォルテを決めて構いません。
幻想曲ですのでかなり自由に演奏して良いのですが、全て弦楽器のアンサンブルと考えると、あまり厳しく、硬いフォルテは出ないと思います。艶があって厚みのあるフォルテを目指してみて下さい。
ピティナ&提携チャンネル動画(6件)
楽譜
楽譜一覧 (12)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)サーベル社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)音楽之友社

EMB

Peters