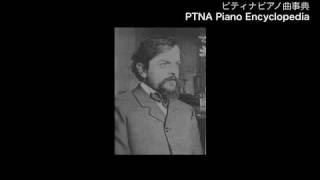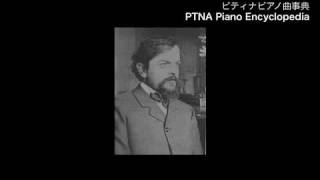作品概要
楽曲ID:
1450
作曲年:1913年 出版年:1916年
初出版社:Durand
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:練習曲
総演奏時間:45分40秒
著作権:パブリック・ドメイン
楽章等 (12)
ピティナ&提携チャンネル動画(29件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (12)

ドビュッシー ピアノ曲集7
(株)音楽之友社
(株)音楽之友社

ドビュッシー ピアノのための12の練習曲 DEBUSSY
(株)全音楽譜出版社
(株)全音楽譜出版社

ドビュッシー集2
(株)春秋社
(株)春秋社

標準版 C.ドビュッシー 12の練習曲
(株)音楽之友社
(株)音楽之友社

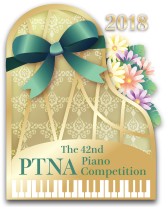 コンペ課題曲:F級
コンペ課題曲:F級  ステップレベル:展開1,展開2,展開3
ステップレベル:展開1,展開2,展開3