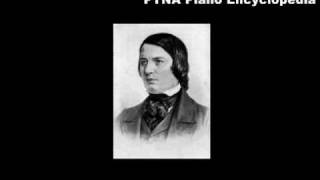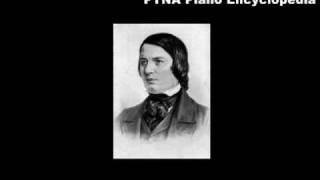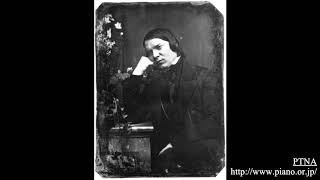シューマン : ピアノ五重奏曲 変ホ長調 Op.44
Schumann, Robert : Quintett für Klavier und Streichquartett Es-Dur Op.44
作品概要
楽器編成:室内楽
ジャンル:種々の作品
総演奏時間:25分00秒
著作権:パブリック・ドメイン
解説 (1)
執筆者 : 齊藤 紀子
(746 文字)
更新日:2008年6月1日
[開く]
執筆者 : 齊藤 紀子 (746 文字)
シューマンにとっての歌の年(1840年)、管弦楽の年(1841年)に続く室内楽の年、1842年に作曲された。同ジャンルの最初の作品(習作を除く)である3曲の弦楽四重奏曲に続いて作曲された。1842年の夏に着手したのち、完成までは3ヶ月強を要し、11月の初めにようやくまとめられた。翌年の年明け早々、ライプツィヒのケヴァントハウスにて、クララのピアノで初演されている。この時、聴衆の中には、ドイツ・ロマン派の音楽に批判的態度を示していたベルリオーズもいたが、この曲に非常に感激したと伝えられている。
第1楽章 快活に、輝かしく 変ホ長調 2分の2拍子
力強さ、輝かしさを前面に押し出す第1楽章と、ピアノの音色を活かした柔和な第2主題の対比がみられるソナタ形式の楽章。展開部は、第2主題で始まる。
第2楽章 行進曲風に、ややゆったりと ハ短調 2分の2拍子
葬送行進曲を想起させる楽章。自由なロンド形式と捉えることができる。左右の手がユニゾンを弾くピアノの下降形分散和音に続き、第1ヴァイオリンが行進曲の主題を提示する。2つの副主題はそれぞれ、ハ長調とヘ短調に転調する。
第3楽章 スケルツォ 非常に快速に 変ホ長調 8分の6拍子
上下に行き来する音階を効果的に用いたスケルツォ。トリオを2つ持つ。第1トリオは変ト長調、第2トリオは変イ短調に転調する。
第4楽章 快活に、しかし甚だしくなく 変ホ長調 2分の2拍子
第1楽章の第1主題とはまた違う力強さで、壮大に全体を締めくくる楽章。自由なソナタ形式と捉えることができる。第1主題は、打楽器的な奏法を用いるピアノが、左右に手のユニゾンによって提示する。第2主題はヴィオラの柔和な音色が活かされている。終結部分は二重フーガで書かれ、高揚した雰囲気のまま幕を閉じる。