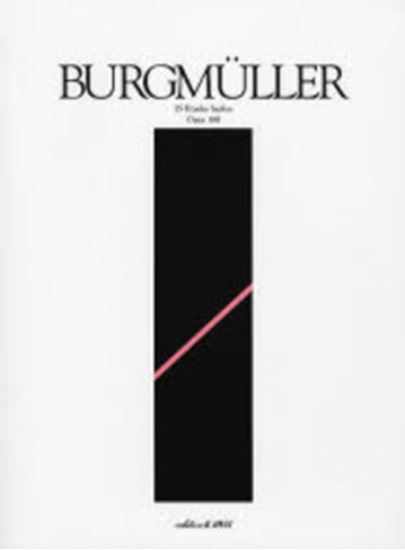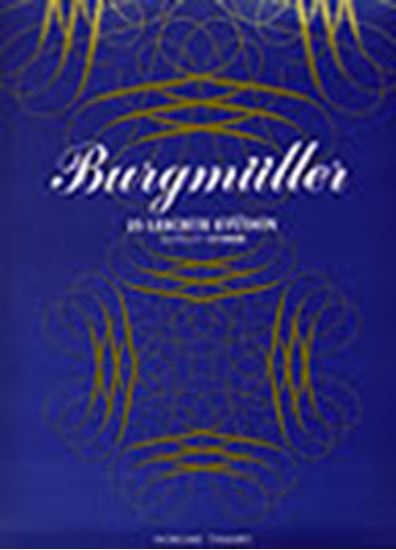ブルクミュラー(ブルグミュラー) : 25の練習曲 アヴェ・マリア Op.100-19
Burgmüller, Johann Friedrich Franz : 25 Etudes faciles et progressives, conposées et doigtées expressément pour l'étendue des petites mains Ave Maria Op.100-19
作品概要
解説 (3)
解説 : 佐藤 卓史
(404 文字)
更新日:2022年1月31日
[開く]
解説 : 佐藤 卓史 (404 文字)
religioso(敬虔に)の指示を待つまでもなく、カトリックの礼拝堂に響く聖歌隊の合唱を模した曲です。カテドラルの残響の長い響きを表現するために、ペダルの使用は必須でしょう。打鍵よりも少し後で踏み換える、レガートペダルの使用法を習得しましょう。色とりどりの変化和音がステンドグラスのように美しく曲を彩りますが、特に16小節の VI 度調ドミナントでの半終止は奇跡的な瞬間です。
演奏のポイント(原典 ♩=100)
1〜8小節は4声、 9〜16小節は3声のハーモニーです。最適なバランスを探ってみましょう。楽譜上には示されていませんが、合唱をイメージして随所に自然なブレス(息継ぎ)を入れます。17小節以降は8分音符の伴奏型が加わりますが、ペダルを踏むとこれがうるさくなりがちなので、気をつけましょう。27小節のモルドゥア IV 度の響きも味わって。
楽曲分析図 : 飯田 有抄
(12 文字)
更新日:2018年3月15日
[開く]
楽曲分析図 : 飯田 有抄 (12 文字)
譜例提供: 音楽之友社
演奏のヒント : 大井 和郎
(1158 文字)
更新日:2019年1月31日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (1158 文字)
まず形式から把握しましょう。
1-2小節間 3-4小節間 5-8小節間 の3つのフレーズが前半
9-10小節間 11-12小節間 13-14小節間 15-16小節間 の4つのフレーズが中間部
17-18小節間 19-20小節間 21-24小節間 の3つのフレーズが後半
25-30小節間 Coda
になります。
次に各フレーズのdirection(方向性)を知っておきましょう。方向性とは、フレーズの中でどの音に向かっていくか、どの音に導かれるかということで、必ずしも向かう音の音量が大きいと言うことではありません。
1-2小節間 3-4小節間 4つめの音がゴールの音になる。5-8小節間 6小節目1拍目が
ゴールの音。
9-10小節間 11-12小節間 13-14小節間 15-16小節間 各フレーズ4つめの音。
17-18小節間 19-20小節間 21-24小節間 前半と同じ
Coda 25-26小節間 27-28小節間 29-30小節間 それぞれ4つめの音。
になります。
次に音量について知っておきましょう。
1 前半 1-2小節間、 3-4小節間、 5-8小節間 の音量の差を付ける。5-8小節間を最も大きくするようにコントロールします。ただしあくまでpの範囲内であまり大きくしすぎないようにします。
6小節目はサスペンションやパッシングトーンが出てきて、感情的にも愛くるしい部分になりますので、十分にそれを表現します。指導する際には、生徒さんにサスペンション(掛留音)やパッシングトーン(経過音)が無いヴァージョンも弾いて聴かせる。
各フレーズの最後の音は、弾くと言うよりは触れる感じで、決して力を入れません。
2 中間部 9-10小節間よりも、11-12小節間を少し大きくしておきます。何故なら13-14小
節間でカラーを変えなければならないからです。
17小節目以降、左手が大きくなりすぎないように注意します。またその際にテンポも速くならないように注意します。
21小節目 内声は重要ですが、トップの方が重要です。24小節目、スタッカートは不要です。
このスタッカートはフレーズの終了を意味するもので、次の音と区別させる役割と考えます。
27小節目はpocoなのであまりリテヌートをかけません。30小節目、少し29から時間をかけてゆっくり弾きます。
この曲の和声を分析すると、借用和音が出てくる場所や、非和声音が出てくる場所は、とても感情的で感傷的です。このような部分は気持ちを込めて弾きましょう。
例:5-6小節間 13-14小節間 21-22小節間
そして、決してメトロノーム的にならないこと(硬く聞こえる原因になります)、ダイナミックが平坦にならないこと、和音のバランスは常にトップを出して、メロディーラインを際立たせる事等が大切なことです。
編曲・関連曲(6)
ピティナ&提携チャンネル動画(19件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (26)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画(バスティン)

(株)東音企画

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社
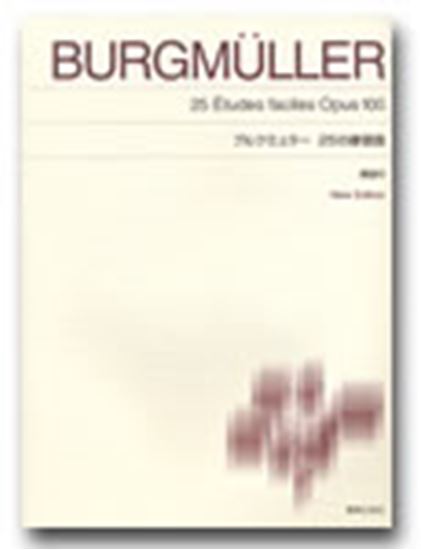
(株)音楽之友社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)ドレミ楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

カワイ出版

カワイ出版

デプロMP

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

デプロMP

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)共同音楽出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

Neil A. Kjos Music Company