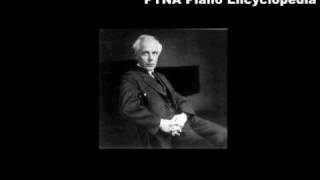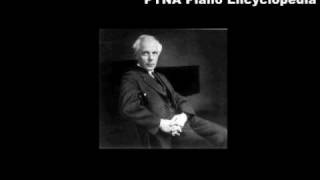バルトーク : ハンガリー農民歌にもとづく即興曲 Op.20 BB 83 Sz 74
Bartók, Béla : Improvizációk magyar parasztdalokra Op.20 BB 83 Sz 74
作品概要
解説 (1)
総説 : 舘 亜里沙
(947 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
総説 : 舘 亜里沙 (947 文字)
1920年に完成し、1922年にウニベルザール社から刊行された8曲から成るピアノ独奏曲(ただし第7曲だけは〈ドビュッシーとの思い出に〉というタイトルのもと、1920年に雑誌『ラ・ルヴュ・ミュジカル』に掲載された)。バルトークはちょうどこの作品の創作直後の1921年に、それまでの民謡についての資料をまとめた論文『ハンガリー民謡集』を発表しており、この即興曲についてもやはり、バルトークのそれまでの民謡を絡めた創作の一つの集大成であることが窺える。
バルトークの(民謡を含めた)民俗音楽の収集・研究が、彼の創作と大きく関わっているということは周知の事実であるが、そうした民俗音楽を題材とした作品も、その創作目的や題材の扱いによって、さらに細分化することが出来る。まず創作目的については、①民俗音楽の旋律を直接用いているか否か、②教育的な目的があるか否か、という2つの極を設定した場合、この即興曲を「教育的な目的のない、民俗音楽を直接用いた作品」に分類することが出来る。 次に、題材の扱いに目を向けると、「教育的な目的のない」この即興曲が、バルトークをより自在な民謡の編曲へと駆り立てていたことがわかる。バルトーク自身もこの作品に対して「かなり大胆な様式」を示したとコメントしているが、やや前の時期に創作された《15のハンガリー農民歌》(Sz. 71)に対して調号を放棄していることや、特に第6曲以降、元の民謡をより音楽素材の断片として消化していることからは、むしろ民謡を出発点に独創的な音楽を創り上げようという姿勢が観取される。
この即興曲に含まれる8曲は、第1曲・第2曲(ハ調)/第3~5曲(ト調)/第6曲(変ホ調)/第7曲・第8曲(ハ調)のように、4つの楽章のように分けることが出来、「即興曲」というタイトルにそぐわない周到な構成を持っている。採用されている民謡は、『ハンガリー民謡』におけるバルトーク自身の分類によれば、第7曲のみ「統一性のない民謡」(アウフタクトのついたエオリア旋法による、A-B-C-D形式の民謡)、それ以外の曲は「古い民謡」(五音音階によるA-B-C-D形式の民謡)となっており、バルトークが五音音階のプリミティヴな響きに、とりわけ創作の可能性を感じていたことがわかる。
楽章等 (8)
ピティナ&提携チャンネル動画(8件)
楽譜
楽譜一覧 (2)

(株)春秋社

(株)音楽之友社