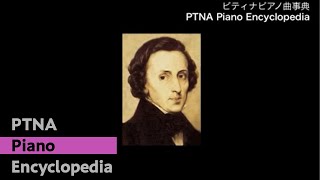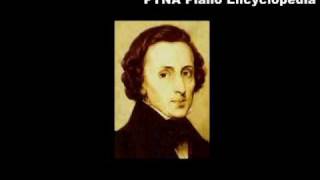作品概要
解説 (2)
執筆者 : 塚田 花恵
(1263 文字)
更新日:2010年4月1日
[開く]
執筆者 : 塚田 花恵 (1263 文字)
【作曲】1840-41年
【出版】1841年にパリ(出版社:M. Schlesinger)、ヴィーン(出版社:P. Mechetti)で、翌42年にロンドン(出版社:Wessel & Stapleton)で出版
ショパンは1839年から46年のあいだ、多くの時間をフランスのノアンにあるジョルジュ・サンドの館で過ごしている。そこでショパンは、パリの喧噪を離れ、創作活動に集中することができた。1841年に完成したこのポロネーズは、ノアンで生まれた重要な作品の1つである。
ショパンはこの作品において、ポロネーズとマズルカという2つの舞曲??いずれもポーランドの主要な舞曲であり、ポーランドの精神を象徴するものである??を統合している。ショパンのポーランドへの想いは止みがたく、この時期に友人のフォンタナに充てた手紙のなかで、「ポーランドに帰れることがあるだろうか」(小松雄一郎訳)とも述べている。
この作品は、ショパンの親しい女友達デルフィーナ・ポトツカの妹である、シャルル・ド・ボーヴォ公爵夫人に献呈された。
作品全体は、以下のように三区分できる。
第I部:序奏(1-8小節)-A(9-26小節)-B(27-34小節)-A(35-52小節)-B(53-60小節)-A(61-78小節)-C(79-102小節)-B(103-110小節)-C(111-126小節)
第II部:D(127-260小節)
第III部:序奏(261-267小節)-A(268-285小節)-B(286-293小節)-A(294-326小節)
第I部と第III部はポロネーズで、序奏と3つの主題部分から構成されており、第II部はマズルカになっている。各部分は、対照的でありながらも連続性を持つように、バランスが計算されている。
第I部は、8小節の導入から始まる。両手のオクターヴのクレッシェンドはリストを思わせる力強いパッセージであり、この部分はfis-mollのドミナントとして主要主題を準備している。主要主題のA部分は、非常に力強い性格である。左手の跳躍、両手で行われる伴奏、低音部での装飾やトリルなどによって、非常に充実した強い響きが生み出される。このA部分は第I部で2度反復されるが、その度に変奏されて、力と勢いを増していく。B部分は短い副主題で、唐突に調性が変わるため、A部分との強いコントラストが生み出される。しかし構造的には、その後に来るA部分やC部分を準備する「アウフタクト」部分として見ることもできる。C部分の新しい素材は、リズミックな動機のあとにV度?I度の動きが続き、それが絶え間なく反復するものである。この部分ではa音のペダルが保たれ、それが次のA-durを準備している。
第II部で、あたかも夢のように挿入されるマズルカは、ポロネーズ部分のエネルギッシュな雰囲気とは対照的な性格である。しかし、優しい響きを作り出す3度和音はA部分との関連を作り出しており、この旋律型は序奏とも共通点を持っているのである。
第III部では、第I部が圧縮されて再現する。
演奏のヒント : 大井 和郎
(3600 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (3600 文字)
10分以上もかかる大曲ですが、構成はそこまで複雑ではありません。基本の素材の数はそれほど多くは無く、変奏によって層が厚くなっているだけに過ぎません。奏者はこれら基本の素材を把握し、長い目でゴールを見据えることがヒントになります。一見長い曲でも分析をすることで曲は大変わかりやすくなります。そして奏者のみならず、聴き手にとって「わかりやすい」演奏が望ましい演奏と言えます。それでは冒頭から見ていきましょう。 1-8小節間はショパン独自の、「調性が分からない冒頭」で、例えばスケルツォの3番や、op10-12 などにも見られるようにショパンの場合、相当先まで進まないと何調であるか分からない曲は多くありますね。この冒頭8小節間は結局、fis-mollのドミナントである、「Cis」がpedal point(保続音)として書かれてあります。スケルツォの3番でもそうなのですが、大切な事は「拍の認識」とそれを正確に表現することにあります。5小節目からは16分音符が1小節間に12のタイミングで来ますのでわかりやすいとも思いますが、1-4小節間は下手をすると何拍子であるかさえも、演奏によっては分からなくなります。冒頭4小節は、一切のルバートをかけず、メトロノームのように正確にタイミングを取ってください。そしてこの4小節間、2拍目は1拍目よりも大きくならないように注意します。そしてもちろんの事ですが、1小節目が最も音量が少なく、8小節目にかけてクレシェンドをかけていきます。 さて、最初の素材はA-1とでもしておきましょう。9-16小節間で8小節分あります。この8小節間は9-12小節間と、13-16小節間の2つに分けることができます。そして、9-12小節間はさらに、9-10小節間と11-12小節間に分かれます。9-10よりも、11-12の方がメロディーラインは3度で進行し、ピッチも上がりますので、音量は大きくなります。 そして達するのが13小節目なのですが、ここは2拍目のメロディーラインDがゴールになりますね。そして次の小節を見てみると更にメロディーラインは上行し2拍目でAになります。ここで、簡単な考え方として、13小節目は、Cis -D-Cis と考え、14小節目は、Cis-A-Gis と考えます(筆者は今、メロディーラインの重要な音のみを抜粋しています)。この考え方で次の小節を見ると、GisEーDis(今度は1拍目と3拍目を抜粋しています)となり、最後の16小節目では、Cis-D-Cisと、後ろに進むにつれて、音程はより広く、音はより高い音に変化していくことがわかります。 つまりは、A-1の9-16小節間、テンションは小節ごとに次々と高まっていくことがわかります。故に、9小節目、フォルテと書いてあるのですが、メゾフォルテ位から始めたほうが無難に進むことが出来ます。 次に17小節目から27小節目までの10小節間をA-2としておきます。このA-2では、主題のメロディーラインが17小節目より左手オクターブで始まります。既に音量的にもかなり大きい部分ですが、A-1が3小節目でテンションを上げるのに対し、A-2では3小節目(小節数で言うと19-20小節間です)A-durに一瞬転調して、カラーが変わります。21-22小節間舞曲的な進行で23小節目のカデンツ(終止形)に入ります。そして、24-26小節間の和音はD Fis C でこれをItalianと呼ぶ増6度のドラマティックな和音で終わります。この24-26小節間は、A-1、A-2の中で最も音量的には大きくなってよいと思います。 次に53小節目から60小節目まで、A-3とします。53小節目において調はB-mollになっています。この8小節間はきれいに2つに4小節ずつ分かれ、53-56小節間と57-60小節間に分かれます。個人的には53-56のほうが57-60よりも音量は大きいと思いますが、それは奏者が判断します。いずれにせよ、この2つのシークエンスは平坦にならないよう、音量や音質で違いをつけてください。 このA-3での注意点を書きます。それはオクターブで上行する右手の音階です。54小節目、58小節目、とも、通常の1/4程度の力で、leggieroで演奏されなければならず、変に時間を取ったり、重たくならないようにします。また、練習方法として、右手の4と5の指のみで(1の指を抜いて)、オクターブを上行させてみてください。なかなか難しいですね。このような練習により、右手の4と5を鍛えておきます。なお、もうおわかり頂いていると思いますが、4は黒伴に使うとスムーズに音階を弾くことができます。ここは大変難しい部分です。地道な練習が必要とされます。 61小節目からは、A-1の変奏になります。左手に音階が入ってきますので、音量は大きくなりますし、精神的には落ち着きませんね。69小節目からは、A-2が戻ってきます。前のA-2と比べて異なる部分は76小節目のように装飾的に書かれているだけの違いで、基本的なもって行き方は同じです。 79小節目からは、Bセクションに入ります。79-102小節間をB-1とします。このB-1の音楽的な解釈は後述しますが、まずはどのように和声を分析するかお伝えします。83小節目を例に取ります。ここの基本的な和音はA Cis E で、A-durの主和音です。ところがこの小節にはA Cis E 以外にDis と Fisが入っていますね。この2つを取り除いて考えなければなりません。そうすると、1拍目、裏拍の4つ32分音符の後ろ2つを和声音と考え、前2つを非和声音と考えます。この場合、Dis とFisが非和声音になり、EとCisが和声音になります。そして、2拍目表拍の音を前の32分音符の最後2つとくっつけると A Cis E となりますね。 以降、全てこの考え方に従い、32分音符の最後の2つ+次の8分音符と和音を考えていきます。すると和音は: A Cis E → A D F → A Dis Fis → A D F → A H D → A D F → A C E → A C F → B D F → A C Es → A H Dis → A C E → A H D → A C E という進行をします。 この中でテンションが高まる部分はどこか、テンションの下がる部分はどこか考えてみてください。そしてそれらをスムーズに進行するように強弱を付けてみてください。 さてこの部分の音楽的な解釈法ですが、このポロネーズも英雄ポロネーズと同様にBセクションが長調で躍動的ですね。一見楽しさの表現かとも思ってしまいますが、ショパンは英雄ポロネーズのように、Bセクションを軍隊的に描写しているのではないかと思います。つまりは、いつ軍隊が攻めてくるか分からないという恐怖心の描写ではないかとも筆者は考えています。 103小節目以降、A-2が戻ってきますね。一瞬昔の記憶が蘇るのでしょうか。実に興味深い形式です。そしてA-2が終わるとまたすぐにB-1が始まります。125-126場面が徐々に頭の中でゆっくりと変わっていく様子を描写しています。 127小節目から168小節目1拍目までをB-2とします。このB-2セクションは更に B-2A(127ー140)と B-2B(141ー147) の2つに分けることが出来ます。 B-2Aの場合、129小節目、sotto voceがあるものの、このセクションでは最もテンションの高いところで、ここをピークに気持ちは徐々に落ち着いてきます。そして140は最も気持ちが安らぐ部分です。 B-2Bの場合、穏やかな会話とでも描写しましょうか。しかし少し独唱的でも構わないと思います。 この後、147小節目からは今度はEーdurにてB2-A(147-160)が戻ってきます。161で再びB2-B(161-168)になりますが、今回は後半が前とは異なります。そして169小節からは全く新しいメロディーラインが来ますね。ここをB2-Cとします(169ー184小節間)。 その後は再びB2-A(186ー200)、B2-B(200ー206)、またB2-A(207ー220)、B2-B(220ー227)、B2-C(228ー248)と続きます。250ー260はAが戻ってくるための橋渡しの部分です。そして261にてAが戻り、311よりCodaになります。 実に巨大なこのポロネーズも、このような分析によって同じ素材が繰り返されている事がよく分かりますね。例えば同じ素材でも調によって雰囲気や音量は変えなければなりませんし、変奏によっても雰囲気は変わってきます。
ピティナ&提携チャンネル動画(8件)
楽譜
楽譜一覧 (4)

(株)全音楽譜出版社

(株)春秋社

(株)音楽之友社

Peters