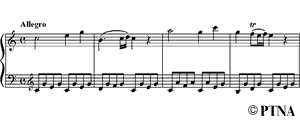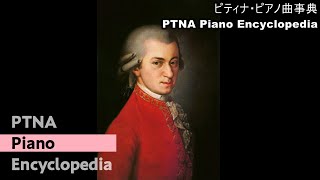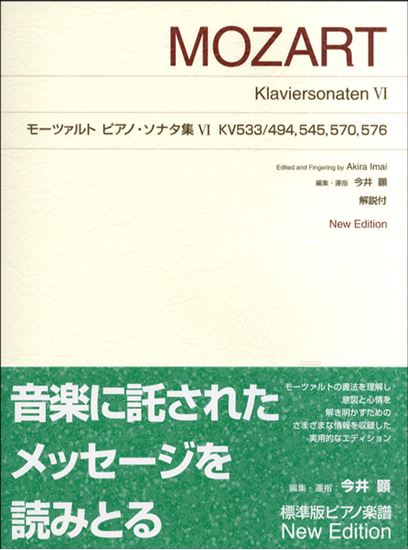モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第16(15)番 第1楽章 K.545 ハ長調
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.15 Mov.1 Allegro C-Dur
作品概要
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:4分30秒
著作権:パブリック・ドメイン
ピティナ・ピアノステップ
23ステップ:応用6 応用7 発展1 発展2 発展3
楽譜情報:33件解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(820 文字)
更新日:2019年3月5日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (820 文字)
第1楽章 ハ長調 4分の4拍子 ソナタ形式
アルベルティ・バスの上に、重音をともなわないシンプルな旋律による主要主題が提示される。音階パッセージによる推移(第5小節~)を経て、同様にシンプルな楽想の副次主題が属調のト長調であらわれる(第14小節~)。分散和音による推移(第18小節~)の後に、短いコーダをともなって前半を閉じる。
後半(第29小節~)は、属調の同主短調であるト短調で、主要主題によって開始され、すぐに二短調へ転じる。そして、音階パッセージによってイ短調からヘ長調へ至る。
主調の下属調であるヘ長調で主要主題が再現され(第42小節~)、音階パッセージによる推移部が拡大される(第46小節~)。
この下属調による主要主題の再現は、しばしば特異なものとして指摘されるが、本来2部形式が発展したソナタ形式にとっては決して珍しいことではない。たしかに、モーツァルトの他のクラヴィーア・ソナタには例がないが、古いタイプのソナタには下属調での再現が見られ、シューベルトのソナタにも例が認められる。
むしろ重要なことは、この下属調への転調が不可避なものではなく、意図的であると考えられることである。というのも、主題再現直前の調性はイ短調を取っており、平行長調であるハ長調(主調)への転調は、自然に行うことができたはずだからである。
また、音階パッセージによる推移部の拡大によって、調性はヘ長調からハ長調へ転じるが、結局は提示部と同様に属和音に終止してしまうため、副次主題の再現は唐突な印象すら与える(自然な再現を目指すならば、ハ長調の主和音に終止する必要がある)。とすれば、実は、この音階パッセージの拡大に意図があり、それは「初心者のための」というタイトルから引き合いに出せば、左右の手による音階練習を意図的に組み込んだのかもしれない。
以降、主調による副次主題の再現(第59小節~)と、分散和音による推移を経て、前半と同様のコーダをもって楽章を閉じる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(559 文字)
更新日:2025年10月9日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (559 文字)
この第1楽章は歌劇的であり、オペラをイメージして場面場面を自分のイマジネーションで作り上げ、歌手は1人か、2人か、また、オーケストラの部分と歌の部分の区別、等、ストーリーを設定してみても良いかもしれません。基本的には極めて楽天的な第1楽章となっています。
この第1楽章は、C-durで始まり、G-durに転調し、d-mollに転調し、ハーモニックシークエンスを経て、F-durに転調し、再びC-durに戻って終わります。その間、冒頭のテーマは、C-dur と F-durの2つの調でしか出てきません。
他の、g-mollとd-mollは、それぞれ29小節目と33小節目に出てきますが、これはどちらかと言うと器楽的な部分であって、歌手が優雅に歌う部分では無いような感じがします。そう考えたとき、メインのテーマはC-durとF-durですので、この2つの調を大切にして、この2つのカラーを完全に変えてみて下さい。
その他、g-moll、d-mollの部分のカラーも変えてみて下さい。例えば、g-mollは強く、d-mollは弱くといったような対比です。
ピティナ&提携チャンネル動画(10件) 続きをみる
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (33)

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)リットーミュージック

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)全音楽譜出版社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)オンキョウパブリッシュ〇

ミュージックランド

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)ドレミ楽譜出版社

ロケットミュージック

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)ドレミ楽譜出版社
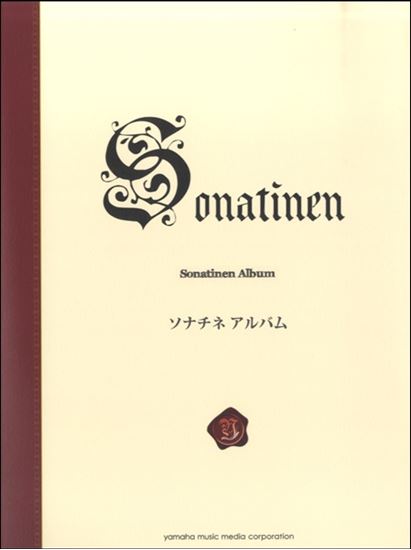
(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)学研プラス

(株)全音楽譜出版社