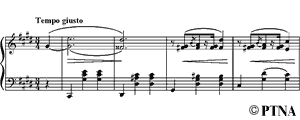作品概要
解説 (3)
解説 : 安川 智子
(964 文字)
更新日:2019年1月9日
[開く]
解説 : 安川 智子 (964 文字)
嬰ハ短調 作品64-2
【作品の基本情報】
作曲年:1846~47 出版年:1847 (Paris, Leipzig)
献呈 : シャルロット・ド・ロトシルド(ナタニエル・ド・ロトシルド男爵夫人) A Madame la Baronne Nathaniel de Rothschild
【楽譜所収情報】
パデレフスキ版:No.7/エキエル版:No. 7/コルトー版:No. 7/ヘンレ版:No. 7/
ペータース版(原典版):(No. 7, 補遺5[ロトシルド家が所蔵していた自筆譜に基づく])
主音は作品64-1と異名同音関係にあたる(変ニと嬰ハ)。そのため4分音符による最初の一音(属音の嬰ト)は変ニ長調のワルツと同じ音であるにも関わらず、次に続く短3和音で全く異なる哀愁に満ちた短調の響きへと転換する。冒頭2小節が右手の6度並進行・半音下降による長い嘆息だとするなら、次の2小節では細かく優雅なステップが続く。この伸び縮みの感覚はこの曲全体に行き渡っており、絶妙のバランスを保っている。たとえばA-B-C-B-A-Bという構造の中で、情感豊かに歌われるAやCと、ノンストップの円舞であるBが交互に現れる。
三度繰り返されるBには、「più mosso(速度を速めて)」の表示があるところとないところがあり、またフランス初版とドイツ初版の間にも違いがある。作品64-1と同じ変ニ長調に転調するCでは「più lento(速度を遅めて)」の表示があるため、その後のBでは速度を戻す意味で「più mosso」が指示されたのであろう。いずれにしても、自由度の高い速度の揺れが、この曲の大きな魅力となっている。
この曲を献呈されたシャルロット・ド・ロトシルドは、ジェイムズ・ド・ロトシルド男爵の娘であり、ショパンのピアノの弟子であった。ショパンは1832年に、男爵のサロンで同夫人ベッティに出会ったことから、ベッティとその娘シャルロット、さらに孫娘マチルドにピアノを教えるようになった。《ワルツ》変イ長調(作品69-1)、《バラード第4番》ヘ短調(作品52)などの重要な作品もシャルロットに贈っていることから、彼女が(あるいはロトシルド家が)ショパンにとって大切な存在であったことがよく分かる。
(2010年2月 安川智子 ※2014年7月改訂)
演奏のヒント : 大井 和郎
(2690 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (2690 文字)
第7番 Op.64-2 cis-moll
音楽的に難しいワルツです。テンポの取り方はピアニストによって様々で、どれが正しくどれが間違っていると言うことはありません。例えば33小節目の新しいセクションに入るとテンポを変える人もいれば、97小節目のpiu mossoを見て初めてこのセクションのテンポを変える人もいます。最終的には奏者に判断がゆだねられます。
このワルツのヒントは「2度の下行」にあります。この「2度の下行」はメロディーラインなどあらゆる箇所に出てきます。この2度をどのように処理するか、色々な考え方ができます。まず冒頭をご覧ください。1-2小節間、メロディーラインはE-Dis です。そして3-4小節間3拍目の音だけを抜粋すると、Dis-Cisになることが分かります。
次に5-6小節間、メロディーはCis-his、7-8小節間、3拍目のメロディーだけを抜粋するとH-Aですね。これらの音程は全て2度です。
この8小節間を2つに分けると、1-4,5-8,と単純に分かれます。仮に1-4だけを考えてみましょう。メロディーラインはEーDis DisーCis です。議論となるところは、1-2小節間と3-4小節間の強弱関係です。メロディーが、E-Disと来ていれば、当然ですがEよりもDisの方を小さくします。また、Dis-Cisと来ていれば当然DisよりもCisのほうを小さく弾きます。
ここで、この4小節間のフレーズは2小節X2と考え、それぞれの最初の音のほうを大きく、後続の音を小さくという考え方ができますね。ところがこれを4小節単位で考えたとき、E-Dis-Dis-Cisとなりますが、この2つのDisはどちらの方が大きいのかという議論になります。 実はこの3-4小節間、版によってはクレシェンドマーキングが書いてある版もあり、1-2小節間よりも3-4小節間の方を大きく弾いてしまう学習者をよく見ます。学習者があまりこれらのダイナミックの関係を意識しなくとも、3-4が1-2より大きくなってしまうのはその音数にあります。音数的には3-4のほうがよほど多いので、自然と音量も上がってしまうのです。
しかしこれを歌として考えたとき、1-2の歌は実に本題であり、表現も強いです。しかしながら、3-4はどちらかというと囁いたり、内緒話のように静かに話している事が想像できます。筆者であれば、この4小節間は2x2に分けても良いのですが、1-2よりも3-4の方が遙かに音量を落とします。ここで1つ重要な注意があります。多くの学習者はこの3-4を弾く際に、2拍目裏拍から3拍目に行くとき、リピートされる音を適当にごまかして抜かします。例えば3小節目の2-3拍はfisが2つありますね。これがはっきりと「2つ」聞こえなければなりません。
では本題に戻ります。4小節単位でフレーズを考えたとき、2度の下行形が2つありますので、右に行けば行くほど音量は小さくなります。しかし5小節目以降を見たとき、1-4で最も低い音であったCisから今度は段々、さらに2度ずつ下がっていくのがわかりますね。9小節目ではGisまで下がってしまいます。
これは、音が高い位置にあればあるほど音は大きくなるというふうに考えたとき、9小節目まで ディミニュエンドをしなければならないなどと思ってしまうのですが、実はそうでもありません。5-8小節間の和音を弾いてみてください。実に甘ったるい、1-4とは全く異なったムードであることが分かります。誰かに何かをお願いしているようにも聞こえます。むしろ1-2よりも表現は強いかもしれません。4小節単位で徐々にディミニュエンドをする秩序をまもりつつ、5-8は新たなフレーズとして扱います。決して1-4より小さくなる必要はありません。
そして表現が最も強いのは、9小節目から始まる2度のフレーズです。このAの音は、サスペンションといって、前の音を引き延ばしている非和声音です。このAがバスのGisと重なり短9度になり、「実に悩ましい2度」となるのです。1-2、5-6,の2度と比べたときこの9小節目の2度は本当に特別な2度ですね。そしてその2度はここを分岐にして上行していきますが、11小節目の同じフレーズと9小節目を比べたとき、上行しているのにも関わらず、11小節目のフレーズの方が柔らかく感じないでしょうか? そうなのです。このワルツのAセクション、実は下行するに従って表現が強くなり、結果的に音量も上がるという「癖」があるのです。25-29小節間をご覧ください。9-12小節間と比べたときに明らかにカラーが異なりますね。この辺りは(26-29)ソフトペダルを使ってでもとても柔らかく、完全に色を変えます。深刻になるのは30小節目からですのでここは元に戻しますが32小節目でこのセクションが終わりますので、たっぷりと時間を取り、文章の最後を読むように、31-32を演奏してください。
続いてAセクションの中のBです。A2とでもしておきます。33小節目からスタートして64小節目で終わります。テンポの話はさておいて、このセクションも下行してたどり着く39小節目に向かって行くに従い、音量がアップします。45小節目ナポリの6という和音です。上行して行くに従ってディミニュエンドしてください。
さて、奏者が困るのが49-64小節間で、なぜならばppというダイナミックが書いてあるからです。それでは前の39-48小節間との違いをつけるのにはどうしたら良いのかという問題が起きます。このセクション、49-64をpp弾くのは大変至難な技ですが、そうすると39-48の音量を少し上げなくてはなりません。このジレンマが実に難しいのです。これは筆者からの提案ですが、39-48は普通にpで演奏し、49-64はペダルを極力少なめにしてみてください。それでかなりのppが出せるはずです。
65小節目からはBセクションになります。このセクションは、音が高い位置にあるほど感情は高ぶると思っていただいて間違いありません。65よりも70が大きく、70よりも73が大きく、75でピークを迎えます。ただやたらと音量のみを上げてしまうと乱暴になってしまうこともありますので、ブローディングなどをかけ、75小節目の3拍目Desにはゆっくり時間を取って達してください。筆者の個人的な感情を述べるのであれば、筆者はむしろ77小節目の和音により強さを感じます。ここが最も大きくなる場所でも良いと思います。
解説 : 齊藤 紀子
(186 文字)
更新日:2019年6月25日
[開く]
解説 : 齊藤 紀子 (186 文字)
嬰ハ短調、テンポ・ジュストは、ナタニエル・ドゥ・ロスチャイルド男爵夫人に捧げられた。前曲と同様に、3部形式で書かれているが、主題の1つがリトルネロの役割を果たしている。中間部では主音が異名同音の関係にある変ニ長調に転調し、ピウ・レントとなる。長調に転じてもこのワルツの主題が持つメランコリックな性格が消えることはなく、そのことがこの曲に深みをもたらしていると言えるだろう。
ピティナ&提携チャンネル動画(7件)
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (58)

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)学研プラス

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

ミュージックランド

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)学研プラス

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ミュージックランド

(株)リットーミュージック

(株)全音楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)全音楽譜出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ハンナ(ショパン)

ミュージックランド

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ドレミ楽譜出版社

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

ハンナ(ショパン)

(株)リットーミュージック

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)共同音楽出版社

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

KMP(ケイ・エム・ピー) ケイエムピー

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)共同音楽出版社

デプロMP

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ミュージックランド
![ショパン ワルツ集[遺作付] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/2392.jpg)
(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社
![[標準版ピアノ楽譜]ショパン ワルツ集 遺作付 - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/2754.jpg)
(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ポーランド音楽出版社

ジェスク音楽文化振興会

(株)東音企画(バスティン)

ハンナ(ショパン)

(株)学研プラス

ミュッセ