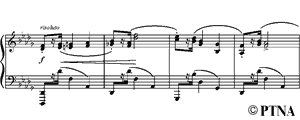作品概要
解説 (1)
マズルカ第20番の解説 : 菅野 雅紀
(3843 文字)
更新日:2010年2月1日
[開く]
マズルカ第20番の解説 : 菅野 雅紀 (3843 文字)
作曲年:1836~37年
出版年:1837年11月(イギリス)
1837年12月(フランス) 1838年1月(ドイツ)
献 呈:A Madame la Princesse de Wurtemberg, nee Princesse Czartoryska
《4つのマズルカ》作品30は1836年から手がけられ、1837年に完成した。この2年間のショパンの話題といえば、ほぼマリア・ヴォドジンスカとの恋愛とその破局に尽きるといえるだろう。1835年9月のマリアとの出会いの後、パリに戻ったショパンは病に倒れてしまう。その病状はひどく咳き込み血を吐き、高熱で幻覚をみることもあったという。ショパンの姿を見なくなったと、人々の間では死亡説がささやかれるほどであった。しかし、翌1836年に入り徐々に体調は回復し、7月にはショパンはチェコのマリアンスケー・ラーズニェでマリアと再会する。このとき、マリアは水彩でショパンの肖像画を描いており、ショパンはマリアに《練習曲》作品25-1、2を教えたという。そして、ショパンは当時17歳のマリアに求婚し、両親にも条件付きで認められた。
マリアの両親、とりわけ母のテレサが出した条件とは、ショパンの健康面に関するものであった。すでに前年の冬に死亡説が流布するほどの大病をしていたショパンに対して、体を大切にし、夜遊びを避け、暖かく養生することなど注意していた。しかしショパンはこの指示を守らなかっただけでなく、それからも体調を頻繁に崩すことを繰り返していた。娘の夫として健康面に大きな不安を感じていたマリアの母テレサの意向もあり、1837年の夏、ショパンのもとには「ごきげんよう、私たちのことをどうぞお忘れなく」という別れの手紙が届くことになる。ショパンはヴォドジンスキ家からの書簡をひとまとめにし、「わが悲しみ」と書き込んだ。
ハ短調 作品30-1 ― Allegro non tanto
所収情報:
パデレフスキ版:No.18 / エキエル版:No.18 [Series A]
ヘンレ版:No.18 / コルトー版:No.18
悲しみに満ちた冒頭主題と、愛に溢れる中間部といった様相の三部形式AABB’AA’になっている。AからBは大きなスラーがかけられ、この形式を超越したところに音楽が描き出されている。
中間部の終わりでニ音を中心に揺れ動く旋律は、「超えられない壁」(ト音)を乗り越え、最後に変イ音に到達した後、冒頭主題に回帰する。この部分に付けられた和音は、ト音と嬰ヘ音が激しくぶつかり合うことで、不協和に響く。この嬰ヘ音は、ハ短調の5度上の5度からの、ト長調としての借用音がハ短調のジプシー短音階(第4音を半音上げた短音階)へと置き換えられたものと考えられる。
ショパンはしばしばこのジプシー短音階をマズルカに用いているが、本作品の旋律にはこの民族的な響きの音階は現れない。それに代わり、旋法的なこの音階を和声的に用いることで、激しい不協和音を作り出している。この不協和な響きは、恋愛や体調の思わしくないショパンの耐えきれない苦痛の表現といえるかもしれない。
和声進行の妙は楽曲の最後にも凝らされており、最後の2小節ではペダルを離すことで低音の支えを失ったハーモニーが、下属和音を響かせた後、主和音に戻ることなく締めくくられる。この予期せぬ結末と、最後に残されたハ音によって、本作品の哀愁はさらに深いものへと昇華される。
ロ短調(-嬰ヘ短調) 作品30-2 ― Vivace (Allegro)
所収情報:
パデレフスキ版:No.19 / エキエル版:No.19 [Series A]
ヘンレ版:No.19 / コルトー版:No.19
ロ短調の主題からはじまり、3つの主題が次々とあらわれるAABBCCBBという形式によって構成される。他のショパンのマズルカでは、ロンド風の巡回形式や三部形式、あるいはそれらが組み合わされた複合三部形式をもつものが多いが、本作品は冒頭の主題が回帰しない珍しい形式である。
主題Aを導入部(i)と考えれば、楽曲の構造はiiBBCCBBという単純な三部形式の一種ととらえることもできる。それぞれの主題の調性をみると、主題Aはロ短調、主題Bは嬰ヘ短調、主題Cはイ長調であり、B-C-Bの三部形式的部分は、イ長調と嬰ヘ短調という、並行調の関係によっている。さらに主題Cでは、2小節の同じ旋律を繰り返しながら、嬰ヘ短調とイ長調を往来しており、作品の大半を占める主題Bと主題Cによる楽想は、嬰ヘ短調を中心に展開している。
その一方で、ショパンが楽譜上に示した調号(シャープ2つ)から、本作品の主調が主題Aのロ短調であると考えられ、この唯一の主調による主題Aを導入部は考えにくい。このような複雑な調性を表現するため、パデレフスキ版などでは、この作品を「ロ短調-嬰ヘ短調」と表記している。
ここで、なぜショパンは楽曲の途中で調号を変更しなかったのかという疑問が生じる。ショパンは作品17以降のマズルカで、作品途中に調号の変更を書き入れる記譜を用いるようになっており、同様の手法は本作品の前後に位置する作品24や作品33の中にもみられる。すなわち、ショパン自身はこの作品を「ロ短調」の作品として強く意識していたと考え得る一方、ロ短調の譜面に嬰ヘ短調を書くにはシャープをひとつ加えるだけでよいため、単純に記譜の簡便性から、調号を変える必要性を感じなかっただけかもしれない。この問題に対する最終的な解釈については、それぞれの演奏者や聴き手に委ねられているといえる。
変ニ長調 作品30-3
所収情報:
パデレフスキ版:No.20 / エキエル版:No.20 [Series A]
ヘンレ版:No.20 / コルトー版:No.20
8小節の序奏につづき表れる冒頭主題は、作品30の4曲で唯一回帰するものである。この16小節にわたる冒頭主題は、他の多くのマズルカと同様、2小節の短い動機の変奏や繰り返しによって形作られている。マズルカの多くは、2小節の動機を2つまとめて4小節、それが2つまとまって8小節のまとまりを作っているのに対して、この作品の冒頭主題では構造の複雑性が大きく高められている。
最初の2小節にあらわれる上行形の動機(a)には、対をなす下行形の動機(b)が続けられ、聴き手は再び動機(a)の出現を期待する。しかし、それに続くのは動機(b)を同主短調に変容させたものである。さらに動機(b)が続き、8小節の主題前半はa-b-b↓-bと構成される。このように下行形の動機(b)を中心に展開される前半部に対して、後半部では拡大された動機(a)と、その完全な逆行形(a’)が対になってあらわれ、最後にはその4小節の組み合わせが同主短調に変容される。すなわち、冒頭主題の後半はa-a’-a↓-a↓’という構成になっており、主題前半とはその構造が異なっている。このように、動機の発展技法を大きく発展させることで、本作品の冒頭主題では、その詩的表現の可能性を大きく高めることに成功している。
作品全体の形式は作品7-3のマズルカにきわめて近く、つぎつぎと新しい主題が表れ、最後に冒頭主題へ回帰する形式i||:A: ||BBCCDDtAとなっている。冒頭主題が回帰するという観点からは一種の三部形式と考えることもできるが、中間部にしては多くの主題が現れ、形式的な曖昧性が持たされている。冒頭主題の動機発展において、期待される繰り返しを避けているのと同様、作品全体にわたっても、期待される冒頭主題の回帰を遅らせることで、作品に思いがけない光を投げかけることを意図しているといえる。なお、作品30ー1で和声的に用いられていたジプシー短音階は、この作品の冒頭主題では音階本来の旋法的な用法によって旋律線に用いられている。
嬰ハ短調 作品30-4
所収情報:
パデレフスキ版:No.21 / エキエル版:No.21 [Series A]
ヘンレ版:No.21 / コルトー版:No.21
それぞれが特徴的な個性をもつ作品30の4つのマズルカの最後に位置づけられたのは、139小節という大規模な嬰ハ短調の本作品である。一組のマズルカの最後に大規模な作品を配置するのは、作品17以降のマズルカに共通してみられる特徴である。作品は、iAABBCiAcodaと、比較的はっきりとした三部形式を示している。
5度上の5度にあたる嬰ニ音を中心に揺れ動く序奏は、5度の嬰ト音に5度下行した後、主和音とともに苦渋に満ちた冒頭主題へと導く。この冒頭主題は上行や下行を繰り返しながらも、決して長調を響かせることなく、対を為す次の主題へと移っていく。そして中間部の前半にあたるこの主題、やはり長調を響かせることなく、ただただ暗雲に包まれるかのごときである。
本作品でわずかな光明が見いだされるのは、第65小節からの中間部後半である。ここでは、短調の響きが顔をのぞかせながら、それを振り払うかのごとくロ長調へ向かって転調を繰り返す。しかしロ長調に到達しようかというとき、不意に序奏が再現し、苦しみの嬰ハ短調へと引き戻されてしまう。
マリア・ヴォドジンスカとの破局に対するショパンの苦悩をひたすらに表現しているかのような作品ではあるが、その暗さが、随所にみられるショパン独特の繊細な美しい変奏をより一層引き立て、そこに魔法の一瞬がうまれる。
ピティナ&提携チャンネル動画(2件)
楽譜
楽譜一覧 (4)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス