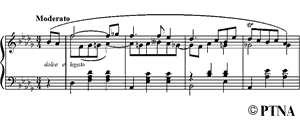作品概要
解説 (3)
解説 : 安川 智子
(452 文字)
更新日:2019年1月31日
[開く]
解説 : 安川 智子 (452 文字)
《ワルツ》 変ニ長調 作品70-3 没後出版
【作品の基本情報】
作曲年:1829 出版年:1855 (Paris,Berlin)
献呈:なし
【楽譜所収情報】
パデレフスキ版:No.13(フォンタナ版)/エキエル版:(BN20) [B]-3番/コルトー版:No.13/ヘンレ版:No.13/ペータース版:(No.10)
ポーランド時代の1829年~30年の間に作曲された5曲のワルツのひとつ(作品69-2参照)。ワルシャワ音楽院のコンスタンツァに恋をしたショパンが、「彼女の霊感を得て小さなワルツを書きました」、と友人ティトゥスにこの変ニ長調のワルツを送っている。1855年の出版譜(フォンタナ版)以外の一次的資料は一切失われている。
初期のワルツに多いダ・カーポを用いた3部形式(A-B-C-A-B)である。右手が受け持つ旋律は二声の独立した声部書法で書かれ、それをワルツのリズムが伴奏する。変ト長調に転調をしたCでは伴奏が内声に割り当てられ、外声が並進行で美しいハーモニーを奏でている。
(2010.2.安川智子)
演奏のヒント : 大井 和郎
(1147 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (1147 文字)
第13番 Op.70-3 Des-Dur
このワルツは、ショパンが元来持っているポリフォニーの強い要素が十分出ているワルツです。このワルツの重要なポイントはバランスです。このバランスをどうとるかによって演奏に雲泥の差が出ます。バランスと言っても左右の手のバランスではなく、すでに2声で書かれてある右手の問題です。
冒頭から見ていきましょう。1-4小節間、右手上声部のメロディーラインのほかに、内声が入ってきますね。この内声は1や2の指で取らなければならなく、力の強い1の指はついつい大きく音が出てしまいがちですが、その辺りを気をつけなければなりません。内声と外声がはっきりと区別がつくような演奏が望ましいです。例えば、1小節目の最初の上声部のメロディーは2分音符のFですが、3拍目でタイとなり、裏拍のGesに行きます。このとき、Fは、伸びている事になるのですが、そのFを耳で聴き続けて欲しいです。別の言葉で言うと、下の声部が入ってきてもFの伸びを邪魔しない音量で内声を弾き、バランスを取ります。結果、下の声部は可能な限りppで演奏します。
学習者はこの内声が、1-4小節間全く休みが(休符が)無いことに注目し、指やペダルで繋がなければならないのですが、よく発生する事例としては、小節が変わるとき、右手の1の指で、前の小節からタイになっている音を切ってしまうことです。各小節の1拍目を弾いたとき、前の小節で伸ばされた3拍目の音が聞こえるように確認してください。大変重要なことです。
17小節目からはA2のセクションになります。17-18小節間と、19-20小節間ではムードが全く異なりますので、違いをつけます。21-23小節間、実に悩ましい和音がありますので、ここは大きくて良いと思います。十分に歌ってください。さて、このセクションも内声はできる限りppで演奏して下さい。つまりはtopを出してください。
33小節目からはBセクションが始まります。このセクション(33-49小節間)、右手上声部がメロディー、下声部は伴奏形となり、左手はバスの役目も果たすもう1つのメロディーが存在しています。このセクションは2重唱と考えます。繰り返しもありますので、2回目は1回目と異なった演奏で弾きます。例えば、1回目は右手の上声部をはっきりと出し、2回目は左手のメロディーをはっきりと出す、ような違いをつけます。
40小節目は1つ目のゴールです。トリルを長めに演奏して少しゆっくりとしても良い場所だと思います。2つめのゴールは48小節目になります。
55からはB2です。このセクションもtopをきれいに出します。また、繰り返しもありますので、ここも2回目は1回目と異なった何かを行ってください。
解説 : 齊藤 紀子
(145 文字)
更新日:2019年1月31日
[開く]
解説 : 齊藤 紀子 (145 文字)
3曲目の変ニ長調は、1829年の作とされる。3部形式によるモデラート。献呈はされていないが、ワルシャワ音楽院での学生時代に知り合った声楽の学生、コンスタンツィア・グウァドコフスカのことを想って作曲したとされる。右手は2声からなり、演奏に際してはこの2つのラインを弾き分けることが大切である。
ピティナ&提携チャンネル動画(2件)
楽譜
楽譜一覧 (12)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)共同音楽出版社

(株)ドレミ楽譜出版社
![ショパン ワルツ集[遺作付] - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/2392.jpg)
(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社
![[標準版ピアノ楽譜]ショパン ワルツ集 遺作付 - 楽譜表紙画像](https://ptna-assets.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/enc/books/2754.jpg)
(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

ポーランド音楽出版社

ジェスク音楽文化振興会