作品概要
解説 (2)
解説 : 樋口 晃子
(1189 文字)
更新日:2019年2月9日
[開く]
解説 : 樋口 晃子 (1189 文字)
Deux nocturnes op. 27
この2曲のノクターンは1835年に作曲され、初版はパリ(M. Schlesinger, 1836)、ライプツィヒ(Breitkopf und Hartel, 1836)、ロンドン(Wessel, 1836)で出版された。オーストリア駐仏公使夫人であったダッポニィ伯爵夫人に献呈。身分の高い彼女の捧げたことから、「貴婦人の夜想曲」と呼ばれることもある。また、1組の作品としてまとめられているが、これら2曲の曲想は互いを引き立たせるかのように、著しい対照をなしている。
No. 2
この曲は、ショパンが唯一ロンド風(A, B, A’, B’, A’’, B’’, Coda)の形式で書いたノクターンで、AとBの2つの主題が交互に3度繰り返されるという構造をもつ。Aの甘美な旋律と全体の優美な曲想ゆえに、作品9-2(2番)や作品15-2(5番)と並んで、演奏される機会の多い曲である。
第2番も第1番同様に、左手には曲全体を通して、フィールドが好んで用いた、大きな跳躍を含む分散和音の伴奏型が用いられている。A(A’, A’’)は常に変イ長調で現れる。A’(第26小節~)とA’’(第46小節~)はAとほぼ変わらないが、その都度、右手の単旋律に装飾的変化が加えられている。例えば、A’ではピアノという楽器でこそ可能な速いパッセージ(m. 32)や、A’’では非和声音をふんだんに盛り込んだ即興的なパッセージ(第51~52小節)が挙げられる。このように、回数を重ねるごとに装飾の使用程度は高くなり、それに比例して高音のきらめきが際立つ。これらの装飾音は、ダンパー・ペダルを踏みっぱなしにしても高音部は濁ることなく、むしろ透明で輝きのある音響が得られた当時の楽器の特性を十分に考慮して作曲されている。
Bでは、Aの単旋律の主題に対し、3度や6度といった重音からなるもう1つの主題が現れる。第10小節に始まるBでは、転調による気分の高揚に合わせて音量が増すと、その音程はオクターヴにまで拡大される(第18小節)。最終的には、fzや左手バス声部のアクセントが手伝って、B’の第 42~45小節でクライマックスを迎える。続くA’’へはAの再現として主題に静かに戻るのではなく、ffのままA主題が回帰し、直前の曲想はしばらく保たれる。主題Aのこの再現法は、作品32-2(10番)にも見られる。
そして、このノクターンで特に注目したいのは、異名同音の使用である。例えば、第24小節では右手のcisをdesと読み替えることで、変イ長調のA’への移行をスムーズにしている。また第34小節では、前の小節の右手のdesをcisと読み替え、変イ長調からイ長調への瞬時の遠隔転調を可能にしている。こうした移ろいゆく調性は、鍵盤上で即興的に手を動かす過程で見出されたものであろう。
演奏のヒント : 大井 和郎
(1506 文字)
更新日:2018年3月12日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (1506 文字)
第8番 Op.27-2 Des-Dur このノクターンの左手の伴奏形をまず見ていただきたいです。ただの1小節として、16分音符の伴奏形がなくなっているところはありません。一貫して最後まで16分音符の伴奏形は続きます。つまり、流れを止めない事が重要になってきます。ところが右手を見ると、わざわざその流れを止めることが目的のように実に数多くの音符が全体にわたって書かれています。この曲の演奏のヒントとしては、右手のパッセージをスムーズに弾き、左手の流れをできる限り止めないようにする事に尽きます。 しかし誤解していただきたくないのは、だからといってin tempoで淡々と進むのではなく、時間を取るべきところは取り、細かい音符のパッセージを無理なく、速すぎず、機械的にならないように演奏し、かつ左手がある1音だけ長く伸びたり、止まったりしないように心がけます。従ってルバートは必須であり、基本的な流れの中でテンポの自由な調整が必要になります。例えば、20小節目の2拍目、右手に32分音符がオクターブで入ってきます。これをオンタイムで弾いてしまえば、とても機械的になりますし、堅く聞こえてしまいます。またこの部分だけ音量が大きくなります。ストレスがかかるのは1拍目のBes と As であり、2拍目は衰退していく様子を描写しなければなりません。そのためには少しだけ2拍目で時間を取らないことには、32分音符をスムーズに弾くのは不可能に等しいです。 このような箇所が随所に見られますね。奏者は臨機応変にそのようなパッセージに対応し、自然に音楽が流れるように心がけてください。とはいえ、中には技術的に困難なパッセージもあります。例えば32小節目の2拍目の右手です。ついつい、オンタイムで弾かないとという呪縛があると、このようなパッセージは雑になりがちです。しっかりと部分練習をするのですが、例えばこのケースの場合、3連符を一つ一つ練習するよりも、3連符の1つ前の音から3つ抜粋して練習をする方が遙かに効果的です。つまりは、指番号125を練習するようにします。 このように、オクターブ以上離れている広い跳躍のパッセージを練習する際は、軸となる真ん中の音を決めます。この場合は3つしかありませんので、当然2の指が担当する真ん中の音が軸音になります。As Es C で試してみましょう。 1 Es に2の指を置きっ放しにします。その状態でAsを弾きます。 2 次に同じ状態で今度はCを弾きます。次に、CからAsに戻ります(もちろん2の指はEsに置いたままです)。 3 今度はAsからCへ。この動作を素早くできるように段々と速度を上げていきます。音は、AsC CAs AsC CAs の繰り返しになります。 4 つぎに、As Es C をループさせ、As Es C Es As Es C Es と弾いてみましょう。この動作を行ったとき、困難さを感じなければこのユニットは弾けるようになります。 できたら次に、A E Desを同じように練習します。そして4つのユニット全て練習が終わったら、前半2つ、後半2つに分けて練習します。多くの奏者は、左手と合わせた時、後半の方にトラブルがあります。それは右手が原因ではなく、33小節目で左手が低いDesに飛ぶので、それが心配になり、気持ち的に焦ってしまい右手を間違います。練習の際、33小節目には行かず、32小節目の最後の音で止めて練習をしてみてください。 52小節目のような、長い細かいパッセージを練習する際も、例えば、前半と後半に分けて練習をすると良いでしょう。
参考動画&オーディション入選(9件)
楽譜続きをみる
楽譜一覧 (17)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)リットーミュージック

(株)全音楽譜出版社

(株)シンコーミュージックエンタテイメント

(株)リットーミュージック

ハンナ(ショパン)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社
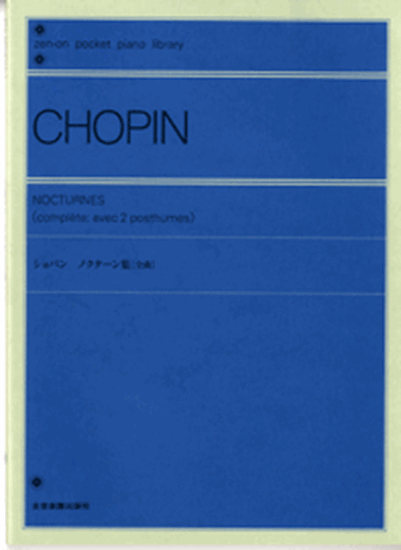
(株)全音楽譜出版社

ポーランド音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)音楽之友社

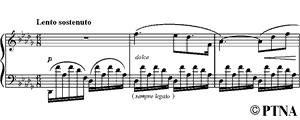
 第8番 - 演奏動画のサムネイル](http://i.ytimg.com/vi/rZF1OR0Fxgo/mqdefault.jpg)
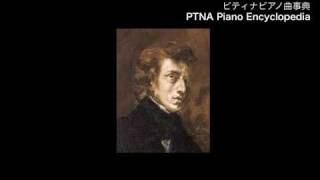


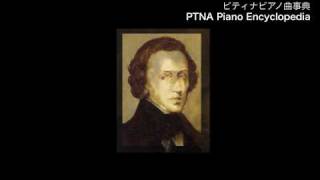







![ノクターン[夜想曲] 第8番 - 演奏動画のサムネイル](http://i.ytimg.com/vi/F3FwjvE4vGU/mqdefault.jpg)

