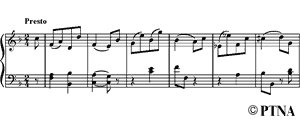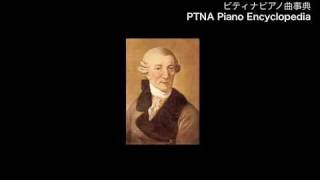ハイドン : ソナタ 第38番 第3楽章 Hob.XVI:23 op.13-3
Haydn, Franz Joseph : Sonate für Klavier Nr.38 Mov.3 Finale: Presto
作品概要
ジャンル:ソナタ
総演奏時間:3分00秒
著作権:パブリック・ドメイン
ピティナ・ピアノステップ
23ステップ:応用6 応用7 発展1 発展2 発展3
楽譜情報:7件解説 (1)
解説 : 大井 和郎
(566 文字)
更新日:2025年3月5日
[開く]
解説 : 大井 和郎 (566 文字)
この第3楽章に限らず、ハイドンの作品を、現代のピアノで弾く際に、是非覚えておきたいことがいくつかあります。まず、「ペダルの多用」に注意をする事。自宅で練習していると、部屋は、多くの場合残響はありませんので、かなりドライに聞こえ、ペダルをつい入れたくなるのですが、これがホールで演奏となると、自宅のようにクリアーに聞こえなくなります。 例えばこの楽章の場合、28~30小節間にペダルを入れると左手の4つの音も加わり、右手の16分音符がクリアーに聞こえなくなります。それから音階を基本としているパッセージにペダルを入れると濁りが生じます。ペダルは最小限に留めてください。 もう1つの注意点は、余計な箇所で音楽を止めない事。古典派の音楽は器楽であり、アンサンブルであり、指揮者が指揮をする音楽で、その流れは止めてはなりません。強調したい部分、カラーを変えたい部分など、状況に応じて、決して聴く側が、拍を失うことの無いように注意して下さい。 その他、フレージングに関して。冒頭8小節には、2小節ずつのフレーズが4つあると考えます。その時に、この4つが全く同じダイナミックレベルであることは、音楽そのものが平坦になります。その場その場の心理状態を察し、 4つのフレーズを異ならせて弾くようにします。このような、音楽的な解釈 と演奏も必須です。