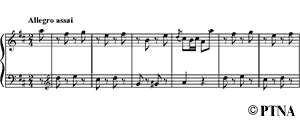ハイドン : ソナタ 第30番 第3楽章 Hob.XVI:19 op.53-2
Haydn, Franz Joseph : Sonate für Klavier Nr.30 Mov.3 Finale: Allegro assai
作品概要
解説 (2)
解説 : 稲田 小絵子
(224 文字)
更新日:2020年2月9日
[開く]
解説 : 稲田 小絵子 (224 文字)
第3楽章:フィナーレ。アレグロ・アッサイ、ニ長調、2/4拍子。変奏的なロンド形式。
主題は左右の手によって交互に音を発し、まるで打楽器のように奏されるのが印象的。それは提示されるたびに変奏され、右手が十六分音符によって主題旋律を彩る。間に挟まれる2つのエピソードはそれぞれニ短調とイ長調。どちらも、高音の明るい主題とは対照的に比較的低音域を使うが、前者の短調はユニゾンで響きの太さを出し、後者の長調は、オクターブのトレモロによって激しさを表している。
演奏のヒント : 大井 和郎
(523 文字)
更新日:2025年1月26日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (523 文字)
2つ注意点があります。1つはタイミングの話です。特に、初めてこの曲を聴く人達の為にも、拍を誤って認識させてしまう様な演奏は避けるようにします。要はメトロノームのように寸分の狂いも無くタイミングを正確に弾くようにします。例えば、36小節目の2拍目裏拍がDのオクターブになっていますが、これが1拍目の表拍として聴かせないようにします。それには、セクションが変わるとき、絶対に余計な時間を取らずに次のセクションに行くようにして下さい。少しでも時間が狂うと、拍も狂って聞こえてしまいます。
もう1つは、音が交互に、右、左、と来るセクションがあります。例えば、33~34小節間もその例です。この33~34小節間はまだ判りやすいのですが、1~16小節間、上の音(右手)と下の音(左手)は、2つの声部と考えます。この2つの声部を同じに弾くと、ADFisEGCisEDFis と聴き手には聞こえます。本当は、A Fis G E Fis が上の声部であり、D E Cis D が下の声部ですので、上と下とでは、音量を変え、2声が混同されて聞こえないように工夫して下さい。
1~16小節間は後半でオクターブになりますが、そこでも同じく、2声の音量と音質を変えてください。
ピティナ&提携チャンネル動画(0件)
楽譜
楽譜一覧 (6)

ヘンレー

ヘンレー

ヘンレー

(株)音楽之友社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス