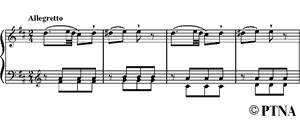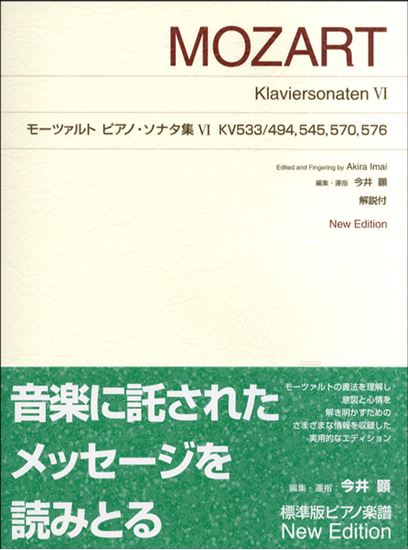モーツァルト : ピアノ・ソナタ 第18(17)番 第3楽章 K.576
Mozart, Wolfgang Amadeus : Sonate für Klavier Nr.17 Mov.3 Allegretto
作品概要
解説 (2)
解説 : 岡田 安樹浩
(606 文字)
更新日:2019年3月5日
[開く]
解説 : 岡田 安樹浩 (606 文字)
第3楽章 二長調 4分の2拍子 ロンド・ソナタ形式
ロンド主題は舞曲風の性格をもち、和音の刻みによる単純な伴奏をもって提示されるが、伴奏声部はすぐに16分3連音符の技巧的なパッセージへと変化する。この16分3連音符は分散和音へと変化し、楽曲の中心的な構成要素となる。
属調へ転じ、ロンド主題の動機がレスポンソリウム風に発展し(第26小節~)、16分3連音符による推移的なパッセージをはさんだ後に、順次下行を特徴とする和声的なクープレ主題が提示される(第51小節~)。そして、16分3連音符による分散和音の上下行による推移を経て、冒頭主題が回帰した後(第65小節~)、推移部が変形してヘ長調へと至る。
中間部は冒頭主題の動機が発展し、多声的に展開する。ヘ長調からト短調、イ短調、ロ短調、ホ短調を経てニ長調へと至り半終止する。
前半で属調主題を導入した、冒頭動機によるレスポンソリウム風の楽想が主調であらわれ、クープレ主題を主調で再現する(第142小節~)。16分3連音符による分散和音の推移を経てロンド主題が回帰して楽曲を閉じる。
第3楽章は、発展的な中間部とクープレ主題の主調再現をもっており、ソナタ形式的な調性配置と、動機展開的な発展をもったロンド形式といえるだろう。
K.576のソナタは、その両端楽章が多声的な発展と動機の展開に主眼が置かれており、モーツァルトのクラヴィーア・ソナタ全曲の中でも異彩を放つ作品といえる。
演奏のヒント : 大井 和郎
(677 文字)
更新日:2025年10月9日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (677 文字)
これ以上楽しいことは無い位に楽しい表現です。わくわくするような楽しさを表現して下さい。連続する16分音符の3連符が楽しさを増幅させます。この第3楽章にも2人以上のキャラクターがいて、2人のキャラクターの掛け合いになります(例:26〜29小節間、95〜130小節間等)。
異なった声質を持った2人が歌っているように表現してみて下さい。
冒頭のテーマの処理の仕方ですが、1〜2小節間よりも、3〜4小節間の方がテンションが高まります。そのまま、5〜6小節間を最初のフレーズのピークポイントしても構いませんし、1〜4小節間、テンションを上げておいたところで、5〜6小節間と音量を落として軽さを出す奏法も1つの奏法です。1つ確かなことは、1〜2小節間のフレーズよりも、3〜4小節間のフレーズの方がテンションは高まりますので、これと同じ素材が出てくる部分、例えば、9〜12小節間も、1〜4小節間と同じテンションの高め方をして下さい。
この第3楽章の注意点としては、16分音符の3連符が出てくるとき、全体のテンポが走らないようにしてください。3連符が出てきても、1小節目と同じテンポで演奏して下さい。
そしてこの3連符の音量なのですが、主観的な話になります。普通に弾いても、これ程の数の音符が並べば自然に音量は大きくなります。メロディー音を消さない程度に音量を留めておく方が良いのではないでしょうか?
ピティナ&提携チャンネル動画(3件)
楽譜
楽譜一覧 (9)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス