作品概要
解説 (2)
演奏のヒント : 大井 和郎
(473 文字)
更新日:2024年5月14日
[開く]
演奏のヒント : 大井 和郎 (473 文字)
この曲を絵画的描写と考えた上でのお話しです。この曲は、はっきりと旋律を出すと言うよりは、ぼやけた、ぼんやりした、水彩画のようなイメージが欲しいところです。その上で、ペダルは必須となりますので、まずは学習者が幼い子供である場合、ペダルの基礎から学ばせることをお勧めします。そしてペダルは、濁りがなかなか判らない場合や、環境もあります(部屋の造り等)。できる限り、反響の少ない部屋で、できる限り、調律されているピアノで、注意深く濁らないように音楽を進ませますが、左手は、例えば、1~4小節間は全く同じですので、濁り自体がわかりにくいところもあります。
そこで、右手のみでペダルの練習をしてみて下さい。1拍目の音のところで、前の音が残っていたり、濁ったり、あるいは切れたりしなければ成功です。
その上で、1~4小節間、5~8小節間、9~10小節間、11~12小節間、13~16小節間の、5つのフレーズを全て、異なった音質と音量、異なったムードで弾くようにします。
個人的には、この曲にルバートはありだと思っています。自由にテンポをコントロールしてみて下さい。
解説文 : 熊本 陵平
(700 文字)
更新日:2024年11月14日
[開く]
解説文 : 熊本 陵平 (700 文字)
主題となる旋律の特徴は、1小節内では分散和音(和音構成音)のみの構成となるが、4小節を俯瞰した時に半音階の下行進行によって形成されていることが分かる。
ハーモニックスピードも1小節1和音で進行していることから、1小節だけでは和声関係は成り立たず、これらを複合的に考えた時、半音階による横の流れを意識して、大きなフレージングで表現することが肝要だろう。
全体の構成としては二部形式。
A[a(1から4小節)+a1(5から8小節)]
B[b(9から12小節)+a2(13から16小節)]
※a2はコーダとして捉えることもできる。
5小節からのa1小楽節は1から4小節のa小楽節と音程・和声共に異なるが、その4小節間の特徴として半音階の下行進行であることなど共通する特徴が多く見られるため、a小楽節の変異(展開)形の小楽節と捉えてa1とした。開始小節が同じ音であるa2小楽節の方が元々のa小楽節に近い。
9小節から4小節間は2小節ごとのゼクエンツとなっており、フレージングもA楽節では4小節が一つに対してb小楽節においては2小節が一つとなっている。このb楽節においても、半音階の下行進行の流れは変わらず、a楽節では右手にあった半音階進行がb楽節では左手の方にある。このことから10小節は3拍目に四分休符があるものの、次小節へ向かって下がってゆくという全体の大きな横の流れは意識すべきだと考える。
a2楽節は主和音Ⅰのみであり、その性質はコーダだと捉えることができる。Ⅰの7和音で終結しており、その第7音が付点二分音符をタイで結ばれて終止している。これは不完全終止の一種であり、いかにも近現代作品らしい終止である。
ピティナ&提携チャンネル動画(5件)
楽譜
楽譜一覧 (2)

(株)東音企画
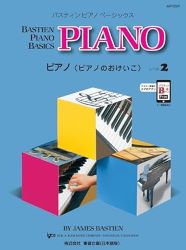
(株)東音企画






