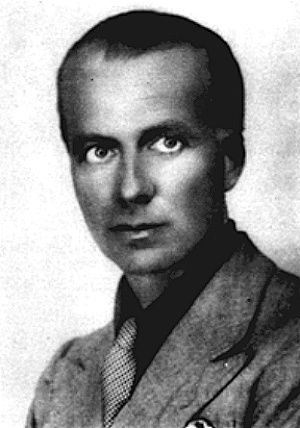
解説:実方 康介 (320文字)
更新日:2010年1月1日
解説:実方 康介 (320文字)
1940年代には12音技法による作曲などを試みるが、音列を用いた作曲法からは離れる。後年は一つの音を微細に変化させていくような、音色重視の作曲法を自己の語法とした。初期作品の「ピアノ・ソナタ」等にもその萌芽がみられる。その音楽語法は主にフランスにおいて発達したスペクトル楽派の創始者、ジェラール・グリゼとトリスタン・ミュライユ(ともにオリヴィエ・メシアンに師事していた)に影響を与えた。同楽派はシェルシの語法の上に理論的な発展を重ねたものであるともいえる。ピアノ作品は1930年代と50年代にその多くが作曲された。その作品数と高い品質から、20世紀のピアノ音楽作家としての再評価が待たれる。
■ 関連リンク ■
執筆者:
実方 康介
<続きを表示する>
作品(21)
ピアノ独奏曲
ソナタ (4)
組曲 (7)

