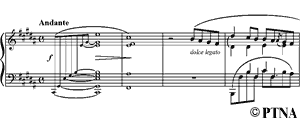作品概要
解説 (1)
解説 : 上田 泰史
(1395 文字)
更新日:2010年1月1日
[開く]
解説 : 上田 泰史 (1395 文字)
Deux Nocturnes Op.62
この二曲は1846年に作曲され、初版はパリ(Brandus, 1846)、ライプツィヒ(Breitkopf und Härtel, 1846)、ロンドン(Wessel, 1846)で出版された。彼の弟子と思われるR. フォン・ハイゲンドルフ=ケンネリッツ嬢に献呈。ショパンが生前に出版したノクターンとしては最後のものである。作品55の二曲に比べ、書法はますますポリフォニクになり、半音階によるうねりは消えて響きは透明度を増す。ここに至って、彼は常に憧れを抱き続けてきたポリフォニックな書法と歌唱的な様式の折り合いをつけ、自分なりの答えを見出したようである。
no.1 ロ長調
第1番は、他の多くのノクターンと同様、A-B-A’と図式化される三部形式による。作品55-2(第16番)と同様、唐突なカデンツかで開始される。冒頭に置かれた和音は第7音が付加されたⅡの和音である。この一見奇妙な出だしは、当時よく行われていた「プレリュード」と呼ばれる習慣に由来するものであろう。「プレリュード」は作品を演奏する前に聞き手の注意を演奏者に向けさせたり、タッチを確かめたりするために行われる短い即興的な前奏で、20世紀初期までは普通に行われていた。バックハウスやヨーゼフ・ホフマンのライヴ録音にはこうした「プレリュード」を聴くことができる。しかし、なぜショパンはわざわざそれを記譜したのだろうか。これはよく検討する価値のある問題であるが、個々での議論はよすとしよう。
「プレリュード」に続く主題は声部数が不定の擬似的なポリフォニーである。この曲の冒頭部分は、バロックのフーガにしばしば見られるように拍節が一定ではない。参照説目の第3拍目に出る主題は、7小節目で再び現れるとき、第1拍目にきている。この主題の下行音型は、第11~14小節目にかけて、右手の内声で利用される。こうしたモチーフによる一貫性の確保はバッハに代表されるフーガ書法の主要な特徴であるが、ショパンはおそらくそれを強く意識している。第14~21小節右手が常に2声となり、8分音符で動く。テクニックの点からみて、こうした多声の動きはクレメンティやクラーマーといった19世紀初期に活躍した先人が用い始めた比較的古いピアノ書法である。続く経過的な第21~25小節目には、Bで使用されるシンコペーションのリズム・オスティナートが現れている。その後に再び主題が回帰し、変イ長調の中間部Bに入る。Bで初めて現れるトリルは、そのままA’の主題再現(第68~75小節)で利用される。トリルの中に旋律を織り込むこの技法は、30年代末から40年代にデーラーのようなヴィルトゥオーゾ・ピアニスト兼作曲家によってしばしば用いられたいわば流行のテクニックであった。ショパンは古い技法だけでなく最新の流行も積極的に取り込んでいるのである。
第75小節で主題が遠隔調のト長調の属七に落ち着くと、再びロ長調に戻るために4小節間の巧みな経過部が続く(第76~80小節)。ここでは、4声部がとりわけ対位法的に扱われており、入念に書かれた部分である。第81小節に始まるコーダでは再び左手のシンコペーションによるリズム・オスティナートが回帰し、その上で右手が増二度を含むいくぶん「エギゾチック」な音階が漂い夢想的な雰囲気のうちに曲は閉じられる。
ピティナ&提携チャンネル動画(10件) 続きをみる
楽譜
楽譜一覧 (13)

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社

ハンナ(ショパン)

(株)ドレミ楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)音楽之友社

(株)全音楽譜出版社

(株)全音楽譜出版社
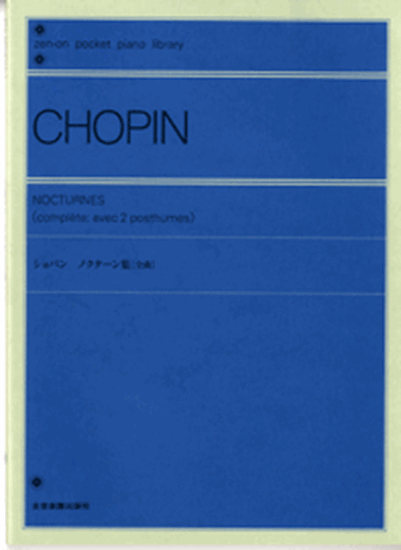
(株)全音楽譜出版社

ポーランド音楽出版社

(株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

(株)音楽之友社