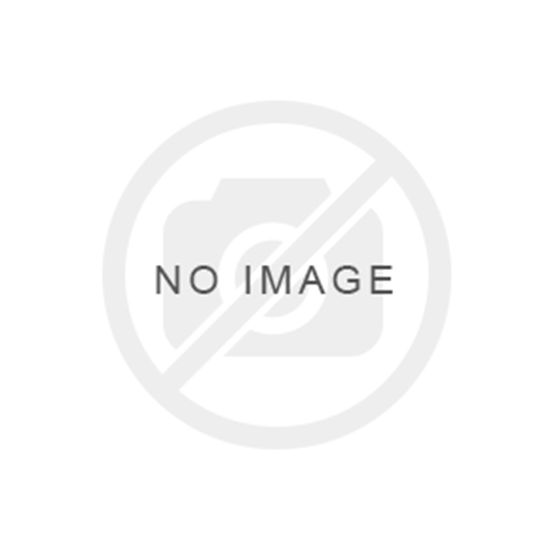作品概要
初出版社:カワイ出版
楽器編成:ピアノ独奏曲
ジャンル:曲集・小品集
著作権:保護期間中
※特記事項:ピアニスト八坂公洋氏によるCD録音はこちら(「くすんだ緑と墓石の子守唄」収録) http://ml.naxos.jp/album/NARC-2105
解説 (1)
解説 : 小室 敬幸
(1164 文字)
更新日:2018年4月25日
[開く]
解説 : 小室 敬幸 (1164 文字)
ピアニスト松谷翠(1943~1994)からの委嘱で作曲され、10曲すべて彼が初演している。 佐藤の音楽を評して松谷は「ロマン派とは異なるが、日本人独特の心象の世界がある。」と語っているのだが、それは本作にも通じている。多くの日本人が心に思い浮かべることが出来るであろう、日本各地の様々な風土や情景の「視覚的な色彩」から触発されて作曲されたからだ。 楽譜には、作曲者自身がインスパイアされた視覚イメージが掲載されている。
第1集(1977)
くすんだ緑と墓石の子守唄
黄と黒との季節
八月の鎮魂
悲しげな顔
短長の跛行リズムを繰り返す〈くすんだ緑と 墓石の子守唄〉は、「祖母のぬくもりへの唄」 だという。土葬されていた祖母の改葬をおこなったある夏の情景。〈黄と黒との季節〉は、 父が亡くなる頃に見た「菜の花の咲く裏日本〔日本海側〕の5月」。おそらくは作曲者が生まれ育った山形県鶴岡市にほど近い三川町(菜の花 まつりが開かれる名所)での光景か? 低音のオスティナートがこびりつく〈八月の鎮魂〉は、 原爆での死者を弔う真夏の情景。供物にはスイカ、外には蝉のこげ茶が見える。〈悲しげな顔〉 は、作曲の2年前(1975年)に終わったばかりのベトナム戦争を写したモノクロ写真。なかには父母を失った痩せこけた少年の姿がみえる。lentoと指示された最後の3小節は、楽曲冒頭と鏡像関係になっているのが興味深い。
第2集(1979)
青い冬
朱の舞
片足で立つ鳥居
〈青い冬〉は、 北国における「雪の降り積もっ た青い朝」の印象を、細かくテンポや曲想を移り変わらせつつ様々な角度から描く。 〈朱の舞〉は、農家のなかで人々とその熱気がローソクの灯りに照らされて乱舞する様だというが、一体何をしているのか? 寒々しい冒頭から歌がつむがれ、 それが次第に舞踊へと姿をかえてゆく。 原爆で一方を失った〈片足で立つ鳥居〉は、長崎の山王神社に現存している。佐藤は尺八独奏のために「片足鳥居の映像」という作品を書いており、そちらでもオクターヴ上がって、2度下がる音型が主題となっていることからも分かるように、片足鳥居を表す音型なのであろう。 灰色になった1945年の長崎。
第3集(1986)
茶畑のある風景
石をのせた屋根のある漁村
笹の絨毯は北海にすべる
〈茶畑のある風景〉は「八十八夜」 、つまり5月頭の茶摘み時期である。色はもちろん「みど り」で、ミの音がシグナルのように鳴り響き続ける。〈石をのせた屋根のある漁村〉は、裏 日本のあまり明るくない浜辺の風景。波打つようなパターンを繰り返すなかで、光、岩、白い波しぶきが表れる。〈笹の絨毯は北海にすべる〉 は、宗谷岬に広がる短い熊笹の原っぱ。切れ目なく海へと続いていく様が、反復する音型に よって力強く描かれてゆく。